医療保険
60代以降の医療保険:老後の医療費不安を解消する

60代以降は、収入が減る一方で、病気やケガのリスクが高まるため、医療費への備えは非常に重要な課題となります。この時期、現役時代に加入した医療保険をどうするか、多くの人が悩みます。保険を継続するのか、それとも解約して貯蓄で備えるのか、老後の家計と保障のバランスを慎重に考える必要があります。
この記事では、60代以降の医療保険の考え方を解説します。公的医療保険の自己負担割合の変更を明確にし、医療保険を継続すべきか、解約すべきかの判断基準、そして生命保険料控除の活用まで。老後の医療費不安を解消するためのヒントを提案します。
公的医療保険の自己負担割合の変更

60代以降は、年齢とともに公的医療保険の自己負担割合が変わります。この制度を理解しておくことが、医療保険を考える上で不可欠です。
年齢別の自己負担割合
69歳まで: 医療費の自己負担割合は3割です。
70歳から74歳まで:
窓口での自己負担割合は、所得に応じて2割または3割です。
75歳以降:
・「後期高齢者医療制度」に移行し、自己負担割合は、所得に応じて1割、2割、または3割となります。
【補足】: 2022年10月からは、一定以上の所得がある75歳以上の方の窓口負担割合が1割から2割に変更されており、医療費負担が増加する可能性があります。
高額療養費制度の活用
・ひと月の自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超えた分が払い戻される「高額療養費制度」は、高齢者も利用できます。
・この制度があるため、公的医療保険の対象となる医療費の負担は、上限額まで抑えられます。
医療保険を継続すべきか、解約すべきかの判断
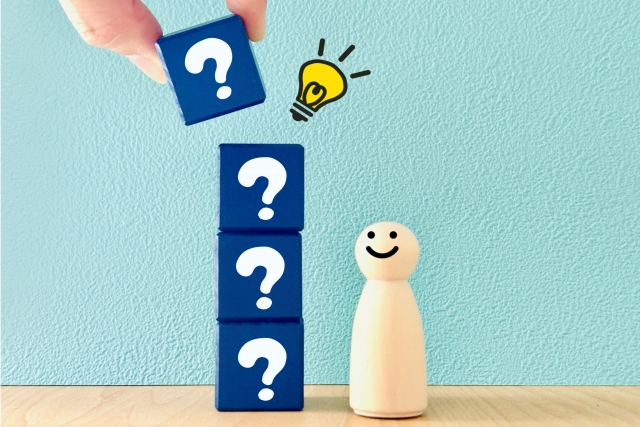
60代以降は、現役時代に加入した医療保険を継続すべきか、それとも解約すべきか、ご自身の健康状態や家計状況を考慮して判断しましょう。
医療保険を継続すべきケース
持病や既往症がある人:
一度解約してしまうと、新しい保険に加入するのが難しくなります。
貯蓄が十分でない人:
万が一の医療費を貯蓄で賄えない場合、医療保険で備える必要があります。
保障内容に満足している人:
先進医療特約など、現在の保障内容に満足している場合は、継続を検討しましょう。
医療保険を解約すべきケース
保険料が家計を圧迫している人:
年金生活に入り、保険料の負担が重くなっている場合は、解約を検討しましょう。
貯蓄が十分にある人:
万が一の医療費を貯蓄で賄えるだけの十分な貯蓄がある場合は、解約も選択肢の一つです。
保障内容が不要になった人:
子どもが独立し、医療費への備えが不要になった場合など、ライフステージの変化によって保障内容を見直す必要があります。
生命保険料控除の活用

生命保険料控除は、医療保険の保険料も対象となります。
生命保険料控除の仕組み
控除額:
医療保険は「介護医療保険料控除」の区分に該当し、年間の払込保険料に応じて、所得税と住民税が軽減されます。
手続き:
会社員は年末調整で、自営業者は確定申告で手続きが必要です。
生命保険料控除の活用
公的年金受給者も、年末調整や確定申告で生命保険料控除を申告できます。
生命保険料控除を最大限活用することで、税金の負担を軽減し、家計の負担を軽くできます。
まとめ:60代以降の医療保険は「必要性」と「家計」で考える
60代以降の医療保険は、現役時代とは異なる視点で考える必要があります。
・公的医療保険の自己負担割合や、高額療養費制度を理解し、民間の医療保険で不足する部分を補いましょう。
・ご自身の健康状態、貯蓄状況、家計の状況を考慮して、医療保険を継続すべきか、解約すべきか判断しましょう。
・生命保険料控除を最大限活用し、税金の負担を軽減しましょう。
この記事を活用して、ご自身に合った医療保険を見つけ、医療費の不安を解消して豊かな老後を実現してください。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



