iDeCo
50代からのiDeCo:受け取り時期と運用期間の最適化
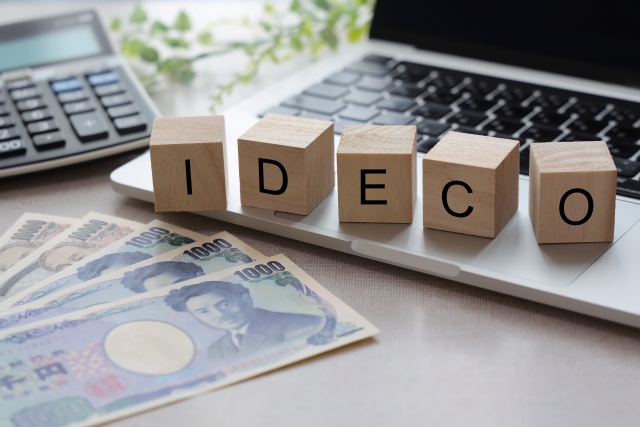
「老後まであと少しだけど、iDeCoの資産ってどう運用して、いつから受け取るのがベストなの?」
50代は、老後資金の準備において、いよいよ「ゴール」が見えてくる大切な時期です。iDeCo(個人型確定拠出年金)は、この時期から始めても税制メリットを享受できますが、20代や30代から始めるのとは異なる戦略が必要になります。特に、運用期間が短くなることを考慮した、「受け取り時期」と「運用期間」の最適化が重要です。
この記事では、50代からiDeCoを始める方、またはすでにiDeCoを運用している50代の方のために、運用期間が短くなることによるリスク・リターンへの影響を解説します。さらに、運用商品の見直し(元本確保型へのシフトなど)や、60歳以降の受け取り開始時期の検討まで、あなたのiDeCo資産を最後まで賢く活用するための戦略を提案します。
50代からのiDeCo:運用期間が短くなる影響

50代からiDeCoを始める場合、一般的なリタイア時期である60歳まで、残された運用期間は10年未満となります。この期間の短さは、iDeCoの運用に大きな影響を与えます。
複利効果の限界と積立額の重要性
・複利効果が限定的: 投資期間が短いため、20代や30代のように複利の力を最大限に活かして資産を爆発的に増やすことは難しくなります。
・積立額の重要性増大: 複利効果が限定される分、目標とする老後資金を達成するためには、毎月の掛金を可能な限り多く拠出することがより重要になります。
【例】55歳から60歳までの5年間でiDeCoに500万円を貯めたい場合、年率3%運用で月額約7.8万円の積立が必要です。
金融庁 つみたてシミュレーターで算出
価格変動リスクの影響大
・回復時間の短さ: 株式などのリスク資産は、短期的に大きく価格が変動する可能性があります。運用期間が短いと、もし市場が大きく下落した場合に、回復するまでの時間がなく、損失が確定してしまうリスクが高まります。
・ドルコスト平均法の効果限定: 積立投資のメリットである「ドルコスト平均法」(高値掴みを避ける効果)も、積立期間が短いと、その効果が限定的になります。
ドルコスト平均法については、以下の記事も参考になります。
ドルコスト平均法とは?時間分散で賢く資産形成!
運用商品の見直し:リスクを抑え、安定性を重視

50代からのiDeCo運用では、運用期間の短さを考慮し、リスクを抑え、安定性を重視した運用商品の見直しが不可欠です。
資産配分を「守り」にシフト
・株式比率の引き下げ: 若年層のように株式比率を高くするのではなく、株式の比率を抑え、比較的価格変動が穏やかな債券や元本確保型商品の比率を高めることを検討しましょう。
【例】株式50%:債券50%や、株式30%:元本確保型70%など、あなたのリスク許容度と残り期間に合わせた配分を見つけます。
・低リスクなバランス型投資信託の活用: 株式と債券を自動でバランスしてくれるバランス型投資信託の中でも、債券比率が高い商品を選ぶのも一つの方法です。
「元本確保型商品」へのシフトを検討
・リスク回避の最終手段: リタイアが迫り、絶対に元本を減らしたくないと考える場合は、定期預金や保険といった元本確保型商品へのスイッチングを検討しましょう。
・注意点: 元本確保型は元本割れリスクはありませんが、その分、期待できるリターンも非常に低いです。インフレが進むと、実質的な資産価値が目減りするリスクがある点も理解しておく必要があります。目標金額まであとどれくらいかを考慮し、慎重に判断しましょう。
運用商品の「スイッチング」を活用
すでにiDeCoで積立投資を行っている場合は、運用商品の「スイッチング」(保有している商品を売却し、別の商品に買い替えること)を活用して、ポートフォリオを調整しましょう。
・スイッチングのタイミング: 年に1回など、定期的にポートフォリオを確認し、リスクが高いと判断したらスイッチングを実行します。
・徐々にシフト: 一度に全額をリスクの低い商品にスイッチングするのではなく、数年かけて段階的に比率を調整していく「段階的シフト」も有効です。
60歳以降の「受け取り開始時期」の検討

iDeCoは原則60歳から受け取りが可能になりますが、最長75歳まで受け取り開始を遅らせることができます。この「受け取り開始時期」をいつにするかという選択は、運用期間の長さや、受け取り時の税金に大きく影響します。
運用を継続して「資産寿命」を延ばす
・60歳以降も運用継続のメリット: 60歳で運用を止めずに引き続き運用を継続すると、その期間も運用益が非課税になります。働ける期間が延びた場合や、他に生活費がある場合は、受け取りを遅らせることで、複利効果をさらに長く享受し、資産寿命を延ばすことができます。
・2025年度税制改正(予定): iDeCoの掛金拠出可能期間は現在65歳未満までですが、2025年度税制改正では70歳未満まで延長が検討されています。 これが実現すれば、60代前半もiDeCoで所得控除を受けながら積立を継続できる可能性があります。
税制優遇を最大限に活かす「受け取り方」とタイミング
iDeCoの受け取り方は、一時金、年金、併用があり、それぞれ税制優遇が異なります。退職金や公的年金の受給額、他の所得などを考慮して、最適な方法とタイミングを検討しましょう。
・一時金受け取り: 「退職所得控除」が適用されます。会社からの退職金が少ない場合や、公的年金の受給開始時期とずらすことで、税負担を軽減できる可能性が高いです。特に2026年1月からは、一時金と退職金の受け取り間隔ルールが「5年」から「10年」に変更される予定であり、これにより税制優遇をより受けやすくなります。
・年金受け取り: 「公的年金等控除」が適用されます。公的年金との合計額が控除額を超えると課税されます。公的年金の受給額が少ない場合や、他の所得がない場合に検討できます。
・併用: 一部を一時金、残りを年金で受け取ることで、それぞれの控除枠を効率的に活用し、税負担を分散させる戦略です。
・専門家への相談: 自身の退職金や年金受給額は人それぞれ異なるため、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談し、最適な受け取り方をシミュレーションしてもらうことをおすすめします。
まとめ:50代からのiDeCoは「計画的な運用と受け取り」が鍵
50代からのiDeCo運用は、残りの運用期間が短くなるという特徴を理解した上で、「守り」にシフトしたポートフォリオへの見直しと、「受け取り開始時期」を戦略的に検討することが成功の鍵となります。
・運用期間が短い分、積立額を最大化し、安定性を重視した運用商品(株式比率を抑える、元本確保型も視野に)へのシフトを検討しましょう。
・60歳以降の受け取り開始時期は、税制優遇を最大限に享受できるよう、他の退職金や公的年金とのバランスを見ながら慎重に決定しましょう。
50代からiDeCoを賢く活用し、あなたのiDeCo資産を最後まで有効活用することで、安心で豊かなセカンドライフを着実に築いていきましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています



