生命保険
養老保険のメリット・デメリット:貯蓄と保障を両立させる保険

養老保険は、万が一の事態に備えながら、満期時には「満期保険金」というまとまったお金を受け取れる、貯蓄と保障を両立させた生命保険です。しかし、その便利な仕組みの反面、他の保険や貯蓄方法に比べて保険料が割高になるなどのデメリットもあります。
この記事では、養老保険の基本的な仕組みから、貯蓄と保障のバランス、満期保険金の活用方法を詳しく解説します。そして、保険料の高さを他の貯蓄方法と比較し、養老保険があなたのライフプランに合っているかどうかを判断するためのヒントを提供します。
養老保険の基本的な仕組み:満期保険金と死亡保障

養老保険とは、「保障期間」と「満期」が設定されている生命保険です。契約者がその保障期間中に亡くなった場合は「死亡保険金」が、満期まで生存していた場合は「満期保険金」が支払われます。
養老保険の主な特徴
・保障期間: 10年、20年、60歳までなど、一定期間が設定されています。
・満期保険金: 満期時に生存していれば、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取れます。
・死亡保障: 満期前に亡くなった場合は、死亡保険金が支払われます。
「貯蓄」と「保障」を両立
養老保険は、支払った保険料が将来の保険金として積み立てられる仕組みのため、保障を確保しながら資産形成も同時に行えます。解約した際には、それまでの保険料に応じて「解約返戻金」が支払われます。
貯蓄性と保障のバランス
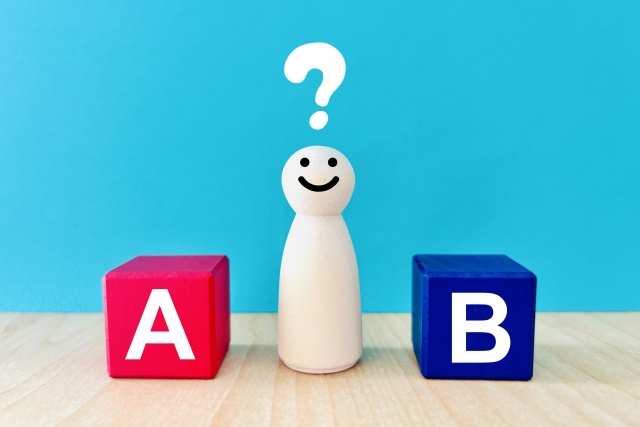
養老保険の大きな魅力は、貯蓄性と保障を両立させている点にあります。しかし、このバランスの取り方が、メリットとデメリットの両方を生み出します。
メリット:貯蓄をしながら安心も手に入れる
1.確実な満期保険金の受け取り:
満期時に生存していれば、満期保険金が必ず支払われます。これにより、将来の資金計画が立てやすくなります。
2.死亡保障も確保:
満期前に万が一のことがあった場合でも、死亡保険金が支払われるため、遺された家族の生活を守ることができます。
3.モチベーションの維持:
満期という明確なゴールがあるため、保険料の支払いが継続しやすくなります。
デメリット:保険料の高さと運用効率
1.保険料が割高:
養老保険は、死亡保険金と同額の満期保険金という「確実な給付」があるため、終身保険に比べて、保険料が最も高くなります。
2.運用効率が低い:
近年、低金利が続いているため、解約返戻金や満期保険金の返戻率が低くなりがちです。貯蓄目的だけであれば、他の金融商品の方が有利な場合があります。
3.途中解約は損をするリスク:
保険期間中に解約すると、解約返戻金が払込保険料の総額を下回り、元本割れする可能性が高くなります。
満期保険金の活用方法(教育資金、老後資金など)

養老保険の満期保険金は、まとまったお金として受け取れるため、様々なライフイベントの資金として活用できます。
1.子どもの教育資金:
子どもの大学入学時期に合わせて満期を設定すれば、入学費用や学費として活用できます。
2.老後資金の準備:
定年退職する時期に合わせて満期を設定し、老後資金として活用できます。
3.住宅購入の頭金:
住宅購入を計画している時期に合わせて満期を設定し、頭金として活用することも可能です。
保険料の高さと、他の貯蓄方法との比較

養老保険の保険料は、他の保険や貯蓄方法と比較して高めです。
養老保険:
・特徴: 貯蓄と保障を両立。保険料は高いが、満期保険金がある。
・比較: 同じ保障内容の終身保険よりも保険料が割高です。
定期保険+貯蓄:
・特徴: 安価な定期保険で保障を確保し、浮いた保険料を自分で貯蓄・運用します。
・比較: 養老保険よりも、貯蓄や運用の自由度が高く、運用の仕方によってはより多くの資産を形成できる可能性があります。ただし、自分で運用する手間がかかります。
終身保険:
特徴: 一生涯の保障と貯蓄を両立。保険料は養老保険よりも安くなりますが、保障期間が一生涯なので、長生きすれば保険料総額は養老保険よりも高くなる可能性があります。
賢い選択のポイント
・貯蓄の目的:
貯蓄をしながら保障も欲しいのであれば養老保険は有効です。しかし、貯蓄を最優先し、運用効率を重視するのであれば、他の金融商品(iDeCo、NISA、投資信託など)を検討する方が賢明かもしれません。
・保険料の負担:
養老保険の保険料は、家計の大きな負担になりがちです。無理のない範囲で継続できるかどうか、慎重に検討しましょう。
まとめ:養老保険は「目的」と「保険料」で賢く選ぶ
養老保険は、保障と貯蓄を両立させる魅力的な保険です。
・保障と貯蓄のバランスが取れている一方で、保険料が割高になるというデメリットを理解しましょう。
・満期保険金の活用目的を明確にし、その目的を達成するための最適な保険期間を設定しましょう。
・養老保険の保険料は、他の貯蓄方法や保険に比べて高いです。ご自身のライフプランや家計に合った保険を選びましょう。
この記事を参考に、養老保険を賢く活用し、あなたのライフプランに合わせた最適な備えをしていきましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



