ファイナンシャルプランナー
食料品値上げ時代を賢く生き抜く!家計防衛のための「お金の知識」完全ガイド

近年、私たちの生活に欠かせない食料品の値上げが続いています。スーパーの棚に並ぶお気に入りの商品も、気づけば値札が変わっていた…そんな経験はありませんか?ペットボトル飲料や即席麺、牛乳、アイスクリームなど、身近な食品が次々と値上がりし、家計を圧迫していると感じている方も少なくないでしょう。
かつては「冷凍食品半額デー」に代表されるデフレの時代があり、私も食品卸売りの営業として、その熱狂を肌で感じていました。当時は月に一度のお祭り騒ぎだった半額セールが頻繁に行われるようになり、消費者は安値に慣れきっていました。しかし、今はその時代とは大きく異なります。
食料品値上げの背景:なぜ私たちの生活は苦しくなっているのか?

現在の物価上昇は、単一の要因ではなく、複数の複雑な社会情勢が絡み合って引き起こされています。
・原材料価格の高騰: 国際的な穀物価格の上昇(例:ウクライナ侵攻による供給不安)、原油価格の高騰などが、食品メーカーのコストを押し上げています。これらは、小麦や砂糖、食用油といった基本的な原材料だけでなく、飼料価格にも影響し、肉や乳製品の値上げにもつながっています。
・円安の進行: 私たちが輸入に頼っている多くの食料品は、円安が進むことで円換算での価格が上昇します。例えば、海外から輸入するコーヒー豆やチョコレートの原料、加工食品などがその影響を大きく受けています。
・物流コストの増加: 燃料費の高騰に加え、トラックドライバー不足などの人手不足も深刻化しています。これにより、商品の輸送にかかる費用が増大し、それが最終的に商品の価格に転嫁されています。
・人件費の上昇: 少子高齢化が進む日本では、様々な業界で人手不足が深刻化しており、企業は従業員を確保するために賃上げせざるを得ない状況にあります。この人件費上昇分も、最終的な商品価格に反映される傾向にあります。
これらの要因が重なり合い、各メーカーは値上げに踏み切らざるを得ない状況になっているのです。
家計への具体的な影響:見えない負担と世代別の課題
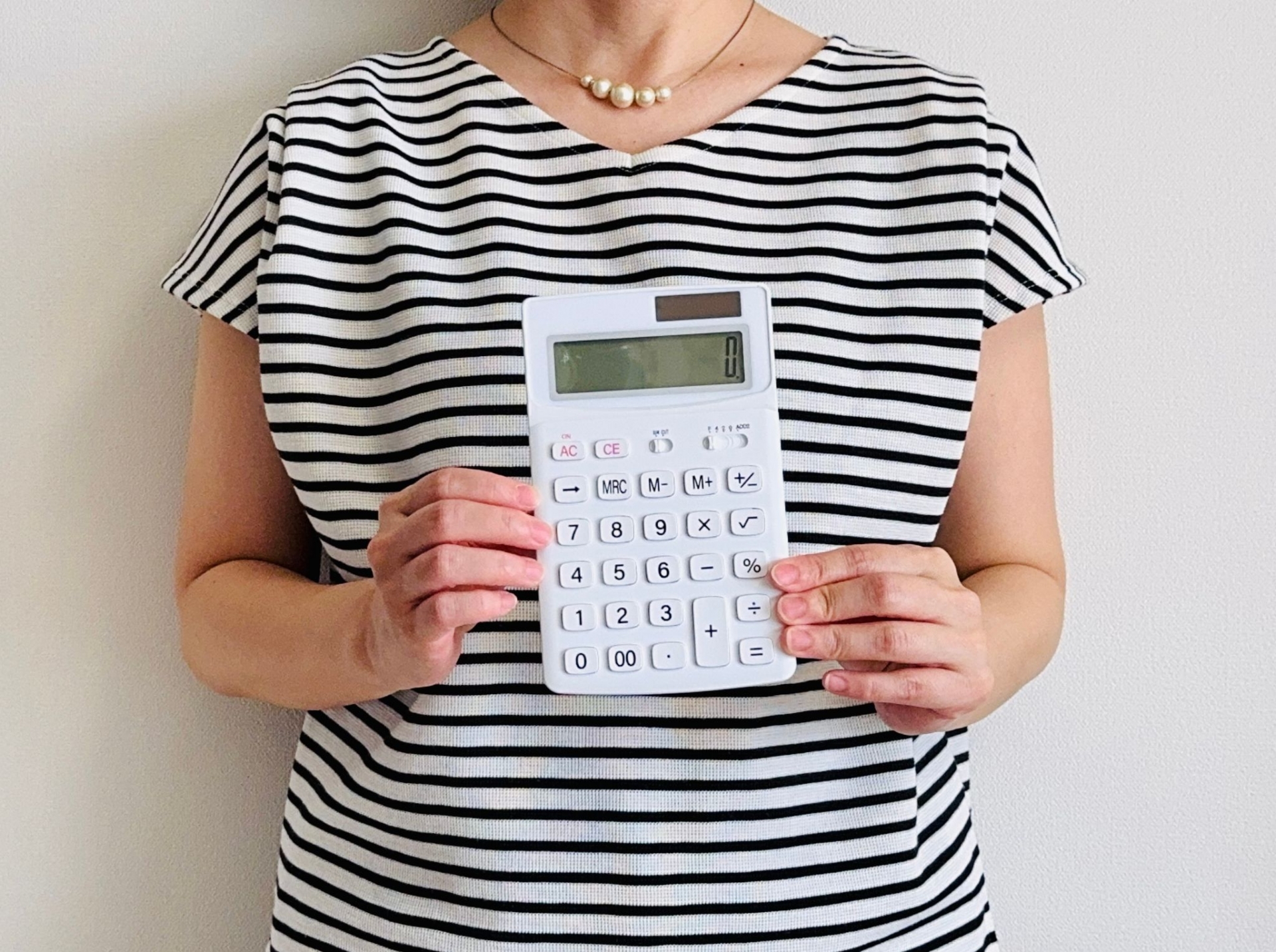
物価は上昇しているにもかかわらず、私たちの給料はどうでしょうか?「ボーナスの金額が上昇!」といった新聞記事を見ても、それは大企業のお話で、地方の中小企業では給料がほとんど上がっていないのが実情です。
もしあなたの給料が変わらないまま、身の回りの商品が10%値上げされたらどうなるか、具体的にシミュレーションしてみましょう。
例えば、毎月20万円の生活費(食費5万円、住居費8万円、光熱費1万円、交通費1万円、通信費1万円、その他4万円と仮定)で暮らしていたとします。
このうち、食費が10%値上げされると、食費は5.5万円になります。たった5千円の増加と思うかもしれませんが、他の生活必需品も軒並み値上げされれば、あっという間に月数万円の出費増につながります。
今まで20万円でやりくりできていたはずが、何も悪いことをしていないのに、突然21万円、22万円と生活費がかかるようになってしまうのです。
これは、実質的に私たちの暮らしが苦しくなっていることを意味します。収入があるうちはその影響に気づきにくいかもしれませんが、知らない間に家計は確実に圧迫され、貯蓄に回せるお金が減っていくのです。
・子育て世代: 食費だけでなく、子どもの教育費や習い事の費用も上昇傾向にあります。給料が上がらない中でこれらの費用が増えれば、家計はさらに厳しくなります。また、将来の不安から貯蓄に力を入れたくても、毎日の生活費で精一杯という状況に陥りやすいです。
・単身者・若年層: 実家暮らしであれば影響は少ないかもしれませんが、一人暮らしの場合、食費や光熱費の値上げはダイレクトに響きます。将来のための貯蓄や自己投資に回せるお金が減少し、キャリア形成やライフプランに影響が出る可能性もあります。
・年金受給世代: 年金だけでは生活費をまかなうのが難しい中で、物価上昇は一層の負担となります。特に食料品は毎日購入するものなので、高齢者にとっては深刻な問題です。
お金の知識が今こそ必要な理由:新しい時代を生き抜くために

物事には流行り廃りがあるように、世の中の流れがあります。今までは銀行預金や保険も大きな利息がついていましたが、今はもうそのような商品はほとんどありません。人類は長生きするようになり、国もこれまでのような年金支給をすることが難しくなっていることは周知の事実です。
「今までリスクがあるから全く資産運用なんて考えたこともなかった」という人も、おそらく世の中の流れでそうも言っていられなくなる時代になってきています。
60歳、ないし65歳で退職しても年金だけでは足りない、だから貯めておかないと考えるのは当然です。しかし、人間の寿命が長くなれば、用意しておかなければならない貯蓄額はどんどん増えていきます。一体いくら貯めておけばいいのでしょうか?
もはや貯蓄を取り崩すだけの老後ではなく、老後の年金も含めた収入が生活費を上回る状態、要するに退職後も貯蓄ができるライフスタイルを、長い期間かけて作り上げておく必要があります。そのためには、お金の知識がこれまで以上に不可欠です。
・インフレに打ち勝つ: 物価が上がり続ける中で、現金を銀行に預けておくだけでは、実質的な価値が目減りしてしまいます。お金にも働いてもらうことで、インフレに負けない資産形成を目指す必要があります。
・「貯蓄から投資へ」の流れ: 政府も「貯蓄から投資へ」の流れを後押ししており、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)といった税制優遇のある資産形成制度が充実しています。これらを活用しない手はありません。
・人生100年時代への備え: 長寿化が進む中で、退職後の期間が長くなります。この長い老後の生活資金を年金だけでまかなうのは非常に困難であり、自助努力による資産形成がより一層重要になっています。
合理的にお金を使う!具体的な解決策と選択肢
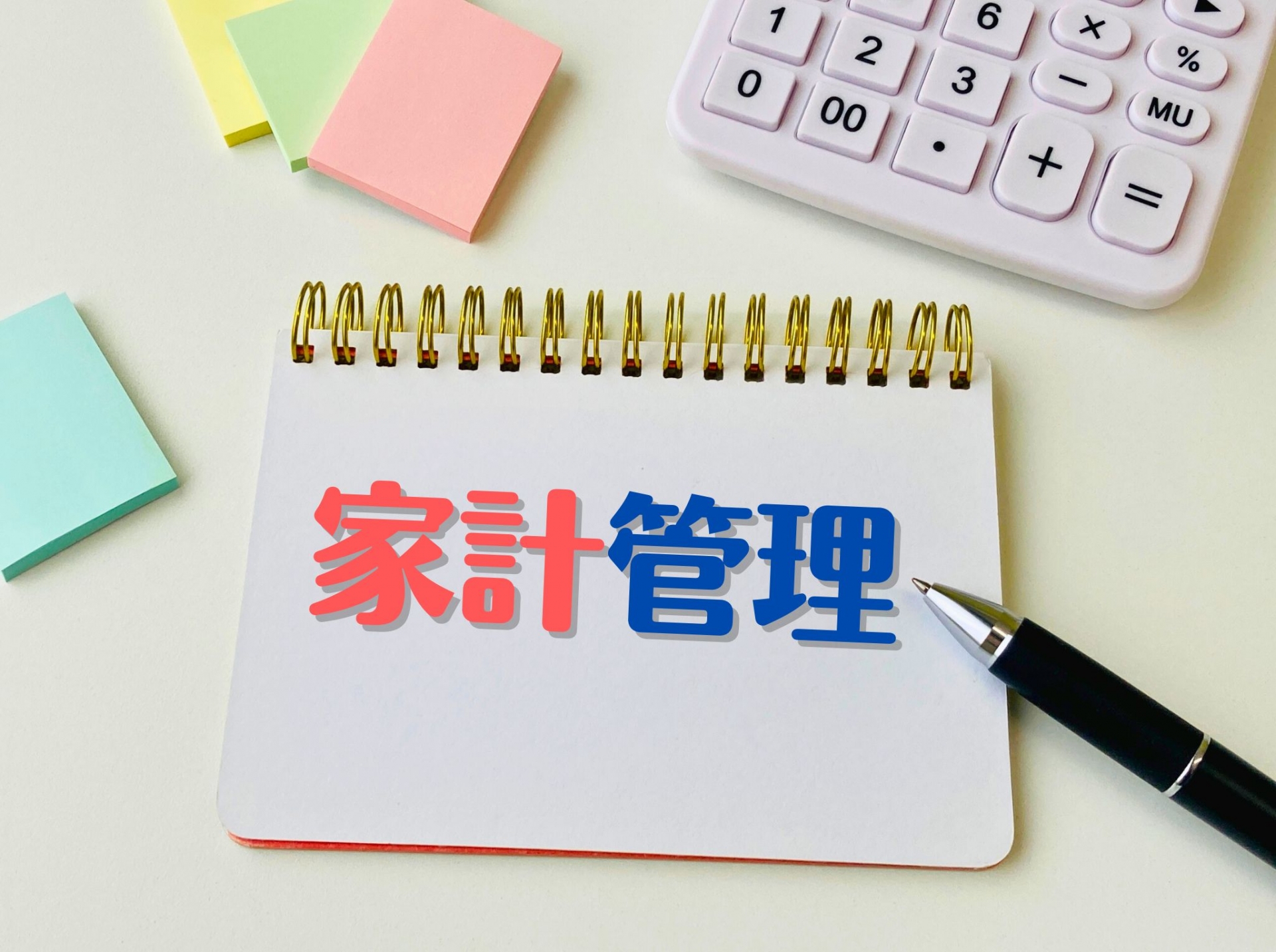
では、具体的にどのようにすればよいのでしょうか。解決策をいくつか提案します。
徹底した家計管理
まずは現状を把握し、無駄をなくすことが大切です。
固定費の見直し
・通信費: 携帯料金プランの見直し、格安SIMへの乗り換えを検討しましょう。不要なオプションサービスも解約します。
・保険料: 生命保険や医療保険など、本当に必要な保障内容かを見直します。過剰な保険は家計の負担です。
・サブスクリプションサービス: 動画配信サービスや音楽配信サービス、フィットネスジムなど、利用頻度の低いものは解約・休止を検討します。
・住居費: 可能であれば、より家賃の安い物件への引っ越しや、住宅ローンの借り換えなども検討の余地があります。
変動費の節約術
・特売品・見切り品の活用: スーパーの特売日を狙い、賞味期限の近い見切り品も賢く利用しましょう。
・まとめ買いと冷凍保存: 安いときにまとめ買いし、冷凍庫を活用して保存することで、無駄を減らせます。
・自炊のすすめ: 外食や惣菜の頻度を減らし、できるだけ自炊を心がけましょう。作り置きも効果的です。
・食材の使い切り: 無駄なく食材を使い切る工夫をしましょう。
・光熱費(利用量に応じて変動するため本記事では変動費に分類): 省エネ家電の導入、こまめな消灯、エアコンの設定温度の見直し、シャワー時間の短縮など、日々の意識が大切です。
・交通費: 公共交通機関の利用、自転車での移動、カーシェアリングなども検討してみましょう。
資産運用の活用
「投資は怖い」と感じるかもしれませんが、リスクを理解し、少額から始めることができます。
株式投資
企業の株を購入し、企業の成長による株価の上昇や、配当金を得ることを目指します。
・メリット: 大きなリターンが期待できる可能性がある。配当金や株主優待も魅力的。
・デメリット: 株価変動リスクが高い。企業業績や市場全体の影響を受けやすい。
投資信託
多くの投資家から集めた資金を、ファンドマネージャーが株式や債券などに投資・運用する金融商品です。
・メリット: 少額から分散投資が可能。専門家が運用してくれる。
・デメリット: 元本保証はない。運用コスト(信託報酬など)がかかる。
不動産投資
マンションやアパートなどの不動産を購入し、家賃収入を得る、または売却益を狙う投資です。
・メリット: 比較的安定した家賃収入が期待できる。インフレに強い。
・デメリット: 初期費用が高額になる傾向がある。空室リスクや修繕費用リスクがある。流動性が低い。
NISA・iDeCo
国が用意した税制優遇制度を活用した資産形成の仕組みです。
・NISA: 投資で得た利益が非課税になる制度。少額から始められ、投資初心者にもおすすめです。
・iDeCo: 掛金が全額所得控除になり、運用益も非課税になる私的年金制度。老後資金の形成に特化しています。
これらの資産運用は、ご自身のライフプランやリスク許容度に合わせて、最適な方法を見つけることが重要です。
専門家の力を借りる
どうしてもやり方がわからなければ、一人で悩まず、以下のような専門家や公的機関の力を借りることも重要です。
・ファイナンシャルプランナー(FP): 個人の家計状況やライフプランに合わせて、貯蓄、投資、保険、税金、住宅ローン、年金など、お金全般について具体的なアドバイスをしてくれます。
・金融機関の窓口: 銀行や証券会社の窓口でも、投資信託やNISA、iDeCoなどの相談が可能です。
・自治体・消費生活センター: 家計に関する一般的な相談や、多重債務などの問題についても相談できます。
家計防衛は「知る」ことから始まる

前職で食品卸売りの営業として働いていた頃、スーパーの「冷凍食品半額!」の裏側で、いかにメーカーが利益を削って販売しているかを知っていました。当時はそれが消費者に喜ばれる良い循環だと考えていましたが、デフレからインフレへの転換期を経験し、物価と賃金のスパイラルを肌で感じています。
私自身、ファイナンシャルプランナーとして活動する中で、多くの方の家計の悩みに向き合ってきました。皆さん口を揃えて言うのは、「もっと早くお金の知識を身につけておけばよかった」ということです。
例えば、私がサポートしたAさんのケースをご紹介しましょう。Aさんは30代のご夫婦で、お子様が2人。共働きでしたが、毎月の貯蓄がなかなか増えないという悩みを抱えていました。詳しくヒアリングすると、通信費や保険料の見直しで月1万5千円の固定費を削減できることが判明。さらに、週に3回あった外食を週1回に減らし、残りは自炊を心がけることで、食費も月1万円削減できました。
浮いたお金の一部をNISAで積立投資に回した結果、半年後には確実に貯蓄額が増え、ご夫婦で将来の教育費や老後資金について具体的な目標を立てられるようになりました。Aさんは「知っているだけでこんなに変わるなんて!」と驚いていました。
未来の安心のために、今から行動しよう
食料品の値上げは、私たちの生活に直接的な影響を与えています。しかし、悲観的になる必要はありません。正しいお金の知識を身につけ、今から具体的な対策を講じることで、家計の不安を軽減し、より豊かな未来を築くことができます。
重要なのは、無駄をなくす「守り」と、資産を増やす「攻め」の両方をバランスよく実践することです。そして、何よりも「知る」こと。知らなければ、正しい判断はできません。
この厳しい時代を賢く生き抜くために、あなたも今日から「お金の知識」を増やしてみませんか?
ご自身の家計状況や将来の目標について、さらに詳しく相談してみたい場合は、お気軽にご連絡ください。
お金に関する相談はファイナンシャルプランナーの金子賢司まで。日本FP協会の「CFP®認定者検索システム」、またはJ-FLEC(金融経済教育推進機構)のサイトの、J-FLEC認定アドバイザー検索で検索することも可能です。北海道エリアに絞って検索していただくと容易に検索できます。



