iDeCo
NISAの年間投資枠を活用しきれないならiDeCo?両者の年間投資可能額比較

「NISAの枠を使い切れない場合、iDeCoも始めた方がいいの?」
新NISAの非課税投資枠は大幅に拡充されましたが、誰もがその年間上限額を使い切れるわけではありません。もしNISAの年間投資枠を活用しきれていないなら、もう一つの強力な税制優遇制度であるiDeCo(個人型確定拠出年金)を検討すべきかもしれません。
この記事では、NISAの年間投資枠360万円とiDeCoの年間掛金上限の違いを明確にします。そして、どちらの枠を優先的に埋めるべきか、あなたの余裕資金の有無に応じた効果的な使い分けの判断基準を解説。それぞれの制度の強みを理解し、限られた資金で最大限の税制メリットを享受するための賢い資産形成戦略を提案します。
NISAとiDeCo、年間投資可能額の基本を比較

NISAとiDeCoは、どちらも非課税で運用できる制度ですが、年間で投資できる金額の上限や、その目的が異なります。
NISAの年間投資可能額
年間投資上限額: 合計360万円
・つみたて投資枠: 年間120万円
・成長投資枠: 年間240万円
特徴: 投資した運用益が非課税。原則いつでも引き出し可能で、生涯非課税保有限度額は1,800万円。老後資金だけでなく、教育資金や住宅資金など幅広い目的に使える柔軟性があります。
iDeCoの年間掛金上限額
年間掛金上限額: 職業や企業年金の有無によって異なります。
・自営業者など(第1号被保険者): 月額6.8万円(年間81.6万円)
・会社員(企業年金なし・第3号被保険者): 月額2.3万円(年間27.6万円)
・会社員(企業型DCあり): 月額2万円(年間24万円) ※企業型DC掛金と合計で月額5.5万円が上限
・会社員(DBなど確定給付型企業年金あり・公務員): 月額2万円(年間24万円) ※2024年12月から1.2万円から引き上げ済み
特徴: 掛金が全額所得控除になることが最大のメリット。運用益も非課税。ただし、原則60歳まで引き出しできない資金拘束があります。
NISAの年間360万円という枠はiDeCoよりもかなり大きいですが、iDeCoには掛金控除というNISAにはない節税メリットがある点が重要です。
NISA年間投資枠を「活用しきれない」場合の判断基準
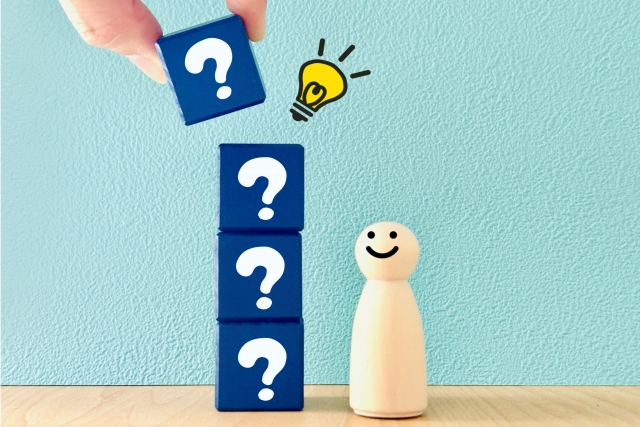
NISAの年間360万円という大きな枠を無理に使い切る必要はありません。大切なのは、あなたのライフステージや家計状況に合わせ、より税制メリットを享受できる制度を優先することです。
課税所得があり、所得税・住民税を減らしたいなら「iDeCo優先」
・こんな人: 会社員、公務員、自営業者など、現役で所得税や住民税を支払っている方。特に年収が高く、所得税率が高い方。
・判断基準: NISAの年間投資枠を使い切れていない場合でも、まずはiDeCoの掛金上限まで拠出することを優先的に検討しましょう。iDeCoの掛金全額所得控除は、NISAにはない「確実」かつ「確定的」な節税メリットだからです。
・理由: iDeCoの掛金は、運用成果に関わらず、毎年あなたの所得税・住民税を確実に軽減します。これは、現役時代の手取りを直接増やす効果があるため、資金の捻出に役立ちます。
資金の柔軟性を最優先するなら「NISA優先」
・こんな人: 老後資金だけでなく、教育資金や住宅購入資金など、近い将来使うかもしれない資金も非課税で貯めたい方。あるいは、原則60歳まで引き出せない資金拘束に抵抗がある方。
・判断基準: iDeCoの掛金控除メリットがあったとしても、60歳まで引き出せない資金拘束が大きな懸念であれば、まずはNISAの非課税枠を優先的に埋めましょう。
・理由: NISAは非課税で運用しながらも、必要な時にいつでも売却して資金を引き出せる柔軟性があります。売却した枠は翌年復活するため、ライフイベントにも対応できます。
将来的な制度改正を考慮する(2025年税制改正大綱の予定)
今後の制度改正の方向性も、判断材料の一つとなります。
・iDeCoの掛金上限額の引き上げ(予定): 2025年度の税制改正大綱では、会社員(企業年金なし)のiDeCo掛金上限が月額2.3万円から6.2万円へ大幅引き上げが予定されています。 これが実現すれば、多くの会社員にとってiDeCoの節税メリットがより大きくなり、NISAの年間枠を活用しきれない場合にiDeCoへ回すことの合理性が高まります。
・iDeCoの加入可能年齢の拡大(予定): 現在の65歳未満から70歳未満への引き上げが予定されています。 これにより、より長くiDeCoの節税メリットと非課税運用を享受できる可能性が高まります。
余裕資金の有無に応じた効果的な使い分け
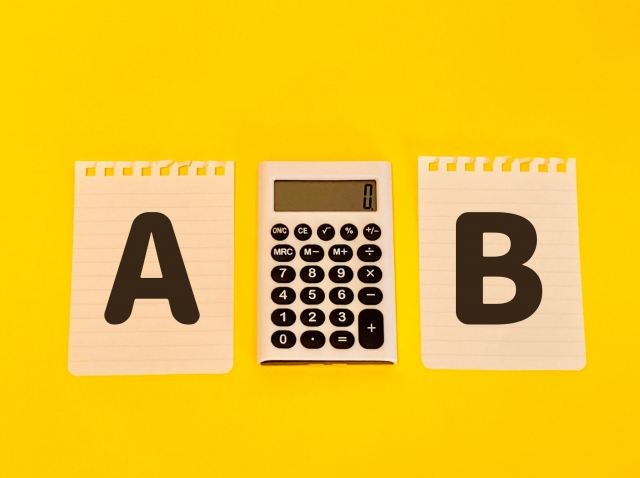
あなたの毎月の「余裕資金」(収入から生活費や当面の貯蓄を除いた、投資に回せるお金)の額によって、NISAとiDeCoの効果的な使い分け方は変わります。
余裕資金が少ない場合(月1万円〜3万円程度)
・戦略: まずはiDeCoの掛金上限まで拠出することを最優先に検討しましょう。
・理由: iDeCoは掛金全額所得控除という確実な節税メリットがあり、たとえ少額でも現役時代の税負担を軽減できます。また、60歳まで引き出せないため、半強制的に老後資金を積み立てることができます。
例: 月2万円をiDeCoに拠出(年間24万円)。これにより、所得税・住民税の軽減効果を得つつ、老後資金のコアを形成します。NISAは余裕があれば、月数百円〜数千円からでも積立を始めましょう。
余裕資金が中程度ある場合(月3万円〜10万円程度)
・戦略: iDeCoの掛金上限まで拠出し、残りの余裕資金をNISAのつみたて投資枠に回すのが最もバランスが良く効率的です。
・理由: iDeCoで確実な節税メリットを確保しつつ、NISAのつみたて投資枠(年間120万円まで)で運用益非課税のメリットを享受し、柔軟性の高い資産形成を進めます。
例: iDeCoに月2.3万円(年間27.6万円)を拠出し、NISAのつみたて投資枠に月5万円(年間60万円)を積立。合計で年間87.6万円を非課税で運用できます。
余裕資金が豊富にある場合(月10万円以上)
・戦略: iDeCoの掛金上限まで拠出した上で、NISAの年間投資上限額360万円をフル活用することを目指しましょう。
・理由: iDeCoの確実な節税メリットを享受しつつ、NISAの広大な非課税枠を最大限に活用することで、非課税での資産形成を最も加速できます。NISAの成長投資枠で個別株や高配当株などを組み入れることで、より高いリターンも狙えます。
例: iDeCoに月2.3万円(年間27.6万円)を拠出し、NISAに年間360万円(月30万円)投資。これにより、年間合計で約387.6万円もの資金を非課税メリットを享受しながら運用できます。
まとめ:NISAの枠を活用しきれないならiDeCoも視野に!
NISAの年間投資枠を使い切れない場合でも、決して損ではありません。大切なのは、あなたのライフスタイルや余裕資金の状況に合わせて、NISAとiDeCoそれぞれの制度の強みを理解し、賢く使い分けることです。
・所得控除による節税を重視するなら「iDeCo」を優先。
・資金の柔軟性や多目的利用を重視するなら「NISA」を優先。
そして、余裕資金があるなら、両方を併用することが、現役時代の節税メリットと、将来の非課税での資産成長という二重のメリットを最大限に享受する「最強の老後資金戦略」となります。あなたの資産形成を最適化するために、iDeCoの活用もぜひ検討してみてください。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています



