生命保険
DINKS夫婦の生命保険:最適な保障と節約術

「お互い収入があるから死亡保険は不要?でも、万が一の時に困らないか不安…」
DINKS(Double Income No Kids)夫婦は、二人とも収入があるため、万が一どちらかが亡くなっても、残された一人の収入で生活できると考えるかもしれません。しかし、一人の収入になった場合でも、現在の生活水準を維持できるとは限りませんし、住宅ローンなど、夫婦で背負っている大きな負担が残るリスクもあります。
この記事では、DINKS夫婦に最適な生命保険の選び方を解説します。互いの生活費を補い合う保障の考え方から、住宅ローンと団信以外の保障、そして個人年金保険やNISA、iDeCoでの資産形成を優先する考え方まで。共働き子なし夫婦ならではの賢い生命保険の活用術と節約術を提案します。
互いの生活費を補い合う保障の考え方

DINKS夫婦の場合、片方が亡くなったとしても、残されたもう一人の収入で生活を続けていくことになります。しかし、収入が減るだけでなく、家事や育児を一人で担うことになれば、生活への負担は大きくなります。
必要な保障額の考え方
・現在の生活費の確保:万が一のことがあった場合、遺された方が生活に困らないように、一定期間の生活費を確保することが重要です。
例: 月20万円の生活費を5年間補うなら、20万円 × 12ヶ月 × 5年 = 1,200万円が必要になります。
・家事・育児の費用:片方が亡くなった場合、これまで分担していた家事や育児を一人でこなすか、外注する必要があります。そのための費用も考慮しましょう。
・葬儀費用など:万が一の際の葬儀費用や、墓地代など、一時的に必要となる費用も考慮しましょう。
必要な保障は「定期保険」で十分なケースが多い
・保障期間:DINKS夫婦の場合、子育て世代のように子どもの独立までといった長期の保障は不要なケースが多いため、特定の期間だけ保障を確保する「定期保険」がおすすめです。
・保険料:定期保険は、終身保険に比べて保険料が安価です。少ない保険料で、必要な保障を確保できるため、家計への負担も少なく済みます。
住宅ローンと団信以外の保障

DINKS夫婦の生命保険を考える上で、住宅ローンと団体信用生命保険(団信)との関係は非常に重要です。
団信の仕組みと保障範囲
・団信の役割:団信は、住宅ローンの契約者が亡くなった場合に、保険金で住宅ローンの残高が完済される保険です。
・団信の保障範囲:団信が保障するのは、あくまで住宅ローンの残高です。遺された方の生活費や、万が一の際の医療費などはカバーしません。
団信でカバーできないリスクと補う方法
・リスク1:遺された方の生活費:団信が住宅ローンを完済してくれても、遺された方の生活費はカバーされません。収入保障保険や定期保険などの生命保険に加入することで、万が一の際に、遺された方が生活に困らないための資金を確保できます。
・リスク2:病気やケガの治療費:団信は病気やケガの治療費はカバーしません。医療保険やがん保険に加入することで、高額な医療費に備えることができます。
・リスク3:働けない期間の収入減:病気やケガで長期間働けなくなった際の収入減は、団信の保障範囲外です。就業不能保険に加入することで、収入減に備えることができます。
個人年金保険やNISA、iDeCoでの資産形成を優先する考え方
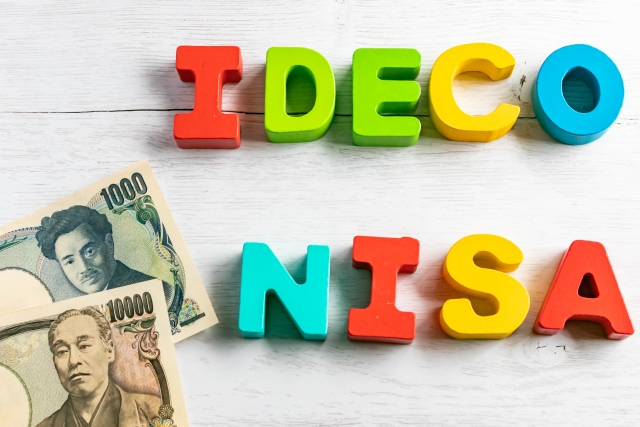
DINKS夫婦は、子育て世代に比べて支出が少ない傾向にあるため、保険に加えて、資産形成を積極的に行うことで、将来の選択肢を広げられます。
貯蓄型保険よりも「資産形成」を優先
貯蓄型保険のデメリット:
終身保険や養老保険などの貯蓄型保険は、貯蓄性がある一方で、保険料が割高です。また、運用効率がiDeCoやNISAなどの資産形成制度に比べて低い場合があります。
「掛け捨て」と「資産形成」の組み合わせ:
・保険: 必要な保障を安価な掛け捨ての定期保険で確保します。
・資産形成: 浮いた保険料を、iDeCoやNISAなどの非課税制度で資産形成に回します。これにより、保障と資産形成を両立させ、より多くの資産を築けます。
個人年金保険、iDeCo、NISAでの老後資金準備
個人年金保険:
・毎月保険料を積み立てて、将来の決まった時期から年金として受け取れる保険です。
・個人年金保険料控除を受けるには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
1.年金の受取人が契約者またはその配偶者であること
2.年金受取人が被保険者と同一であること
3.保険料払込期間が10年以上であること
4.年金の受取開始が60歳以降であること
5.年金受取期間が10年以上であること(確定年金の場合)
iDeCo:
・掛金が全額所得控除になり、運用益が非課税、受け取り時も税制優遇が受けられる制度です。
・夫婦それぞれがiDeCoに加入することで、世帯全体の所得控除を最大化できます。
NISA:
・運用益が非課税になり、非課税保有限度額が1,800万円と大きい制度です。
・iDeCoの掛金上限を超えてさらに老後資金を積み増したい場合に活用できます。
まとめ:DINKS夫婦は「守り」と「攻め」をバランスよく
DINKS夫婦の生命保険は、万が一の備えと資産形成をバランスよく両立させることが重要です。
・団信だけでは安心できないことを理解し、遺された方の生活費や、働けない期間の収入減をカバーする収入保障保険や医療保険に加入しましょう。
・必要な保障を掛け捨ての定期保険で安価に確保し、浮いたお金をiDeCoやNISAといった資産形成に回しましょう。
・個人年金保険料控除の要件を確認し、iDeCoやNISAと合わせて老後資金を計画的に準備しましょう。
この記事を参考に、あなたのライフスタイルに合わせた最適な保険を選び、安心して日々の生活を送りましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



