医療保険
通院給付金特約の選び方:退院後の治療費をどう備える?

医療技術の進歩により、入院日数は年々短くなる傾向にあります。一方で、通院での治療やリハビリテーションが長期にわたることが増えてきました。そんな時、退院後の治療費をどう備えれば良いか、悩む方もいるかもしれません。
この記事では、生命保険や医療保険に付加できる「通院給付金特約」の選び方を解説します。通院給付金が支払われる条件を詳しく掘り下げ、退院後の通院費用やリハビリテーション費用にどう備えるべきかを具体的に提案。そして、通院給付金が必要な人と、不要な人の違いまで、後悔しないための賢い保険選びのヒントをご紹介します。
通院給付金が支払われる条件

通院給付金特約とは、病気やケガで入院した後に、通院して治療を受けた場合に給付金が支払われる特約です。保障内容は保険会社や商品によって異なるため、約款の確認が必要です。
給付金が支払われる条件
入院後の通院:
通院給付金は、入院を伴う治療が前提となります。入院給付金の支払対象となる入院を伴う治療で、退院後も通院が必要な場合に給付金が支払われます。
支払い対象となる期間:
多くの保険商品では、退院日から一定期間内(例:180日以内)の通院が対象となります。また、1回の入院に対して30日を限度とする場合が多いです。
給付金の金額:
入院給付金日額の50%〜100%程度が支払われるのが一般的です。
支払い対象外となるケース
入院を伴わない通院:
・普段の風邪や、健康診断のための通院など、入院を伴わない通院は、基本的に給付金の支払い対象外となります。
・がん保険の抗がん剤治療給付金など、入院を伴わない治療を保障する特約も存在しますが、通院給付金とは異なる保障です。
退院後の通院費用や、リハビリテーション費用
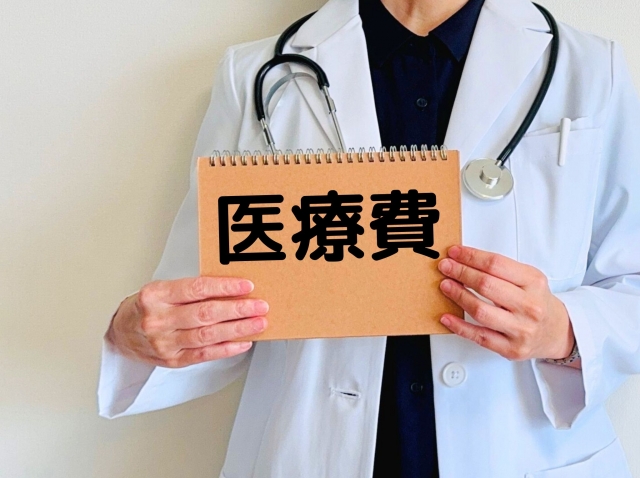
通院給付金特約は、退院後の生活をサポートする上で非常に重要な役割を果たします。
通院費用やリハビリテーション費用
費用の内訳:
通院には、治療費だけでなく、交通費や、薬代、入院中の雑費などがかかります。
リハビリテーション費用:
・脳卒中や骨折などでリハビリテーションが必要な場合、退院後も通院してリハビリを続ける必要があります。
・リハビリテーションは基本的に公的医療保険の適用対象ですが、期限(例:発症から180日以内)を超えた場合、費用が全額自己負担となるため、注意が必要です。
通院給付金の活用
生活費の確保:
退院後の通院やリハビリテーションで、仕事を休む必要がある場合、通院給付金は、その間の収入減を補うための生活費として活用できます。
交通費や雑費の補填:
通院にかかる交通費や、薬代など、細かな費用を補填できます。
通院給付金が必要な人と、不要な人の違い
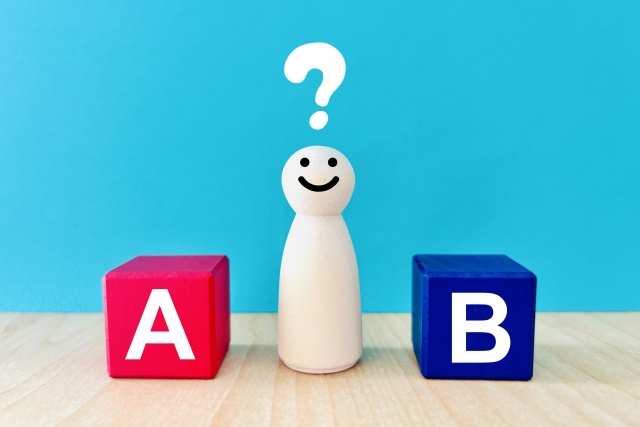
通院給付金特約は、万人に必要な特約ではありません。ご自身のライフスタイルや、貯蓄状況に合わせて、必要性を判断しましょう。
通院給付金特約が必要な人
貯蓄が十分でない人:
入院中の医療費や、退院後の通院費用を貯蓄で賄えない場合。
自営業者やフリーランス:
会社員のように傷病手当金がないため、入院や療養で収入が途絶えるリスクに備えたい人。
退院後の通院・リハビリが想定される人:
脳卒中や骨折など、退院後もリハビリテーションが必要な病気のリスクに備えたい人。
通院給付金特約が不要な人
貯蓄が十分にある人:
入院中の医療費や、退院後の通院費用を貯蓄で賄える場合。
入院給付金が手厚い人:
入院給付金日額が高く、短い入院でもまとまったお金が受け取れる場合。
保険料を抑えたい人:
保険料の負担を最小限にしたい人。
まとめ:通院給付金は「退院後の備え」
通院給付金特約は、入院が短期化している現代において、退院後の治療費や生活費に備える上で非常に有効な保障です。
・通院給付金は、入院後の通院が支払いの条件となります。
・退院後の通院費用や、リハビリテーション費用をカバーできるメリットがあります。
・あなたのライフスタイルや、貯蓄状況に合わせて、通院給付金特約が必要かどうかを判断しましょう。
この記事を参考に、あなたに最適な医療保険を選び、安心して日々の生活を送りましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



