FPによる貸金業法学習記録
貸金業における取立て行為の規制と遵守事項
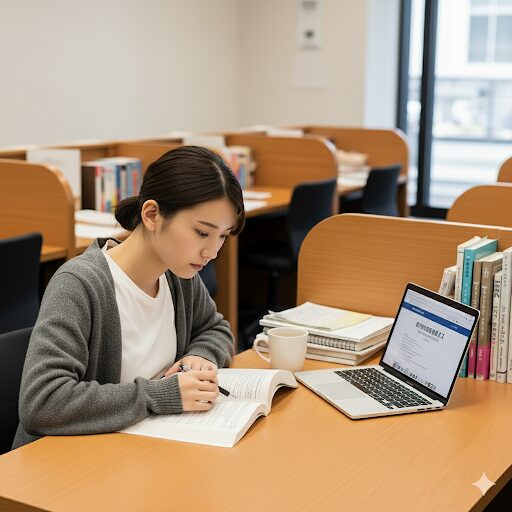
この記事は、CFPが2025年11月16日実施の貸金業務取扱主任者を目指すために、自身の勉強記録として残すブログです。
「※本記事は筆者の学習記録であり、その内容の正確性には万全を期しておりますが、法令改正等により変更される可能性があります。実際の業務や判断においては、必ず最新の法令や専門家の助言を確認してください。
貸金業を営む者、またはその委託を受けて取立てを行う者は、債務者等の私生活や業務の平穏を害するような不適切な取立て行為が厳しく規制されている。これは、債務者保護の観点から特に重要視される。
不適切な取立て行為の禁止される具体的な内容
貸金業者や取立ての委託を受けた者は、債務者等に対し、正当な権限の行使として認められる範囲を超え、以下のような行為を行ってはならないと定められている。
威圧的な言動・私生活等の平穏を害する行為の禁止
・人を威圧したり、その他の者に私生活もしくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。例えば、大声を出す、乱暴な言葉遣いをする、長時間の居座りなどの行為が該当する可能性がある。
時間帯に関する規制
・正当な理由なく、午後9時(21時)から午前8時までの間に、債務者に電話をかけたり、ファクシミリ(ファックス)を送ったり、または居宅を訪問したりすることは禁止されている。ただし、債務者本人の自発的な承諾があれば、この時間帯の連絡や訪問が認められる可能性がある。
債務者からの申し出がある場合の規制
・債務者が、連絡を受ける時期や時間帯などについて特定の申出をしている場合、午後9時から午前8時までの間以外であっても、その申出に反して電話やファックスを送ったり、居宅を訪問したりすることは禁止される場合がある。
居宅以外の場所への訪問・連絡の規制
・正当な理由がなく、債務者等の勤務先など居宅以外の場所に電話やファックスを送ったり、または訪問したりすることは禁止されている。これは、債務者の社会生活における平穏を保護するためだ。
退去意思表示後の居座りの禁止
・債務者等を訪問し、債務者等が「お帰りください」などとその場から退去する意思を示したにもかかわらず、正当な理由なく退去しないことは禁止されている。
私生活に関する事実の開示の禁止
・債務者等の私生活に関する事実(借り入れに関する事実を含む)を、債務者等以外の者に明らかにすることは禁止されている。
・ただし、債務者等の自宅に電話をかけた際に家族が受けた場合に貸金業者と名乗る場合や、郵送物の差出人に貸金業者であることを示したとしても、直ちに規制行為に該当することはない。
・しかし、債務者等から「家族に知られないように」といった要請があったにもかかわらず、家族等に借り入れの事実が推知されるような行為を行った場合は、上記の規制行為に該当する可能性があるため、特に注意が必要。
不適切な要求・第三者への接触の禁止
貸金業者等は、債務者等への取立てにおいて、以下のような行為も禁止されている。
他の借入による弁済要求の禁止
・債務者等に対し、他の貸金業者からの借入れ等による弁済を要求することは禁止されている。これは、多重債務を誘発する行為を防止するためだ。
債務者等以外の者への弁済要求の禁止
・債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済するよう求めることは禁止されている。保証人等、法律上の義務を負う者への請求はこれに当たらないが、それ以外の者へ返済を要求することは規制される。
第三者への取立て協力の要請の禁止
・債務者等以外の者が、債権の取立てに協力することを拒否している場合に、さらに債権の取立てに協力するよう要請することは禁止されている。例えば、親に対し債務者等の居場所や連絡先を執拗に聞き出すような行為が該当する。
・また、債務者等に対し他の借入による弁済を要求することも禁止されている。
弁護士等への委託後の取立ての停止
・債務者等が、貸付の契約に基づく債権に係る債務の処理を、弁護士や弁護士法人、または司法書士や司法書士法人に委託し、その旨を貸金業者が知った場合、債務者に対して取り立てを継続することはできない。この場合、貸金業者は委任を受けた弁護士等との交渉に移行する必要がある。
貸金業者は、これらの規制を遵守し、適正な取立て行為を行うことが義務付けられている。これらの規制に違反した場合には、行政処分の対象となるほか、罰則が科される可能性もある。



