FPによる貸金業法学習記録
貸金業における利息と保証料の規制:三つの法律の役割
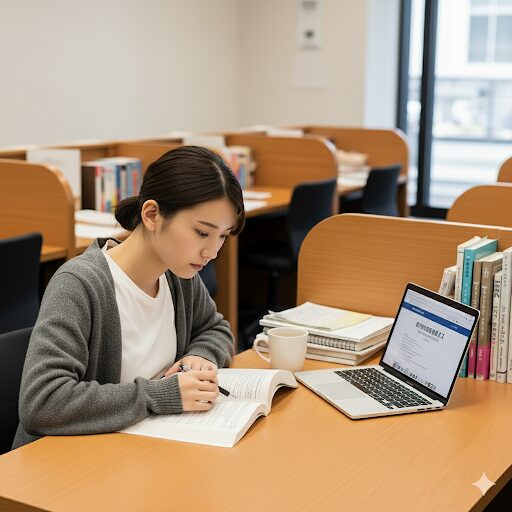
この記事は、CFPが2025年11月16日実施の貸金業務取扱主任者を目指すために、自身の勉強記録として残すブログです。
※本記事は筆者の学習記録であり、その内容の正確性には万全を期しておりますが、法令改正等により変更される可能性があります。実際の業務や判断においては、必ず最新の法令や専門家の助言を確認してください。
貸金業者が金銭を貸し付ける際に収受する利息や保証料は、借り手を過度な負担から守るため、複数の法律によって厳格に規制されている。主要な規制法は、利息制限法、出資法、そして貸金業法の三つである。これらの法律は、それぞれ異なる役割と効力を持っている。
1. 利息制限法:金利・遅延損害金・保証料の上限
利息制限法は、金銭消費貸借契約における利息の最高限度を定めた法律である。この法律が定める制限利率を超える利息の契約は、その超過部分がすべて無効となる私法上の効力を持つ。
制限利率(上限金利)と計算方法
利息の上限は、貸付元本の額に応じて定められている。
・元本が10万円未満の場合:年20%
・元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
・元本が100万円以上の場合:年15%
また、制限利率を適用する際の元本の額は、同一の貸金業者から複数の貸付けを受ける場合、それらを合計した金額を基準とする。
・同時に複数の貸付けを受ける場合、複数の貸付けを受けた元本の合計額を元本とみなし、その利息の上限を計算する。
・重ねて貸付けを受ける場合、すでに貸付を受けた残元本とその貸付けを受けた元本の額との合計額を元本の額として、利息の上限を計算する。
遅延損害金の制限
金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定(遅延損害金)にも上限が定められている。
・その賠償額の元本に対する割合が、利息制限法第1条に規定する利息の率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について無効となる。
・特に営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、賠償額の元本に対する割合が年20%を超えるときは、その超過部分について無効となる。
保証料の制限
保証料は「みなし利息」として扱われ、利息制限法の制限を受ける。
・保証料が利息と合算して利息制限法の利息上限額を超える場合は、その保証料の契約は超過部分について無効となる。
・利息が変動利率の場合、保証料が次のように定める金額を超えるときは、利息制限法により、その保証料契約は超過部分について無効となる。
・1. 貸主が主たる債務者から支払いを受けることができる利息の利率の上限(特約上限利率)の定めをし、かつ、貸主あるいは保証業者が主たる債務者にその定めを通知した場合。
・2. 1.以外の場合は、利息制限法の利息上限額の2分の1の金額。
「みなし利息」の範囲と例外
貸主の受ける元本以外の金銭は、名目のいかんにかかわらず、原則として利息とみなされる。これには、礼金、割引金、手数料、調査料、保証料などが含まれる。ただし、契約の締結および債務の弁済の費用のうち、一定のものは利息とみなされない。
・公租公課の支払いに充てられるべきもの、強制執行の費用、担保権の実行として競売の手続きの費用。
・現金自動支払機などの利用料(1万円以下の入出金額の場合は110円、1万円を超える入出金額の場合は220円)。
・カードの再発行手数料や、書面の再発行に要する費用など、債務者の要請で行った事務に要する費用。
超過利息の元本充当
利息制限法の制限利率を超える利息を貸金業者が天引きした場合や、債務者が任意に支払った場合、その超過した部分の金額は元本の返済に充当されたものとみなされる。この規定は、借り手による過払い金返還請求の基礎となる。
2. 出資法:制限利息と保証料の刑事罰
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)は、利息についての上限を定め、これを超える場合に刑罰を科す法律である。これは公法上の規制であり、違法な高金利貸付に対する刑事罰を定めている。貸金業者の上限金利は**年20%**である。
刑罰の基準
定められた利率を超える場合、その超過した割合に応じて刑罰が科される。年20%以下であれば、刑罰を科されることはない。
・貸付を業とする者が、年20%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科に処される。
・貸付を業とする者が、さらに年109.5%を超える割合による利息の契約をしたとき、その契約は無効となるとともに、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金、またはこれらの併科に処される。
保証業者に対する刑罰
出資法では、保証料が利息と合算して年20%を超える保証料の契約をした保証業者に刑罰を科す。
・こうした保証料の契約を締結した場合だけでなく、保証料を受領し、支払いを要求しただけの者も処罰の対象となる。違反した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または併科される。
媒介手数料の制限
金銭の貸借を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の5%を超える手数料の契約をしたり、受領することはできない。
・貸借期間が1年未満のものは、その貸借の金額に日数に応じ、年5%の割合を乗じて計算した金額が媒介手数料の上限になる。
3. 貸金業法:業務規制と行政処分・契約無効
貸金業法は、貸金業を営む者に対する業務規制を定め、上記2法の制限を確実に遵守させる役割を担っている。
貸金業者の利息に関する義務と処分
貸金業者は、利息制限法の利息上限額を超える利息の契約をすることはできない。そのような利息を受領したり、要求したりすることもできない。
・この規定に違反した場合は、行政処分(監督処分)の対象となる。行政庁は、業務改善命令、業務停止命令、最悪の場合には登録の取消処分を行うことができる。
契約全体の無効
貸金業者が利息制限法の制限利率を超える利息の契約を締結するなど、特定の重大な違反行為があった場合、その金銭消費貸借契約全体が無効となる。



