生命保険
自営業者の生命保険:会社員との違いと手厚い保障の作り方

「自営業者には、もしもの時に使える公的保障が少ないって本当?」
自営業者(個人事業主やフリーランスなど)は、会社員のように、勤務先が用意する手厚い福利厚生や、公的保障が薄いという現状があります。そのため、万が一の事態に備えるための生命保険も、会社員とは異なる視点での選び方が必要になります。
この記事では、自営業者の生命保険の考え方を解説します。公的保障(傷病手当金、失業保険など)の薄さを補う重要性、就業不能保険や所得補償保険がなぜ重要なのかを具体的に説明。さらに、経営リスクと個人保障の切り分けまで、自営業者ならではの賢い保険戦略を提案します。
公的保障の薄さを補う生命保険の必要性

会社員は、健康保険や厚生年金、雇用保険といった公的保障制度に加入しており、病気やケガで働けなくなった際や、失業した際に一定の給付金を受け取ることができます。しかし、自営業者の公的保障は、会社員に比べて薄いのが現状です。
自営業者が利用できない主な公的保障
傷病手当金:
・会社員が病気やケガで仕事を休んだ際に、健康保険から給与の3分の2程度が支給される制度です。
・自営業者は国民健康保険に加入するため、この傷病手当金制度は利用できません。
雇用保険:
・会社員が失業した際に、給付金を受け取れる制度です。
・自営業者は雇用保険に加入できないため、失業給付金制度は利用できません。
退職金:
・多くの会社員は勤務先の退職金制度がありますが、自営業者はこの制度がありません。iDeCoや小規模企業共済などを活用して自助努力で準備が必要です。
このように、自営業者は万が一の際に公的保障から得られる収入源が限られるため、生命保険でこれらの公的保障の薄さを補う必要があります。
死亡保険の必要性
・遺族年金の不足:自営業者は国民年金のみに加入しているため、会社員に比べて遺族年金の額が少なくなる傾向があります。
・死亡保険で補う:遺された家族の生活費や、子どもの教育費などをカバーするため、収入保障保険や定期保険といった死亡保険で、遺族年金だけでは不足する部分を補いましょう。
就業不能保険や所得補償保険の重要性

自営業者の場合、病気やケガで仕事ができなくなると、そのまま収入が途絶えてしまうリスクがあります。そこで重要になるのが、「就業不能保険」や「所得補償保険」です。
就業不能保険の活用
・仕組み:病気やケガで長期間にわたり仕事ができない状態(就業不能状態)が続いた場合、年金のように毎月給付金が支払われる保険です。
メリット:
・収入の穴埋め: 働けない期間の収入減を補うことができます。
・生活費の確保: 住宅ローンや生活費など、毎月かかる固定費の支払いを継続できます。
・注意点:多くの就業不能保険では、「就業不能状態」の定義が厳格に定められており、給付金が支払われるまでに一定の免責期間(30日、60日など)があるため、契約時に給付条件の確認が必要です。
所得補償保険の活用
・仕組み:就業不能保険と似ていますが、病気やケガで働けない状態が続いた場合に、給付金が支払われる保険です。
メリット:就業不能保険との使い分け: 就業不能保険は保障期間が長いものが多いですが、所得補償保険は短期的な備えに適しています。
注意点:所得補償保険は、就業不能保険に比べて、保険期間や給付金額に制限がある場合があります。
経営リスクと個人保障の切り分け
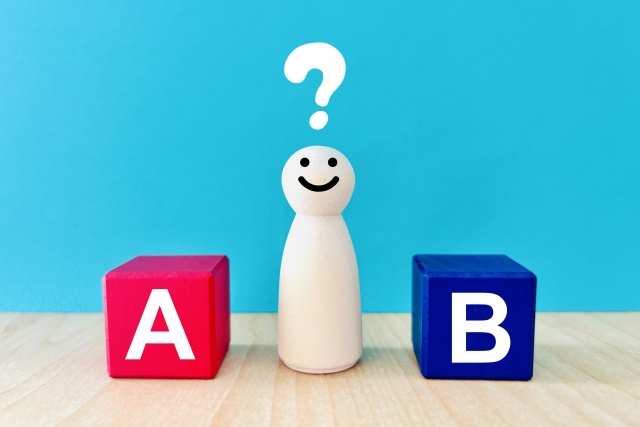
自営業者の生命保険を考える上で、事業の負債やリスクと、個人の保障を明確に切り分けることが重要です。
事業リスクと個人リスクの明確な切り分け
事業保障:
・自身が亡くなった場合、事業を継続するための資金(運転資金、借入金返済など)を準備する保障です。
・事業保障保険など、事業専用の保険で備えるのがおすすめです。
個人保障:
・遺された家族の生活費や子どもの教育費など、個人の生活のための保障です。
・収入保障保険や定期保険といった生命保険で備えましょう。
死亡保険金の受取人指定
・個人保障の場合:死亡保険金の受取人は、家族(配偶者や子ども)を指定しましょう。
・事業保障の場合:死亡保険金の受取人は、事業を引き継ぐ後継者や、事業の共同経営者などを指定することが考えられます。
このように、事業の負債やリスクと、個人の保障を明確に切り分けることで、万が一の際にも、遺された家族が事業の負債に巻き込まれるリスクを避けられます。
まとめ:自営業者は「万が一」の備えを自分で作る
自営業者にとって、生命保険は、公的保障の薄さを補い、将来の不安を解消するための重要なツールです。
・傷病手当金や失業給付金がないことを理解し、就業不能保険や所得補償保険で、働けない期間の収入減に備えましょう。
・収入保障保険や定期保険で、遺された家族の生活費や教育費を確保しましょう。
・経営リスクと個人の保障を明確に切り分け、それぞれに合った保険で備えましょう。
この記事を参考に、あなたの働き方に合った最適な生命保険を選び、安心して事業を継続し、豊かな未来を築いていきましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



