生命保険
生命保険の「がん保障特約」:保障内容と注意点

国立がん研究センターの2021年データによると、一生のうちにがんと診断される確率は、男性で63.3%、女性で50.8%と、日本人の2人に1人ががんになる時代です。生命保険の保障内容を検討する際、がんへの備えは欠かせません。多くの場合、主契約の生命保険に「がん保障特約」を付加するか、または「がん保険」を単体で契約するかのどちらかになります。
この記事では、生命保険に付加するがん保障特約の保障内容と種類を解説します。そして、主契約の生命保険との関係性や、がん保険を単体で契約すべきか、特約で付加すべきかを比較。最適ながんへの備え方を見つけるためのヒントを提案します。
がん保障特約の種類と保障内容

がん保障特約は、がんの診断や治療に備えるための特約で、様々な種類があります。
がん診断給付金
保障内容:
がんと診断された場合に、まとまった一時金が支払われます。
給付金の使い道:
治療費だけでなく、仕事を休んだ間の生活費や、家族のサポート費用など、自由に使うことができます。
支払回数:
「1回限り」のタイプと、2回目以降も支払われる「複数回」のタイプがあります。また、上皮内がんは、対象外となるタイプもあります。
がん治療給付金
保障内容:
がんの治療を目的とした入院・手術・放射線治療・抗がん剤治療などを受けた場合に、給付金が支払われます。
メリット:
治療が長期にわたる場合でも、その都度給付金が受け取れるため、家計の負担を軽減できます。
がん先進医療特約
保障内容:
がん治療のために、公的医療保険の対象外となる先進医療を受けた場合の技術料をカバーします。
費用の相場:
がんの陽子線治療や重粒子線治療など、約300万円前後と高額な技術料がかかる場合があるため、この特約の必要性は高いと言えます。
【補足】: 一部のがん(前立腺がん、頭頸部がんなど)に対するこれらの治療は、公的医療保険の適用が始まっているため、通常の保険診療として3割負担で治療を受けられる場合があります。対象範囲・施設が広がっている可能性もありますので、事前に確認しておきましょう。
詳しくは、メディポリス国際陽子線治療センターさまのサイトを参考にしてください。
主契約の生命保険との関係性

がん保障特約は、主契約の生命保険と密接な関係にあります。
主契約の保険料払い込み免除
特約の条件:
・がんと診断された場合、主契約の生命保険とがん保障特約の両方の保険料が払い込み免除になる商品もあります。
・実際に多くの保険会社で「がん保険料払込免除特約」が提供されています。
メリット:
がん治療による収入減や、出費が増える時期に、保険料の支払いがなくなるため、家計の負担を大きく軽減できます。
特約の保障期間
主契約に連動:
・がん保障特約は、主契約の生命保険と同じ期間で保障が終了することが多いです。
・しかし、商品によっては、特約を主契約とは別に更新できるものもあります。
がん保険を単体で契約すべきか、特約で付加すべきか
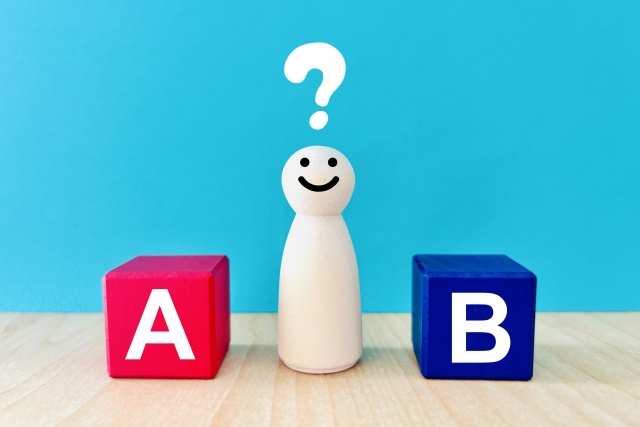
がんへの備え方には、主に「特約で付加」と「単体で契約」の2つの方法があります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、ご自身の状況に合わせて選択しましょう。
特約で付加する場合
メリット:
・手続きが簡単: 主契約の生命保険とまとめて契約できるため、手続きの手間が省けます。
・保険料が割安: がん保険を単体で契約するよりも、保険料が割安になる場合があります。
デメリット:
・保障内容が限定的: 単体のがん保険に比べて、保障内容がシンプルで、細かいニーズに対応できない場合があります。
・主契約に連動: 主契約の生命保険を解約すると、がん保障特約も同時に消滅します。
単体で契約する場合
メリット:
・保障内容が充実: がん治療の多様化に対応した、きめ細やかな保障内容を選べます。
・自由度が高い: 主契約の生命保険とは独立しているため、がん保険だけを解約したり、見直したりできます。
デメリット:
手続きの手間: 生命保険とは別に、新たながん保険の契約手続きが必要です。
まとめ:最適な「がんへの備え」を考える
がん保障特約と単体のがん保険は、それぞれにメリットとデメリットがあります。
がん保障特約:
手軽に、割安な保険料で、最低限のがんへの備えをしたい方におすすめです。
単体のがん保険:
がん治療の多様化に対応した、より充実したがんへの備えをしたい方におすすめです。
この記事を参考に、ご自身のライフプランやがんへの備え方について検討し、最適な選択をしましょう。ただし、保険商品は各社で内容が異なるため、実際の契約検討時には個別の商品内容を必ず確認することが重要です。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



