FPによる貸金業法学習記録
指定信用情報機関の概要と貸金業法上の役割
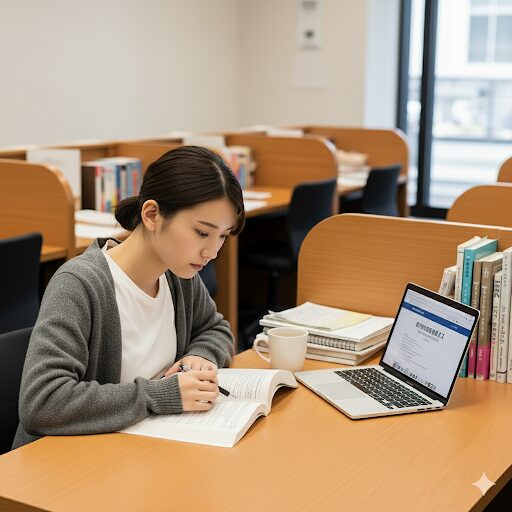
この記事は、CFPが2025年11月16日実施の貸金業務取扱主任者を目指すために、自身の勉強記録として残すブログです。
「※本記事は筆者の学習記録であり、その内容の正確性には万全を期しておりますが、法令改正等により変更される可能性があります。実際の業務や判断においては、必ず最新の法令や専門家の助言を確認してください。
本記事では、貸金業法における指定信用情報機関の制度と、その役割について解説する。指定信用情報機関は、貸金業者が個人顧客の返済能力調査を行う上で、極めて重要な位置づけにある機関だ。
指定信用情報機関の定義と業務
指定信用情報機関とは
指定信用情報機関とは、貸金業法に基づき内閣総理大臣の指定を受け、主に信用情報提供等業務(信用情報の収集、保管、提供)やこれに付随する業務を行う機関のことである。
この機関を利用することで、貸金業者は、資金需要者である債務者の借入残高の総額など、返済能力に関する正確な情報を知ることができる。これは、過剰な貸付けを防止し、顧客の利益を保護するために不可欠な仕組を指す。
業務の委託
指定信用情報機関が、信用情報提供等業務の一部を他の者に委託することは、原則として認められている。ただし、この業務の一部を委託する際には、あらかじめ内閣総理大臣の承認を得る必要がある。
加入貸金業者の義務と信用情報の取扱い
信用情報提供契約と個人信用情報の提供義務
指定信用情報機関の加入貸金業者は、当該機関と信用情報提供契約を締結したときは、その契約を締結した個人顧客の個人信用情報を、指定信用情報機関に提供しなければならない。
この個人信用情報には、主に以下の事項が含まれる。
・顧客の氏名、住所、生年月日、電話番号、運転免許証番号など個人を識別できる事項
・契約年月日、貸付金額、貸付残高、元本または利息の支払いの遅延の有無など契約内容や支払い状況に関する事項
提供情報に変更が生じた場合の対応
加入貸金業者は、指定信用情報機関に提供した個人信用情報の内容に変更があったときは、遅滞なく、その変更内容を指定信用情報機関に提供しなければならない。
信用情報の提供依頼に係る同意
加入貸金業者が指定信用情報機関に信用情報の提供を依頼する場合、原則として、あらかじめ資金需要者等(個人顧客)から同意を、書面または電磁的方法で得なければならない。
ただし、例外として、信用情報提供契約の締結をする前に締結した貸付けに係る契約(例えば、極度方式貸付けに係る契約を締結する前に結ばれた貸付けの契約)については、同意を得る必要はない。
同意に関する記録の保存
上記で同意を得た場合、加入貸金業者は、その同意に関する記録を作成し、指定信用情報機関が当該信用情報を保有している間、その記録を保存しなければならない。
名称の公表義務
加入貸金業者は、自らが加入している指定信用情報機関の商号または名称を、公衆の見やすい場所に掲示するなどの方法により公表しなければならない。
信用情報の利用目的の限定と相互交流
利用目的の限定
加入貸金業者やその役員・職員は、以下の目的外で信用情報を利用してはならない。
・加入指定信用情報機関に対して、返済能力の調査以外の目的のために、信用情報の提供の依頼をすること
・入手した信用情報を返済能力の調査以外の目的に利用すること
・入手した信用情報を第三者に提供すること
指定信用情報機関間の相互交流
指定信用情報機関は、自らの加入貸金業者の依頼に基づき、他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、その依頼に応じなければならない。これは「指定信用情報機関間の相互交流」と呼ばれる仕組みであり、貸金業者がより正確に顧客の総借入残高を把握するために必要不可欠な制度である。
情報提供の記録と保管
指定信用情報機関は、加入貸金業者などに情報を提供した場合、提供した情報の内容などの記録を作成し、その記録を作成後3年間、適切に保管しなければならない。



