学資保険
学資保険の税金はいつ・いくらかかる?一時所得の計算方法と節税のポイントを徹底解説

この記事では、学資保険の税金がかかるタイミングと金額の目安、一時所得の計算方法、税金を抑える方法、受取時期による課税の違いまで、シミュレーションを交えて詳しく解説します。
一時所得の計算方法

学資保険の満期金や祝い金は、原則として「一時所得」に分類されます。
一時所得の計算式は次の通りです。
一時所得 =(受取金額 − 支払保険料の総額 − 特別控除50万円)× 1/2
例えば、支払総額200万円の学資保険で満期時に250万円を受け取った場合、計算は次の通りです。
1.受取金額:250万円
2.支払保険料総額:200万円
3.差額:50万円
4.特別控除50万円を差し引くと0円
5.よって課税対象額は0円(税金はかからない)
このように、特別控除50万円があるため、多くのケースでは税金が発生しません。ただし、複数の学資保険や他の一時所得がある場合は合算されるため注意が必要です。
税金を抑える方法

学資保険の税負担を抑えるためには、次のような方法があります。
・受取額が特別控除50万円を超えないよう契約設計する
・満期金と祝い金を複数年に分散して受け取る
・他の一時所得と同じ年に集中して受け取らないよう調整する
・契約者を変更して課税対象者を分ける(贈与税に注意)
特に「受取時期の分散」と「他の所得とのバランス調整」が効果的です。他の生命保険満期金や退職金などと受取年度が重ならないようにすると、課税額を抑えられます。
税額シミュレーション事例

ケース1:1年で一括受取
支払保険料総額:200万円
受取金額:300万円
他の一時所得なし
計算式:
(300万円 − 200万円 − 50万円)× 1/2 =(50万円)× 1/2 = 25万円(課税対象額)
この25万円は総合課税の所得に加算されます。課税対象額がこの水準であれば、適用される所得税率は5%です。
・所得税:25万円 × 5% = 1万2,500円
・復興特別所得税:1万2,500円 × 2.1% ≈ 260円
・住民税:25万円 × 10% = 2万5,000円
合計負担額は約3万7,760円です。
なお、他の所得がある場合は総合課税により実際の税率が5%を上回る可能性があります。
ケース2:2年に分けて受取
支払保険料総額:200万円
受取金額:150万円を2年連続で受取(合計300万円)
他の一時所得なし
1年目:
(150万円 − 100万円 − 50万円)× 1/2 = 0円(非課税)
2年目:
(150万円 − 100万円 − 50万円)× 1/2 = 0円(非課税)
結果として、所得税・住民税ともに発生しません。受取年度を分散させるだけで、上記ケース1と比較して約3万8千円の節税効果が得られます。
2025年度税制改正による注意点
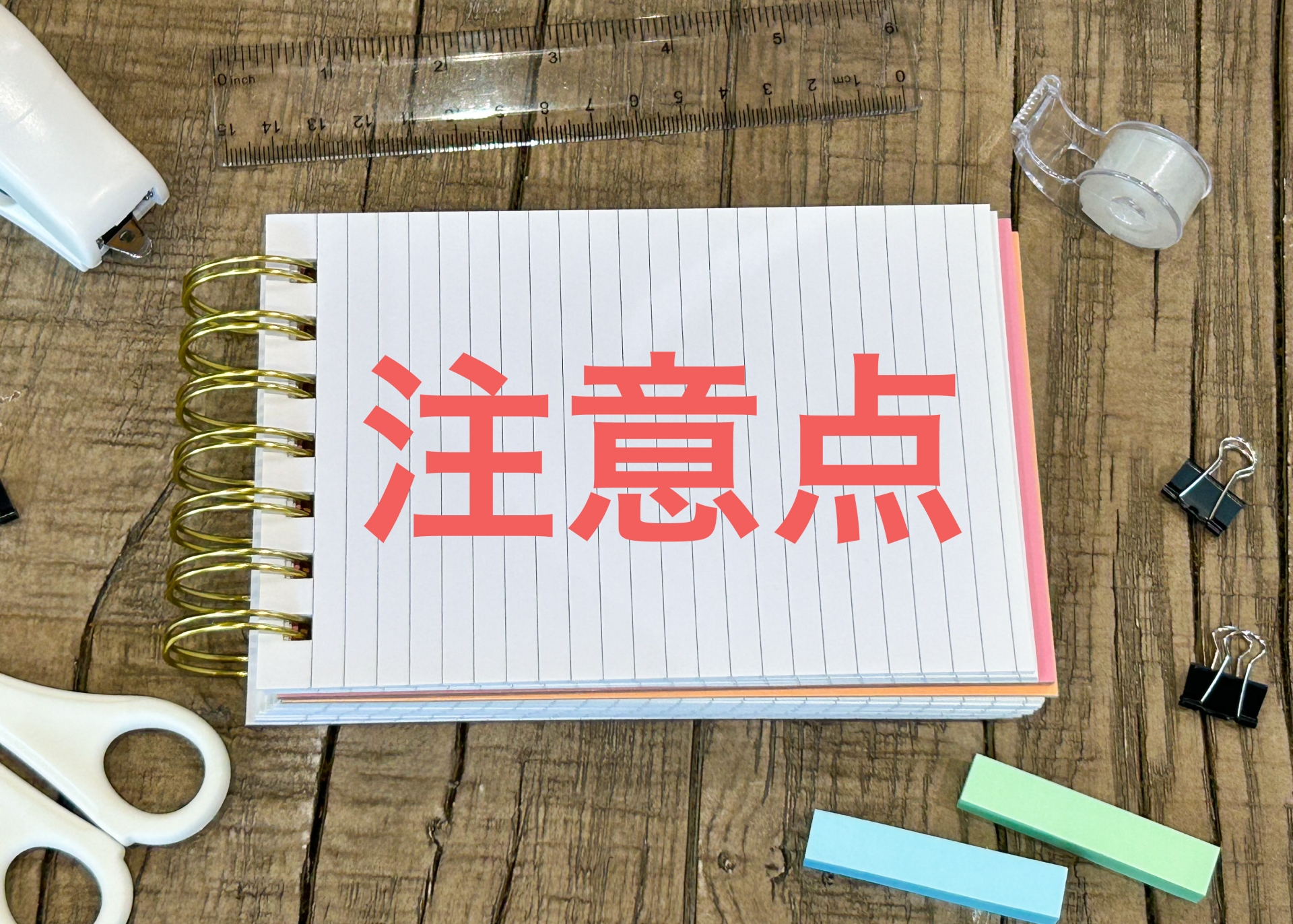
2025年分の所得税から、基礎控除額が48万円から58万円に引き上げられます。一方、住民税の基礎控除額は43万円のまま据え置きです。また、2024年度に実施された定額減税(住民税1万円の減額)は2025年度には行われないため、前年よりも住民税負担が増えたように感じるケースがあります。
受取時期によっては、こうした改正や減税終了の影響で税額が変動するため、事前に確認しておくことが大切です。
まとめ
学資保険は、多くの家庭で非課税となるケースが多いですが、複数契約や他の一時所得と合算されると課税対象になる場合があります。一時所得の計算式と特別控除の仕組みを理解し、受取時期を分散させるなどの工夫をすることで、税負担を大きく抑えることができます。
教育資金は額も大きく、受取時期が家計に直結するため、事前にシミュレーションして計画的に進めましょう。
参考文献
国税庁「一時所得」
国税庁「生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



