生命保険
保険のプロが語る!「保険貧乏」にならないための家計管理術

「将来が不安だからと、たくさんの保険に入ったら、かえって生活が苦しくなってしまった…」
将来のリスクに備えるために、生命保険や医療保険、自動車保険など、さまざまな保険に加入している方は多いでしょう。しかし、その保険料が家計を圧迫し、「保険貧乏」になってしまっては本末転倒です。
この記事では、保険料が家計を圧迫する原因と対策について解説します。必要な保障を見極める重要性、そして保険料と貯蓄・投資をバランスよく配分する考え方まで。保険のプロが教える「保険貧乏」にならないための家計管理術を提案します。
保険料が家計を圧迫する原因と対策

保険料が家計を圧迫する主な原因は、「保障の過剰な契約」と「保険の種類」にあります。
原因:保障の過剰な契約
・高額な保障額の設定:「万が一に備えて、保険金額は多ければ多いほど安心」と考え、必要以上に高額な死亡保障や入院給付金を設定してしまうと、保険料は高くなります。
・不要な特約の付加:「あれば安心だから」と、主契約にたくさんの特約を付加してしまうと、保険料が積み重なり、家計を圧迫する原因となります。
対策:
・必要保障額の算出:ご自身の家庭の状況(遺族年金、配偶者の収入、子どもの教育費など)を考慮し、本当に必要な保障額を計算しましょう。
・不要な特約の見直し:本当に必要な特約だけを厳選し、不要な特約は外しましょう。
原因:貯蓄性のある保険への過度な依存
・保険料が割高:終身保険や養老保険といった貯蓄性のある保険は、保障と貯蓄の両方を兼ね備えている分、保険料が割高になります。
・運用効率が低い:貯蓄性のある保険は、iDeCoやNISAなどの資産形成制度に比べて、運用効率が低い場合があります。
対策:
・保障は「掛け捨て」、貯蓄は「投資」と割り切る:万が一の備えは、保険料が安価な掛け捨ての定期保険で確保し、浮いたお金をiDeCoやNISAといった非課税制度で資産形成に回すことで、保険と貯蓄を両立させ、家計への負担を減らせます。
必要な保障を見極める重要性

「保険貧乏」にならないためには、ご自身のライフプランに合った、本当に必要な保障だけを見極めることが最も重要です。
ライフステージに応じた必要保障額の変化
・独身者:死亡保障は、親の介護費用や葬儀費用など、必要最低限の金額に抑える。
・子育て世代:子どもが幼い時期は、教育費や養育費など、保障額が最も大きくなる時期です。
・子どもの独立後:子どもが独立し、住宅ローンも完済していれば、高額な死亡保障は不要になる可能性が高いです。
このように、ライフステージに応じて必要な保障額は変化するため、定期的に保険の見直しを行うことが大切です。
公的保障制度との連携
日本の公的保障制度(健康保険、厚生年金、高額療養費制度など)は、万が一の際にご自身や家族の生活を支える土台となります。
・公的保障の確認:ご自身が加入している公的保障の内容を把握し、公的保障だけでは賄いきれない部分を、民間の保険で補うという考え方で保障を見極めましょう。
・例えば、高額療養費制度:ひと月の自己負担額には上限がありますが、差額ベッド代や先進医療費、食事代などは対象外です。医療保険は、これらの公的保障で賄いきれない費用に備えるために加入します。
【補足】: 2025年8月から予定されていた高額療養費制度の改正は、実施が見送られました。 ただし、公的医療費の自己負担が増える可能性は将来も残るため、民間保険の必要性は引き続き高いと言えます。
保険料と貯蓄・投資のバランス
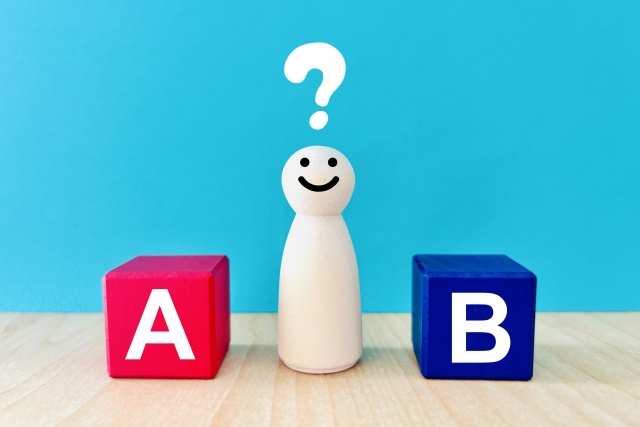
家計全体を考える上で、保険料と貯蓄・投資のバランスを取ることが非常に重要です。
貯蓄・投資を優先する考え方
・目的:将来の老後資金や、教育資金など、お金を「増やす」ことを重視する場合。
・バランス:保険料の負担を最小限に抑え、浮いたお金をiDeCoやNISAといった非課税制度で運用することで、効率的に資産を形成できます。
保障を優先する考え方
・目的:収入が安定しない時期や、一家の大黒柱として家族を支えている場合など、万が一の事態に備えることを最優先する場合。
・バランス:必要な保障を確保するために、保険料に一定の割合を充てることを優先します。しかし、保険料が家計を圧迫しないよう、定期保険などの安価な保険で備えることを検討しましょう。
まとめ:「保険貧乏」にならないための家計管理術
「保険貧乏」にならないためには、闇雲に保険に加入するのではなく、賢く家計を管理することが重要です。
・保障の過剰な契約や貯蓄性のある保険への過度な依存が、家計を圧迫する主な原因です。
・ライフステージに応じた必要な保障を見極め、定期的に見直しましょう。
【補足】: 2025年6月には年金制度改正法が成立し、遺族年金の男女差解消など、今後公的年金制度も変更される可能性があります。これにより、将来受け取れる年金額が変わる可能性があるため、定期的な見直しはより重要になります。
遺族年金について、どのような検討が行われているのかは、以下の記事を参考にしてください。
2028年施行予定の遺族年金改正:年収500万円の夫が亡くなった場合、妻の年金はどう変わる?
・保険料と貯蓄・投資のバランスを考え、ご自身の家計に合った保険戦略を立てましょう。
この記事を参考に、保険を「いざという時の安心」のためだけに活用し、家計をスリムにすることで、豊かな生活を送っていきましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



