自動車保険
搭乗者傷害保険とは?補償内容と人身傷害保険との違い・必要性を徹底解説

車を運転する方の中には「事故で自分や同乗者がケガをしたら、どこまで保険で守られるのだろう?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。自賠責保険や人身傷害保険があるのに、さらに搭乗者傷害保険まで必要なのかと迷う人も少なくありません。実際に補償の違いがわかりにくいため、加入すべきかどうか判断が難しいのが現実です。
この記事では、搭乗者傷害保険の補償内容やメリット、そして実際のシミュレーションを交えながら「加入すべき人」と「不要な人」の違いを整理しました。読み終える頃には、自分にとって本当に必要かどうかを判断できるようになるはずです。
搭乗者傷害保険とは?補償内容と人身傷害保険との違いを徹底解説
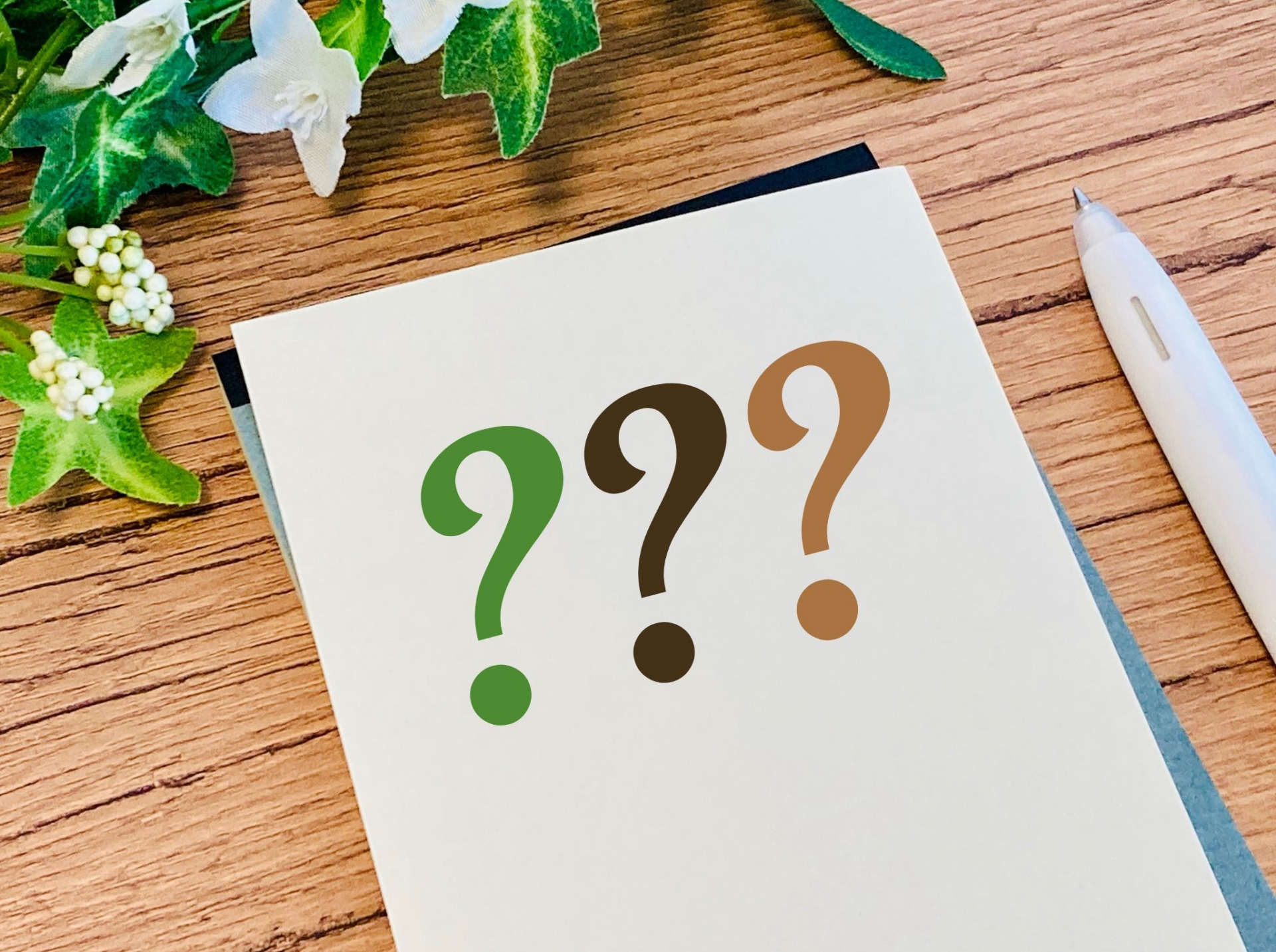
搭乗者傷害保険は、自動車に乗車中の事故によって運転者や同乗者が死傷した場合に保険金が支払われる補償です。自分自身だけでなく、同乗している家族や友人なども対象となるのが特徴です。
人身傷害保険が「実費補償」であるのに対し、搭乗者傷害保険は「定額補償」である点が大きな違いです。そのため、医療費以外の雑費や収入減少に対して自由に使えるのがメリットです。
搭乗者傷害保険の補償内容|死亡・後遺障害・入通院の支払い方式
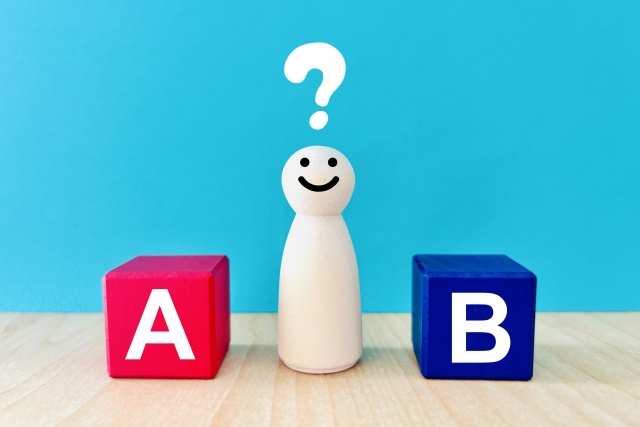
契約内容によって異なりますが、一般的には次のような場合に保険金が支払われます。
・事故による死亡 → 一定期間内に亡くなった場合、契約金額が支払われます。
・後遺障害 → 障害の程度に応じて契約金額の一部が支払われます。
・入通院 → 入院や通院に対して保険金が支払われます。ここには2種類の方式があります。
- 日数払い方式:入院日数や通院日数に応じて日額で支払われる方式
- 部位・症状別払い方式:骨折や打撲など、ケガの部位や症状に応じてあらかじめ定められた金額が支払われる方式
どちらが適用されるかは保険会社や契約内容によって異なるため、加入前に確認しておくことが重要です。
また、支払われる条件には制限があります。例えば、死亡や後遺障害については「事故日からその日を含めて180日以内」が対象とされるケースが一般的です。さらに、保険会社によっては搭乗者傷害保険を取り扱っていないところもあり、特約として選べない場合もあります。
搭乗者傷害保険のメリットとは?治療費以外の出費に使える定額補償
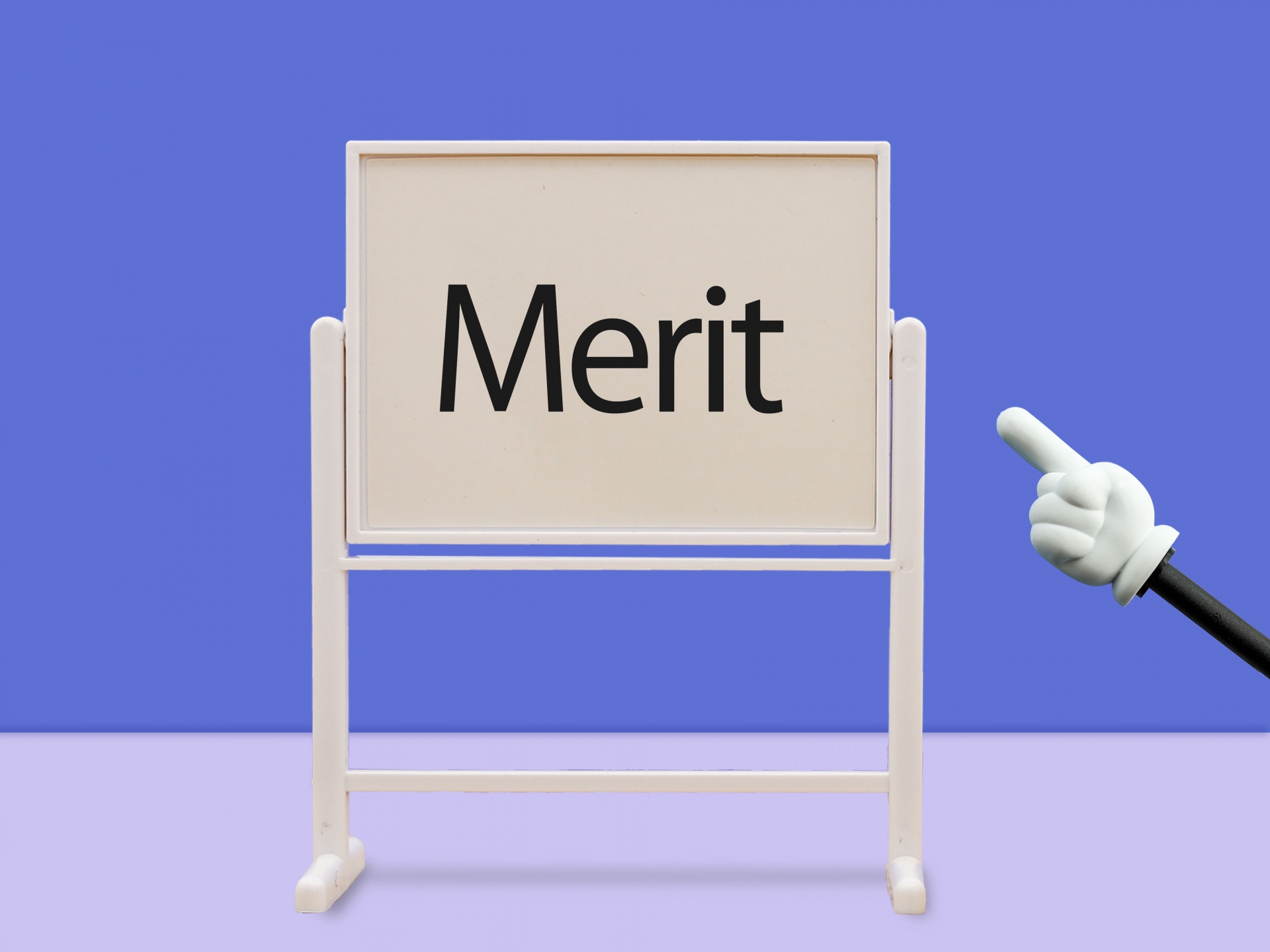
搭乗者傷害保険は、人身傷害保険と比べて「定額で支払われる」点が特徴です。そのため、治療費以外の費用に充てられるというメリットがあります。
例えば、差額ベッド代や家族の交通費、休業による収入減少など、人身傷害保険ではカバーできない部分を補える点は安心材料になります。また、同乗者への補償が明確にできるため、友人や知人をよく乗せる方にとっても有効です。
搭乗者傷害保険は必要か不要か?実際のシミュレーションで確認

実際にどのように役立つのかをシミュレーションで見てみましょう。
【ケース1:家族4人での事故】
父親が入院30日、母親が通院15日となった場合、人身傷害保険だけでは治療費は全額補償されますが、休業損害や雑費は対象外です。
一方、搭乗者傷害保険を付帯し、入院日額5,000円・通院日額3,000円で契約していた場合、合計19万5,000円が支払われ、実費以外の負担をカバーできます。
【ケース2:同乗していた友人がケガ】
通院10日の場合、人身傷害保険で治療費は出ますが、仕事を休んだ損失は補償されません。
搭乗者傷害保険があれば3万円が支払われ、追加的なサポートになります。
【ケース3:高齢の両親が同乗】
入院が長引いた場合、差額ベッド代や介護タクシー代などの費用が想定されます。日額5,000円の契約なら入院60日で30万円が支払われ、治療費以外に充てられます。
搭乗者傷害保険が不要となるケース|無駄を避ける判断基準

逆に、必ずしも加入が必要でない場合もあります。
・人身傷害保険を「無制限」に設定している場合 → 実費はほぼ全てカバーされるため、上乗せの必要性は低い
・同乗者がほとんどいない場合 → 補償のメリットは限定的
・他の医療保険や傷害保険で十分に備えている場合 → 重複する可能性が高い
自賠責保険・人身傷害保険との違いを比較して理解する

搭乗者傷害保険の必要性を判断するうえで大切なのは、他の補償との違いを正しく理解することです。特に自賠責保険や人身傷害保険と役割が混同されやすいため、整理してみましょう。
・自賠責保険 → すべての車に加入が義務付けられている最低限の補償。死亡時の上限は3,000万円と定められており、重大な事故では不足するケースもある。
・人身傷害保険 → 実際にかかった治療費や休業損害などを「実費」で補償する。家族や同乗者も幅広く対象にできるため、自賠責の不足を補う役割がある。
・搭乗者傷害保険 → 実費ではなく「定額」で支払われるため、治療費以外の雑費や収入減少の補てんなど自由に使える。
このように見ると、搭乗者傷害保険は「治療費そのものを補償する保険」ではなく、「自由に使える定額給付による安心感」が特徴だと理解できます。
搭乗者傷害保険の注意点|取り扱いの有無や180日以内の制限条件

搭乗者傷害保険に加入するかどうかを判断する際には、次のようなポイントに注意するとよいでしょう。
・人身傷害保険や医療保険でどこまでカバーできているかを確認する
・定額補償が自分や家族にとってどの程度必要かを考える
・普段の運転状況(同乗者の有無、子どもの送迎、友人を乗せる頻度など)を踏まえて優先度を決める
・保険会社によっては搭乗者傷害保険を取り扱っていない場合があるため、加入の可否を事前に確認する
まとめ|搭乗者傷害保険は「自由に使える定額補償」で安心をプラス
搭乗者傷害保険は、自動車事故による死傷に対して「定額補償」が受けられる制度です。人身傷害保険だけでは不足しがちな部分を補える一方、ライフスタイルや既存の補償内容によっては不要な場合もあります。また、保険会社によっては取り扱いがない場合もあるため、自分の契約内容を確認したうえで検討することが重要です。加入の有無は、自分の運転状況や家族構成に合わせて考えるとよいでしょう。
参考情報
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



