iDeCo
iDeCoの積立年数が短くてもメリットある?期間別効果検証

「老後まであと10年しかないけど、iDeCoに加入するメリットってある?」
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、長期積立が基本と言われますが、老後まで期間が短い50代や60代から始める場合でも、税制メリットは受けられるのでしょうか。結論から言うと、iDeCoは積立年数が短くても、十分に加入するメリットがあります。
この記事では、短期間(例:5年、10年)でもiDeCoに加入するメリットに焦点を当てて検証します。所得控除と運用益非課税の恩恵を具体的に解説し、どんな場合に短い期間でもiDeCoを検討すべきかまで、あなたのiDeCo運用と老後資金確保に役立つヒントを提案します。
iDeCoの積立年数が短くても加入するメリット
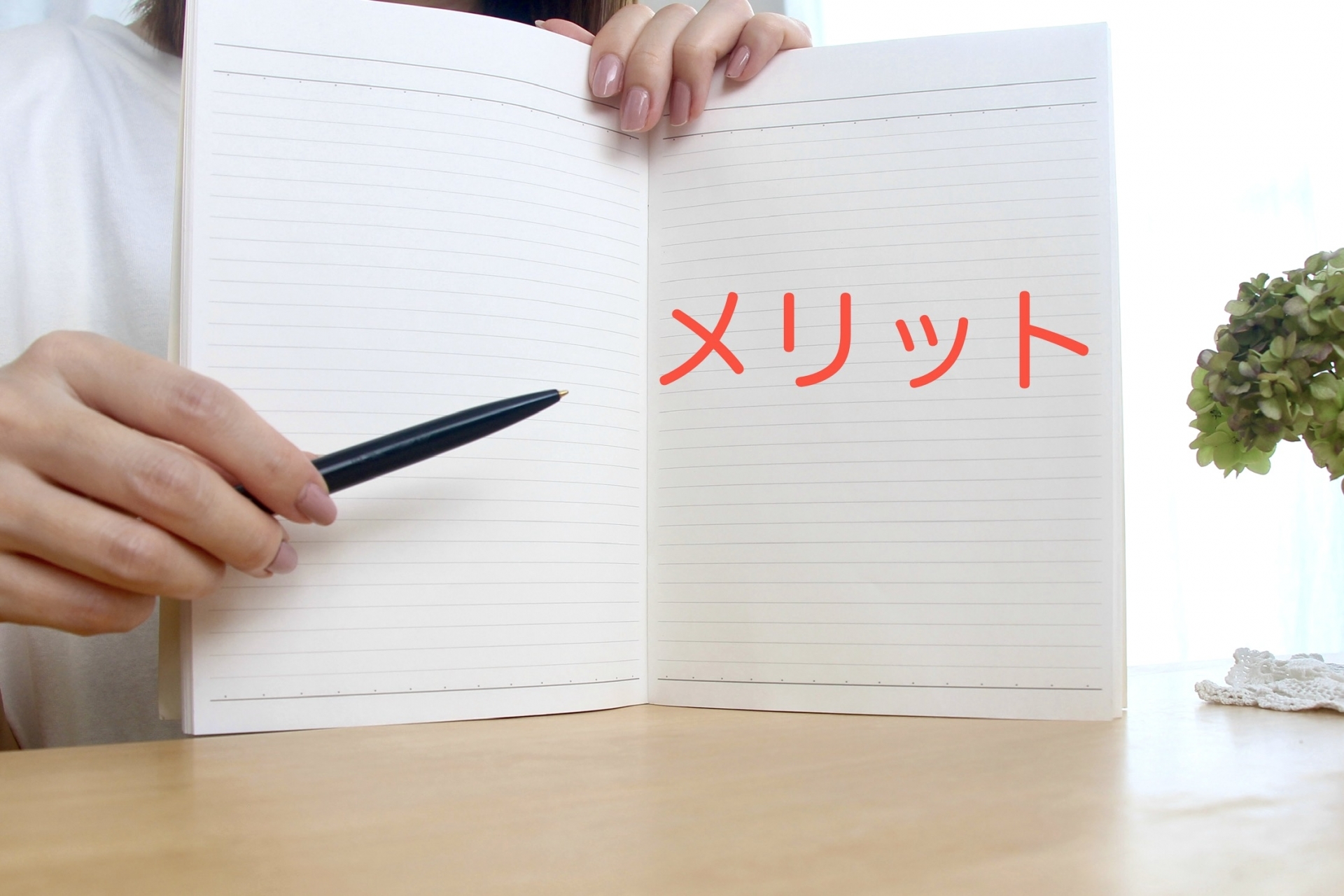
iDeCoは、積立期間が短くても、その強力な税制メリットのおかげで、預貯金や他の投資方法よりも効率的に資産を増やせる可能性があります。
積立期間が短くても「所得控除」の恩恵は確実に受けられる
iDeCoの最大のメリットは、掛金が全額所得控除になることです。これは、運用期間の長短に関わらず、掛金を拠出する期間中、毎年確実に受けられるメリットです。
・所得税・住民税の軽減効果:
例えば、55歳から60歳までの5年間、iDeCoに月2.3万円(年間27.6万円)拠出したとします。年収500万円(所得税率10%、住民税率10%)の場合、年間で約5.5万円の税金が安くなります。これが5年間続くので、合計で約27.5万円の節税が可能です。
iDeCo公式サイト かんたん税制優遇シミュレーターで計算
・短期間でも効果的: このように、積立期間が短くても、所得税率が高い人ほど、短期間でも大きな節税効果を得られます。
短い期間でも「運用益非課税」の恩恵を享受
積立期間が短くても、iDeCoの運用益非課税のメリットは享受できます。
・運用期間の長さ: iDeCoは原則60歳まで拠出できますが、60歳以降も最長75歳まで運用を継続できます。そのため、積立期間は短くても、非課税で運用できる期間はさらに長く取ることができます。
シミュレーション例:
・55歳から60歳までの5年間、月2.3万円を積立(元本138万円)。年率5%で運用した場合、60歳時点の資産額は約156万円になります。
金融庁 つみたてシミュレーターで計算
・この資産をすぐに引き出さず、70歳まで年率5%で運用を継続すれば(運用期間合計10年)、資産額は約254万円になる可能性があります。運用益約98万円、55歳からであれば116万円が非課税で得られる計算です。
カシオ 複利計算を使って計算
このように、積立期間が短くても、その後の運用継続期間を長く取ることで、非課税のメリットを享受し、資産を増やすことが可能です。
どんな場合に短期間でもiDeCoを検討すべきか?

積立期間が短くてもiDeCoを始めるべきかどうかは、あなたの現在の状況や将来の計画によって異なります。
退職金がない・少ない場合
・退職金の代わり:
退職金制度がない、または少額しか見込めない場合、iDeCoは「自分で作る退職金」として非常に有効です。退職金と同様に、受け取り時に「退職所得控除」という大きな税制優遇が適用されるため、短期間の積み立てでも、そのメリットを活かしてまとまった資金を税負担を抑えて受け取ることができます。
所得税率が高い場合
・節税効果の最大化:
所得税率が高い人(年収が高い人)ほど、iDeCoの掛金控除による節税効果が大きくなります。短期間の積み立てでも、毎年確実に税金が軽減されるメリットは非常に大きいため、高所得の方にとっては、積立年数が短くても十分に検討する価値があります。
「老後資金のラストスパート」をかけたい場合
・効率的なラストスパート:
50代に入り、子どもの教育費の負担が減るなど、家計に余裕ができた場合は、iDeCoで「老後資金のラストスパート」をかける絶好のチャンスです。所得控除による節税メリットを受けながら、効率的に資産を増やせます。
・掛金上限額の活用:
企業年金がない会社員や専業主婦(夫)のiDeCo掛金上限は月2.3万円ですが、2025年度の税制改正大綱では、会社員(企業年金なし)の上限が月6.2万円に大幅引き上げが決定しています。これが実現すれば、より多くの掛金を拠出し、短期間でも大きな資産形成を目指せます。
投資の経験がない場合
投資の練習台:
投資経験がない場合、老後まで時間がないからといってリスクの高い投資に手を出してしまうのは危険です。iDeCoであれば、金融機関が提供する低コストで分散された投資信託の中から、リスクを抑えつつ運用に慣れることができます。
【補足】2025年度税制改正と受け取り時の注意点

短期間でiDeCoを活用する方にとって、特に重要なのが受け取り時の税制です。2025年度税制改正大綱では、受け取り方に関する重要な変更も決定しています。
・退職所得控除の「10年ルール」への変更:
iDeCoを一時金で受け取る際、退職金とiDeCoの一時金を同じ年に受け取ると、控除枠を分け合うため、税負担が増える可能性があります。この合算ルールについて、現在は退職金受給から5年空ければ、iDeCoの一時金を独立した退職所得として扱える優遇措置があります。
しかし、2025年度の税制改正大綱で、この期間が「10年」に変更されることが決定しました。
・短期間加入者への影響: 50代からiDeCoを始める場合、60歳で受け取ると勤続年数とiDeCo加入期間が近くなるため、税負担が大きくなる可能性があります。この変更を考慮し、退職金の受給時期とiDeCoの一時金の受け取り時期をずらすなど、より戦略的な出口戦略を立てる必要があります。
まとめ:iDeCoは積立年数が短くても「お得」
iDeCoは、積立年数が短くても、掛金控除による節税メリットと、非課税での運用益というメリットを確実に享受できます。
・短期間でも所得控除の恩恵は大きいため、高所得者ほどメリットが大きいです。
・60歳以降も運用継続が可能なため、積立期間が短くても、非課税での運用期間を長く確保できます。
・退職金の代わりとして、あるいは老後資金のラストスパートとして、iDeCoは短期間でも活用すべき、非常に有効な手段です。
「もう遅い」と諦めるのではなく、短期間でもiDeCoのメリットを最大限に活かし、あなたの老後資金を賢く形成していきましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



