iDeCo
iDeCoとNISA、どちらから始めるべき?投資初心者向けステップ

iDeCo(個人型確定拠出年金)とNISA(少額投資非課税制度)は、どちらも非課税で資産形成ができる強力な制度です。しかし、特に投資初心者の方にとっては、その違いや、どちらから始めるべきかという点で迷ってしまうことも多いでしょう。
この記事では、iDeCoとNISA、どちらから始めるべきかという投資初心者の悩みに焦点を当てて解説します。あなたの投資目的(老後資金か、他のライフイベントもか)による判断基準、少額から始める場合の初期選択肢、そして制度理解の難易度から見た始めやすさまで、あなたが安心して一歩を踏み出すためのステップを提案します。
投資初心者向け!iDeCoとNISA、まずはここを比較しましょう

iDeCoとNISAはどちらもメリットが大きいですが、初心者が最初にどちらを選ぶか判断するために、以下のポイントで比較してみましょう。
投資目的と資金の柔軟性
iDeCoの目的: 老後資金の形成に特化しています。原則60歳まで引き出しできない「資金拘束」があるため、途中で使ってしまう心配がありません。
・こんな方へ: 「確実に老後資金を貯めたい」「退職後の生活に不安がある」
NISAの目的: 幅広い資産形成に利用できます。教育資金、住宅購入資金、老後資金など、様々な目的に利用でき、原則いつでも引き出し可能です。
・こんな方へ: 「老後だけでなく、将来の教育費や住宅購入にも備えたい」「急な出費にも対応できるようにしておきたい」
税制優遇の仕組み
iDeCoの優遇: 「掛金を出す時」「運用する時」「受け取る時」の3段階で税制優遇が受けられます。
・掛金が全額所得控除: 毎月拠出した金額が所得税・住民税の計算から差し引かれるため、現在の税金が安くなります。これがiDeCo最大のメリットです。
・運用益が非課税です。
・受け取る時も税金が優遇されます。
こんな方へ: 「現役時代から確実に税金を減らしたい」「年収が高く、所得税率が高い」
NISAの優遇: 「運用する時」に税金がかからない制度です。
運用益が非課税です。
こんな方へ: 「運用で増えたお金に税金がかからないメリットを享受したい」「手軽に非課税投資を始めたい」
制度理解と手続きの難易度
・iDeCo: 加入資格の確認(企業年金の有無など)、掛金上限の計算、年末調整・確定申告での控除手続き、原則60歳まで引き出せない制約など、NISAに比べて少し複雑に感じることがあるかもしれません。
・NISA: 証券口座開設後、商品を選んで積み立てるだけと、比較的シンプルです。非課税枠は大きいですが、年間360万円の枠内で自由に利用できます。
iDeCoとNISA、どちらから始めるべき?投資初心者向け判断基準
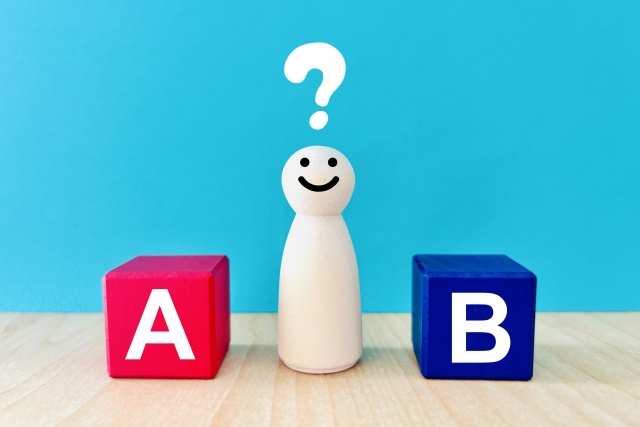
上記の比較を踏まえ、投資初心者の方がどちらから始めるべきか、具体的な判断基準を提案します。
「現役時代の節税効果」を最優先したいなら【iDeCo】から
こんな方におすすめ:
・会社員、公務員、自営業者など、所得税や住民税を支払っている方。
・確実に老後資金を貯めたいという強い意志がある方。
・60歳まで引き出せない資金拘束に抵抗がない方。
理由: iDeCoの掛金が全額所得控除になるメリットは、現役時代の手取りを直接増やす効果があり、運用成果に関わらず毎年確実に節税できます。これがNISAにはないiDeCoの最大の特徴です。特に年収が高く、所得税率が高い方ほどメリットが大きいです。
「資金の柔軟性」と「手軽さ」を最優先したいなら【NISA】から
こんな方におすすめ:
・老後資金だけでなく、教育資金や住宅購入資金など、将来使うかもしれない資金を非課税で貯めたい方。
・「まずは投資に慣れたい」という初心者で、制度がシンプルな方が良い方。
・60歳まで資金が拘束されることに抵抗がある方。
理由: NISAは、非課税で運用しながらも、必要な時にいつでも売却して資金を引き出せる柔軟性があります。手続きも比較的シンプルで始めやすいのが魅力です。
【究極の選択】余裕があれば両方を「併用」しましょう
こんな方におすすめ:
・所得税・住民税を支払っており、かつ資金の柔軟性も確保したい方。
・老後資金も他のライフイベントのための資金も、両方非課税で効率的に準備したい方。
・月々3万円以上の余裕資金がある方(iDeCoの最低掛金5,000円+NISAの積立を合わせて)。
理由: iDeCoの「現役時代の節税効果」と「老後資金を確実に貯める力」、NISAの「非課税で自由に使えるお金を増やす力」という、それぞれの強みを組み合わせることで、相乗効果で資産を増やすスピードを上げることが可能です。これが最も効率的な老後資金戦略となります。
少額から始める場合の「初期の選び方」

どちらを選ぶにしても、投資初心者はまず「無理のない範囲で少額から始める」ことが重要です。
・iDeCo: 最低掛金は月額5,000円です。この金額からでも、税金が安くなるメリットは確実にもらえます。
・NISA: 金融機関によっては月額100円から積立設定が可能です。
もし毎月数千円しか投資に回せない場合は、まずはiDeCoの月5,000円から始めることで、税金が安くなるメリットを享受しつつ、投資に慣れていくのが良いでしょう。余裕資金が増えたらNISAも始める、というステップアップも可能です。
知っておきたい!iDeCoの最新制度改正情報(2024年12月・2025年度予定)

iDeCoは、より多くの人が老後資金を準備しやすいように、今後も制度が変わっていく予定です。最新の変更点も知っておきましょう。
掛金上限額の拡大(2024年12月・2025年度予定)
2024年12月改正:
公務員や、確定給付型の企業年金がある会社員の場合、iDeCoの掛金上限が月1.2万円から月2万円に引き上げられました。
2025年度予定改正:
会社員で企業年金がない人向けのiDeCo掛金上限が、月2.3万円から月6.2万円へ大幅に増額される予定です。これが実現すれば、より多くの税金が安くなるメリットを受けられるようになります。
加入可能年齢の拡大(2025年度予定)
iDeCoに掛金拠出ができる期間が、現行の65歳未満から70歳未満へ引き上げられる予定です。これにより、より長くiDeCoを活用して老後資金を貯められるようになります。
手続きの簡素化(2024年12月改正)
会社員や公務員がiDeCoに加入する時に必要だった「事業主の証明書」が、原則不要となりました(2024年12月から)。これにより、手続きがよりスムーズになります。
受け取り時のルール変更(2026年1月予定)
iDeCoを一時金で受け取る時の「退職金との合算期間ルール」が、現在の5年から10年に延びる予定です。これにより、退職金とiDeCoをそれぞれ税金が優遇される形で受け取りやすくなります。
まとめ:あなたの「目的」と「柔軟性」で判断しましょう
iDeCoとNISA、どちらから始めるべきかという問いに、画一的な正解はありません。あなたの投資目的(老後資金の確実性か、資金の柔軟性か)、収入(税金が安くなるメリットを享受できるか)、そして制度のわかりやすさを考えて選ぶことが重要です。
・現役時代の節税と老後資金の確実性を優先するならiDeCoから。
・資金の柔軟性と手軽さを優先するならNISAから。
・両方のメリットを最大限享受したいなら、いずれかから始めて「併用」を目指すのが一番良い方法です。
まずはあなたの状況に合った方から、無理のない少額で一歩を踏み出してみましょう。その一歩が、あなたの豊かな未来を築くことにつながります。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています



