iDeCo
iDeCoで年金生活を豊かに!60歳以降も運用を続けるメリット

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、原則60歳から受け取りが始まりますが、実は60歳になったからといって、すぐに受け取らなければならないわけではありません。多くの人が60歳でiDeCoの運用を終えると思いがちですが、60歳以降もiDeCoの資産を運用し続けることは、あなたの年金生活をより豊かにするための、非常に賢い選択肢となり得ます。
この記事では、iDeCoが60歳以降も運用継続が可能なことを明確にします。さらに、運用益非課税の恩恵を長く享受する方法や、老後資金の「資産寿命」を延ばすための具体的な運用戦略まで、年金生活を不安なく、より充実させるためのiDeCo活用術を提案します。
iDeCoは60歳以降も運用継続が可能!
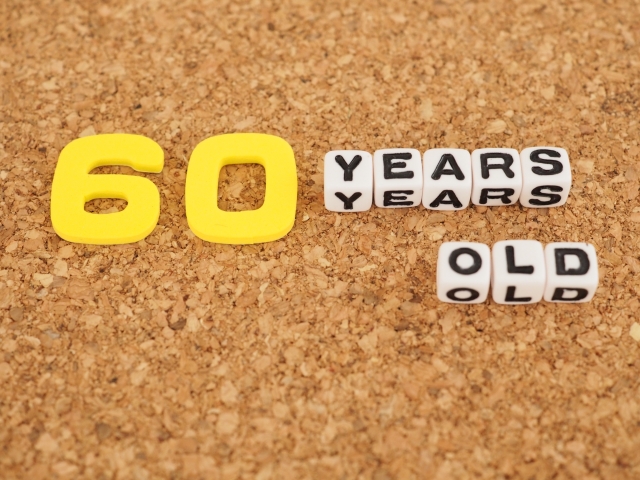
iDeCoの資産は、原則として60歳から老齢給付金として受け取ることができますが、受給開始を遅らせて、運用を継続することが可能です。
60歳以降も運用できる期間
・現在の制度: iDeCoの資産の運用は、最長で75歳まで継続することができます。つまり、60歳になった時点で無理に受け取らず、引き続きiDeCo口座内で運用を続けられるのです。
・掛金拠出期間は異なる: ただし、掛金を拠出できる期間は、原則として65歳未満までです。2025年度の税制改正大綱では、70歳未満まで加入可能年齢が延長されることが検討されています。運用継続期間と掛金拠出期間は異なる点に注意しましょう。
なぜ運用継続が可能なのか?
iDeCoは、加入者が自らの判断で老後資金を準備する制度であり、運用は自己責任で行われます。60歳でリタイアしない、あるいは公的年金の受給開始までまだ時間があるといった場合、運用を継続することで、さらに資産を増やす機会が与えられています。
運用益非課税の恩恵を長く享受する方法

60歳以降もiDeCoの運用を続ける最大のメリットは、「運用益非課税」の恩恵をさらに長く享受できることです。
複利効果を最大化し、資産をさらに育てる
・税金がかからない期間の延長: iDeCo口座内で運用している間は、投資信託の売却益や配当金、預貯金の利息など、すべての運用益が非課税です。60歳以降も運用を継続することで、この非課税期間が延び、利益が税金で引かれずに再投資され続けるため、複利効果が最大限に発揮されます。
・例: 60歳で1,500万円の資産があったとして、これをすぐに受け取らず、70歳まで年率3%で運用を継続した場合、さらに約515万円増える可能性があります。この515万円が非課税で受け取れるのは大きなメリットです。
カシオさまのシミュレーターで計算
市場変動への対応力を高める
・受給開始時期を柔軟に選べる: 60歳以降も運用を続けることで、市場が不安定な時期に無理に受け取りを開始せず、相場が回復してから受け取りを開始するといった、より有利なタイミングを選ぶことができます。
・計画的な取り崩し: 必要な時に必要な分だけiDeCo資産を取り崩し、残りは非課税で運用を継続することで、老後資金全体の「資産寿命」を延ばすことにつながります。
資産寿命を延ばすための運用戦略

60歳以降もiDeCoの運用を続ける場合、資産寿命を延ばし、豊かな年金生活を送るための戦略が重要になります。
リスク許容度の見直しとポートフォリオの調整
60歳以降は、資産を使うフェーズに近づくため、運用期間が短くなることを考慮し、リスクを抑え、安定性を重視した運用へ徐々にシフトしていくことが一般的です。
・株式比率の段階的引き下げ: 株式型投資信託の比率を徐々に減らし、比較的価格変動が穏やかな債券型投資信託や、元本確保型商品(定期預金など)の比率を増やすことを検討しましょう。
・スイッチングの活用: iDeCoでは運用商品を変更する「スイッチング」が可能です。この機能を使って、ご自身のライフプランやリスク許容度の変化に合わせてポートフォリオを調整しましょう。
・目標設定の明確化: 「何歳まで資産を維持したいか」「毎月いくら取り崩したいか」といった目標を明確にすることで、それに合わせた運用戦略が立てやすくなります。
公的年金・他の収入とのバランスを考慮した受け取り戦略
・公的年金との連携: 公的年金(国民年金、厚生年金)の受給開始年齢(原則65歳)とiDeCoの受け取り開始時期をずらすことで、税制優遇を最大限に活用できる可能性があります。例えば、公的年金が始まる65歳まではiDeCo資産を取り崩し、それ以降は公的年金をメインに、不足分をiDeCoで補う、といった方法です。
・退職所得控除の活用: iDeCoの資産を一時金で受け取る場合、「退職所得控除」が適用されます。会社からの退職金や他の退職所得との兼ね合いを考慮し、最も税負担が少なくなるように受け取り時期や方法を検討しましょう。特に2026年1月からは、一時金と退職金の受け取り間隔ルールが「5年」から「10年」に変更される予定であり、これにより税制優遇をより受けやすくなります。
・NISAとの連携: NISAで保有している資産も、老後資金の取り崩しに活用できます。iDeCoとNISAの両方を考慮し、税負担が最も少なくなるよう、最適な取り崩し順序や割合を検討しましょう。
運用を継続する上での注意点
・手数料の継続: 運用を継続する間も、口座管理手数料や運用商品の信託報酬などの手数料は引き続き発生します。
・市場リスクの継続: 運用している限り、元本割れのリスクはゼロではありません。リスクを抑えた運用にシフトしても、市場変動による資産の目減りの可能性は残ります。
まとめ:iDeCoで年金生活を「攻め」と「守り」で豊かに
iDeCoは、60歳になったからといってすぐに受け取る必要はありません。60歳以降も運用を継続することは、運用益非課税の恩恵を長く享受し、資産寿命を延ばすための非常に有効な戦略です。
・非課税運用を最大限に活用し、複利効果で資産をさらに育てる。
・リスク許容度を再評価し、安定性を重視したポートフォリオへ調整する。
・公的年金や他の収入とのバランスを考慮し、賢い受け取り開始時期と方法を選ぶ。
iDeCoを賢く活用し続けることで、あなたの年金生活はより安心で、豊かなものになるでしょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。



