iDeCo
iDeCoで「未納」になったらどうする?掛金が引き落とされない原因と対策
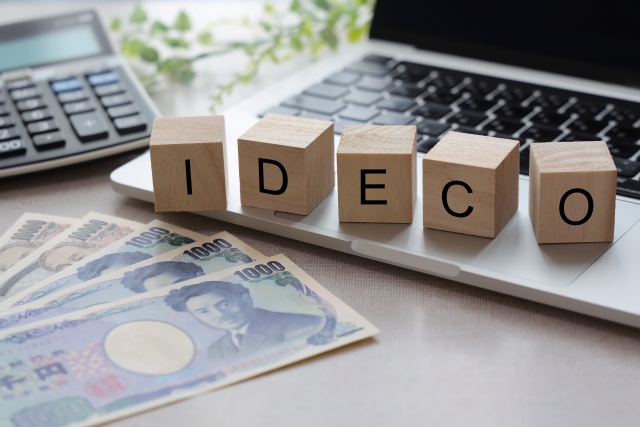
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、原則60歳まで継続して掛金を積み立てていくことで、老後資金を準備する制度です。しかし、口座残高の不足などの理由で、うっかり掛金の引き落としができない「未納」状態になってしまうことがあります。
この記事では、iDeCoで掛金引き落とし不能(未納)になった場合の対処法を解説します。また、未納のままだとどうなるか、そしてスムーズに拠出を再開するための手続きと注意点まで。iDeCoの運用を中断させずに、確実に続けるためのヒントを提案します。
iDeCoの掛金が「未納」になる主な原因と対処法
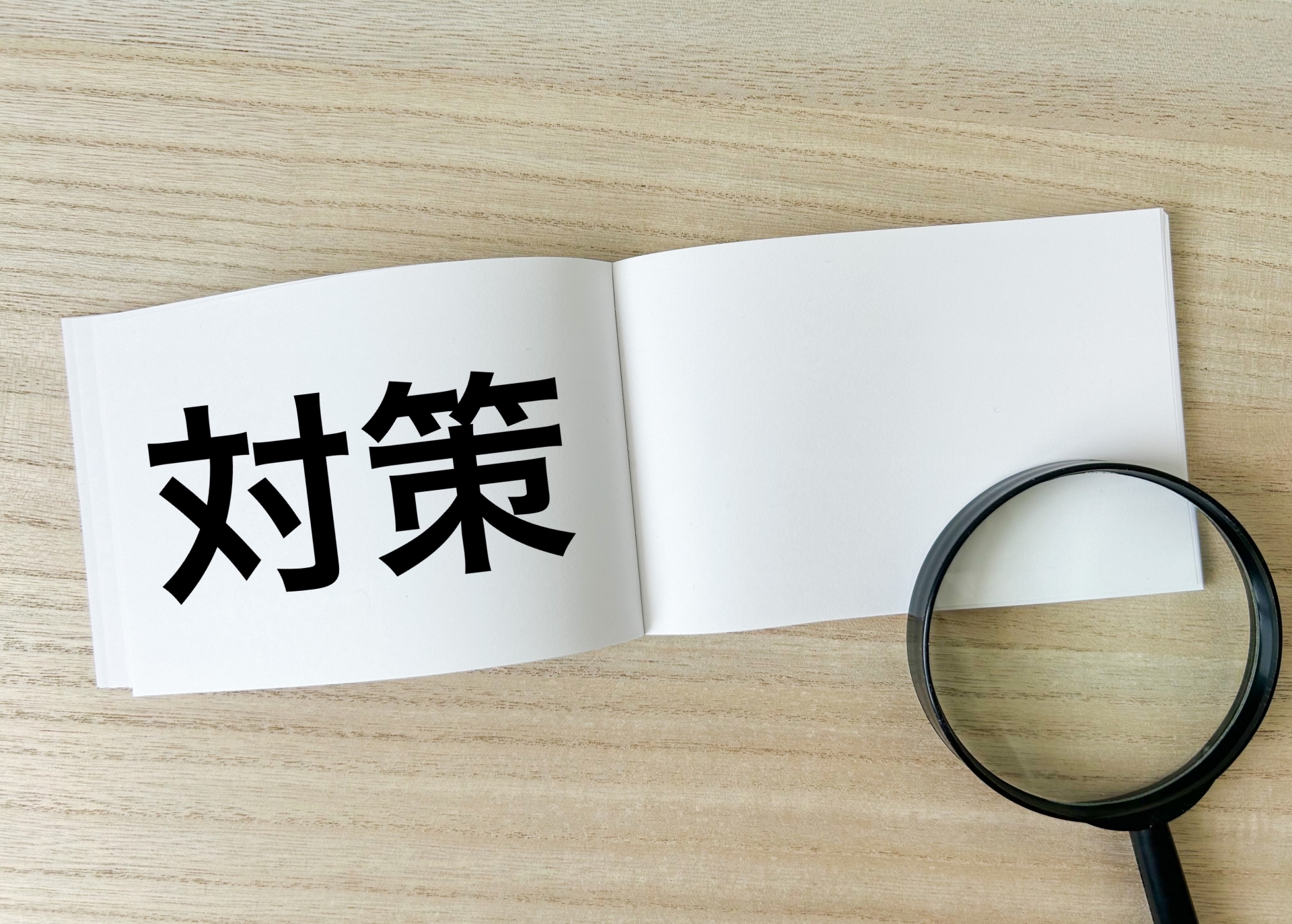
iDeCoの掛金が引き落とされない「未納」状態になる原因は、主に以下の2つです。
口座残高の不足
これが最も一般的な未納の原因です。給与振込口座とは別の口座をiDeCoの引き落とし口座に指定している場合など、残高が不足していることに気づきにくいことがあります。
対処法:
・当月分の再引き落としはない: 多くの金融機関では、引き落としができなかった場合、当月分の掛金を翌月以降に再引き落としすることはありません。
・翌月分は通常通り引き落とし: 当月が未納になっても、翌月の掛金は通常通り引き落としが行われます。未納になった月分は、そのまま拠出されずに終わります。
登録情報の不備
稀なケースですが、iDeCoの口座開設時に登録した引き落とし口座の情報に不備があったり、その後に口座が解約されてしまったりした場合にも、引き落としができなくなります。
対処法:
iDeCoの運営管理機関に連絡し、引き落とし口座の情報を確認・変更する手続きが必要です。
掛金の未納が続くとどうなる?運用への影響

iDeCoの掛金未納自体が、直ちに運用を停止させるわけではありません。しかし、未納の状態が長期にわたって続くと、思わぬリスクにつながる可能性があります。
iDeCoの運用は停止しないが、自動移換されるリスク
自動移換は、主に企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入者が、転職・退職時に移換手続きを6ヶ月以内に行わなかった場合に発生する制度です。iDeCoの掛金未納が直接的に自動移換を引き起こすわけではありませんが、長期間にわたる未納は資産形成の機会損失につながります。
掛金の未納が続くデメリット
掛金が未納になっても運用自体は継続しますが、以下のようなデメリットが生じます。
・所得控除のメリットなし: 掛金の拠出がなければ、所得控除による節税メリットは当然ながら得られません。
・資産形成の機会損失: 掛金を拠出しない期間は、新たな資産の積み立てができず、iDeCoによる資産形成のペースが止まってしまいます。
・手数料負担: 掛金を拠出していなくても、口座管理手数料(月額171円〜、金融機関によって異なる)は継続して発生します。資産が増えないのに手数料だけが引かれていくため、運用効率を低下させます。
未納からの再開手続きと注意点

未納になった場合でも、焦らずに正しい手続きを行えば、iDeCoの運用を継続できます。
再開手続きの流れ
1.残高不足の場合:
・当月分は未納で終わりますが、翌月分からは通常通り引き落としが行われます。
・特に複雑な手続きは必要なく、翌月以降の引き落とし日に口座残高を確保しておけば問題ありません。
・ただし、2ヶ月連続で未納になることがないよう、注意が必要です。
2.自動移換されてしまった場合:
・「運用指図者移換手続き」が必要です。
・移換手続きは、iDeCoの運営管理機関に「個人別管理資産移換依頼書」などの書類を提出して行います。
・移換が完了すると、自動移換されていた資金が再びiDeCo口座に戻り、運用を再開できるようになります。
再開手続きの注意点
・手数料が発生: 自動移換された資産をiDeCo口座に戻す際には、手数料が発生します。無駄なコストを避けるためにも、長期の未納状態は避けましょう。
・運用が再開するまでの期間: 手続きには時間がかかります。再びiDeCoの運用を再開できるまでには、数週間から数ヶ月かかる場合もあります。
まとめ:iDeCoの未納はすぐに解決し、確実に拠出を続けよう
iDeCoの掛金が未納になったとしても、すぐに焦る必要はありません。しかし、放置すると所得控除のメリットを逃し、資産形成の機会損失につながるリスクがあります。
・引き落とし不能の原因を特定し、残高不足の場合はすぐに口座に資金を入金しましょう。
・長期的な未納状態は避け、資産形成のペースを維持しましょう。
・万が一、未納が続いてしまった場合は、速やかに再開手続きを行い、iDeCoの運用を継続することが大切です。
iDeCoの強力な税制メリットを最大限に活かすためにも、毎月の掛金拠出を確実に続け、豊かな老後を築いていきましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



