就業不能保険
20〜30代でも必要?若年層の就業不能保険加入メリット

この記事では、若年層向けに公的制度や一次情報を基に、就業不能保険のメリットと注意点をしっかり解説します。
若年層でも就業不能リスクは低くない

公的制度のデータによれば、30代で傷病手当金を受給する人は、同年代で死亡する人のおよそ6倍に上るとされています。これは、病気やケガによる長期的な就業不能が、死亡リスクよりも頻繁に発生していることを示しています。
早期加入のメリット
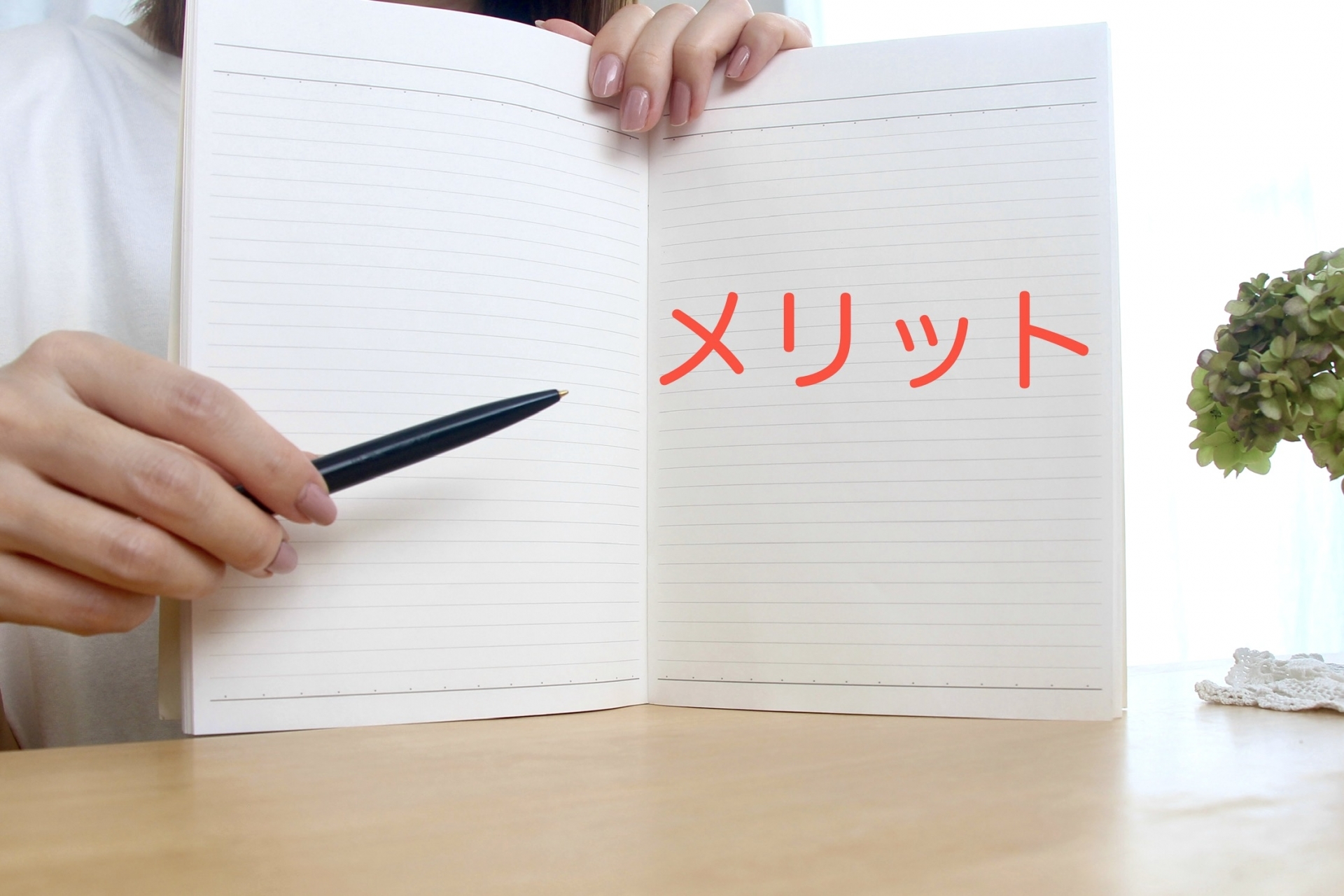
・若年で健康な段階で加入することで、保険料が比較的割安
・持病が少ないため加入審査に通りやすい
・契約後に健康状態が変化しても、契約条件を維持できる
特に精神疾患は加入後では保障が難しくなるため、症状が出る前に検討しておくことが大切です。
若年層向け低価格プランの特徴

・保障期間を短くし、保険料を抑えた設計
・医師の診断や入院を給付条件としたシンプルなプラン
・月額給付型など、生活費補填に特化した設計
まずは必要最低限の保障からカバーし、後から手厚くする方法も有効です。
免責期間と精神疾患の保障に関する注意点
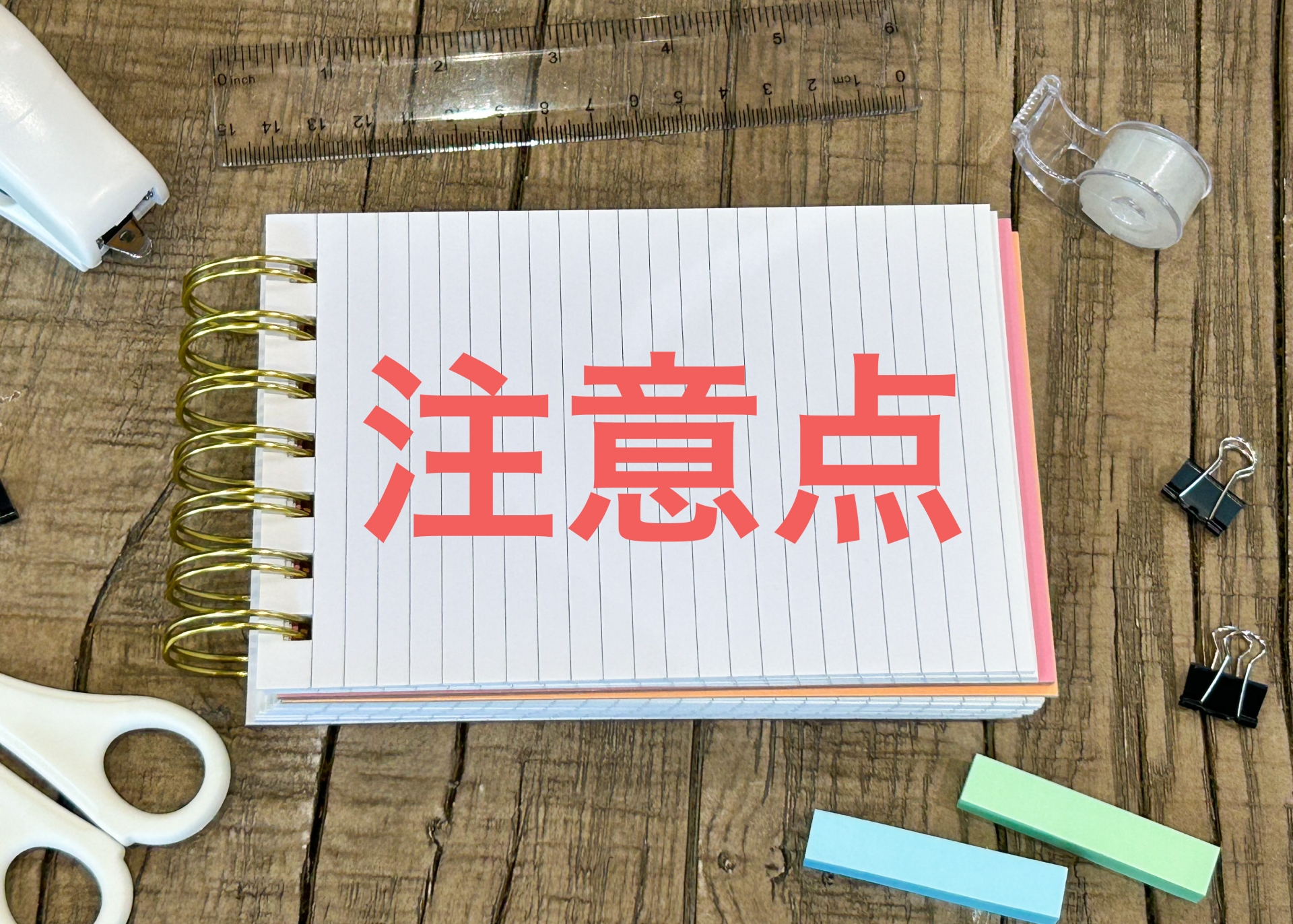
多くの就業不能保険には、60日または180日の免責期間が設定されており、その間は給付が開始されません。短期の就業不能には無力な場合があります。また、精神疾患を対象外とする、あるいは給付額・期間に制限をつける商品も多く、契約前に詳細な条件の確認が必須です。
キャリアとの関係・保障の意義

長期の就業不能は、収入の減少だけでなく、昇進や資格取得といったキャリア形成の機会を逸するリスクにもつながります。就業不能保険は生活費を守るだけでなく、キャリアの再構築の時間的余裕を確保する役割も果たします。
ケーススタディ

・27歳男性(会社員):交通事故による骨折・手術後、8か月休職。免責期間後、月額10万円の給付金で生活費を維持。
・32歳女性(フリーランス):精神疾患で1年半休業。公的制度の対象外だったが、就業不能保険の給付金で貯蓄を維持し復職。
いずれも仮想例ですが、若年でも長期就業不能は起こりうる現実です。
加入前に考えるべきポイント

・会社員は傷病手当金(最長1年6か月・給与の約2/3)を受給可能、自営業やフリーランスは対象外
・現在の貯蓄額や生活費の固定費割合の確認
・職業別の就業不能リスクの違いを理解する
・精神疾患の保障範囲と免責期間を確認
まとめ
生命保険文化センターの2024(令和6)年度「生命保険に関する全国実態調査」によると、就業不能保険(生活障害・就業不能保障保険・特約)の世帯加入率は17.2%で、現役世代(30〜34歳)では28.3%に上ります。
若年層は死亡リスクが低いとはいえ、長期の就業不能による影響は大きく、公的制度だけでは不足するケースもあります。早めの保険による備えが、自身の生活と将来を守る理由になります。
参考:
生命保険文化センター「2024年度 生命保険に関する全国実態調査」
全国健康保険協会「傷病手当金について」
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



