FPによる貸金業法学習記録
過剰貸し付け等の禁止と総量規制に関する基礎知識
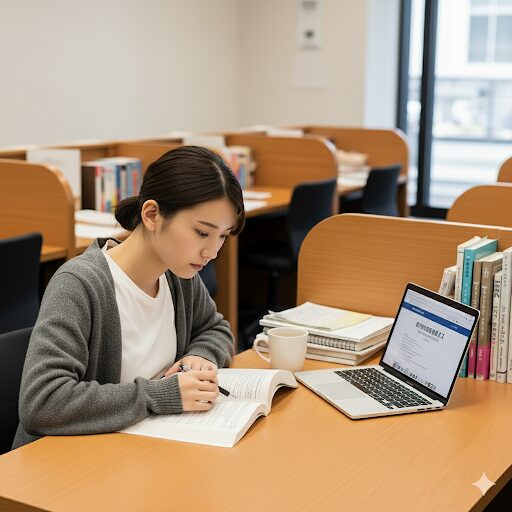
この記事は、CFPが2025年11月16日実施の貸金業務取扱主任者を目指すために、自身の勉強記録として残すブログです。
※本記事は筆者の学習記録であり、その内容の正確性には万全を期しておりますが、法令改正等により変更される可能性があります。実際の業務や判断においては、必ず最新の法令や専門家の助言を確認してください。
貸金業法は、借り手の生活の安定を守るため、貸金業者に対して様々な規制を課している。その中でも、特に重要なのが過剰貸し付け等の禁止と、その具体的なルールである総量規制である。これらの規定は、多重債務問題の発生を抑制し、健全な貸金市場を維持することを目的としている。
過剰貸し付け等の禁止の原則
貸金業法は、貸金業者が貸付契約を締結するにあたり、顧客の返済能力を超える貸付けを行ってはならないと定めている。
返済能力の調査と過剰貸し付けの禁止
・貸金業者は、貸付契約を締結する際、必ず顧客の返済能力の調査を行わなければならない。
・この調査の結果に基づき、その顧客の返済能力を超える貸付けは禁止される。
・この過剰貸し付けの禁止は、個人顧客向け貸付けだけでなく、法人向けの貸付けについても同様に適用される。
・さらに、貸付け本体だけでなく、保証契約においても、顧客の返済能力を超える過剰な保証をすることは禁止されている。
総量規制(個人過剰貸し付け契約の禁止)の詳細
過剰貸し付け等の禁止の原則を、特に個人顧客に対する貸付けについて具体的に規定したものが、いわゆる総量規制である。
総量規制の具体的な内容
・個人顧客に対しては、貸金業者からの総借入残高が、原則としてその顧客の年収の3分の1を超える新たな貸付けを行うことは禁止されている。
・この「個人顧客の総借入残高」を、法令上は個人顧客合算額という。これは、これから契約しようとする貸付けと、これまでの貸付け残高、そして他の貸金業者が行った貸付けを合算した金額である。
・ここでいう年収には、給与や賞与の他、年金、恩給、不動産投資による収入(家賃収入)、事業所得なども含まれる。
総量規制の適用対象外
・総量規制は、個人顧客に対する貸付けに関する規制であるため、法人の保証契約や法人向けの貸付けは対象とならない。
・また、個人の保証契約についても、総量規制の対象には含まれない。
総量規制の例外と除外契約
顧客の利益保護や経済取引上の必要性から、総量規制の対象外とされる除外契約と、残高は算入されるが年収の3分の1を超えても許容される例外契約が存在する。
総量規制の対象外となる「除外契約」
以下の契約は、個人顧客合算額に算入されず、総量規制の対象外となる。
・不動産の建設、購入、または改良に必要な資金の貸付けに係る契約(つなぎ融資を含む)
・自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約
・個人顧客またはその親族で生計を一つにする者の高額療養費を支払うための資金の貸付けに係る契約
・手形の割引を内容とする契約
・金融商品取引法の規定する有価証券を担保とする貸付けに係る契約
・不動産を担保とする貸付けに係る契約
・売却予定の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約
総量規制の「例外契約」
以下の契約は、個人顧客合算額には算入されるものの、顧客の利益の保護に支障を生じることがないため、年収の3分の1を超えても許される例外となっている。
・個人顧客に一方的に有利となる借換の契約。具体的には、毎回の返済額や総返済額が減少し、かつ、追加の担保の差し入れや保証を要求されない場合である。
・貸付の残高を段階的に減少させるための借り換え
・個人またはその親族で生計を一つにする者の緊急な医療費を支払うための貸付けの契約(高額療養費の支払いのための貸付けは除外契約となるため、これには含まれない)
・個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約。特定費用とは、社会通念上、緊急と認められる費用である。
・配偶者と合わせた年収の3分の1以下の貸付けに係る契約(配偶者の同意がある場合)
・ただし、上記の「配偶者と合わせた年収の3分の1以下の貸付け」の例外規定には、金額が10万円を超えず、返済期間が3ヶ月を超えないという要件を満たすものも含まれる。
日本貸金業協会の除外貸付けと、例外貸付に関する記事も参照。



