自動車保険
車両保険の免責金額とは?仕組み・設定方法・事故時のシミュレーションを解説

車両保険における免責金額とは?

免責金額とは、事故が発生して車両保険を使う際に、契約者が自己負担する金額のことを指します。例えば免責金額を「5万円」に設定している場合、修理費用が30万円かかったとしても、保険会社からの支払いは25万円となり、残りの5万円は契約者が負担することになります。
つまり、免責金額は「自己負担のルール」であり、これをどの水準に設定するかで、事故時の家計負担や月々の保険料が変わってくるのです。
免責金額の仕組み

車両保険の免責金額は、通常「1回目の事故」と「2回目以降の事故」で異なる設定が可能です。たとえば「免責金額 1回目:0円/2回目以降:10万円」といった形です。
この仕組みには以下の意味があります。
・1回目の事故は負担なし(安心感を重視)
・2回目以降は一定額の自己負担を設定(過度な請求抑制)
特に、複数回の事故を起こした際には、保険会社が負担する金額を抑える役割を果たしています。
免責金額と保険料の関係

免責金額の水準は、毎月の保険料に直接影響します。一般的に次のような関係があります。
・免責金額を低く設定(例:0円)→ 保険料は高くなるが、事故時の負担は少ない
・免責金額を高く設定(例:10万円)→ 保険料は安くなるが、事故時の負担は大きい
つまり、保険料を抑えたい方は免責金額を高めに、事故時の安心感を優先する方は免責金額を低めに設定するのが基本です。
免責金額の設定方法と選び方

免責金額の設定を考える際には、家計のバランスや車の利用状況を踏まえて選ぶことが重要です。以下の観点を参考にしてください。
・貯蓄に余裕がある → 免責金額を高めに設定し、毎月の保険料を節約
・事故時の負担をできるだけ避けたい → 免責金額を低めに設定し、安心を重視
・新車や高額な車 → 修理費が高額になりやすいため、免責金額を低めにするのがおすすめ
・古い車や使用頻度が少ない → 免責金額を高く設定し、保険料を抑える選択も合理的
シミュレーション:事故時の自己負担額の違い
例えば修理費用が30万円かかったケースを考えてみましょう。
・免責金額0円の場合 → 自己負担は0円、保険会社の支払いは30万円
・免責金額5万円の場合 → 自己負担は5万円、保険会社の支払いは25万円
・免責金額10万円の場合 → 自己負担は10万円、保険会社の支払いは20万円
このように、同じ事故でも免責金額の設定次第で、家計の負担は大きく変わります。万一の出費をどこまで自己負担できるかを踏まえて、現実的なラインを見極めることが大切です。
シミュレーション:複数回事故を起こした場合
免責金額を「1回目:0円/2回目以降:10万円」に設定している場合、次のような違いが出ます。
・1回目の事故(修理費用30万円) → 自己負担0円、保険会社の支払い30万円
・2回目の事故(修理費用30万円) → 自己負担10万円、保険会社の支払い20万円
最初の事故では安心して保険を使えますが、同じ年に再び事故を起こすと、自己負担が大きく増える仕組みです。複数回事故を想定して備えるかどうかも、免責金額の選び方に影響します。
具体的なケース別の選び方
免責金額の設定はライフスタイルや車の価値によって最適解が変わります。以下のケースを参考にしてください。
・新車を購入したばかり(初年度) → 修理費が高額になりやすく、ちょっとした損傷でも出費が大きいため、「免責金額0円」や「1回目0円/2回目10万円」といった安心重視の設定が適しています。
・古い車に乗っている場合 → 車の市場価値が低く、修理費と保険金とのバランスが悪いこともあるため、免責金額を高めに設定し、保険料を節約する方が合理的です。場合によっては車両保険を外す選択肢も考慮に値します。
免責金額に関する注意点
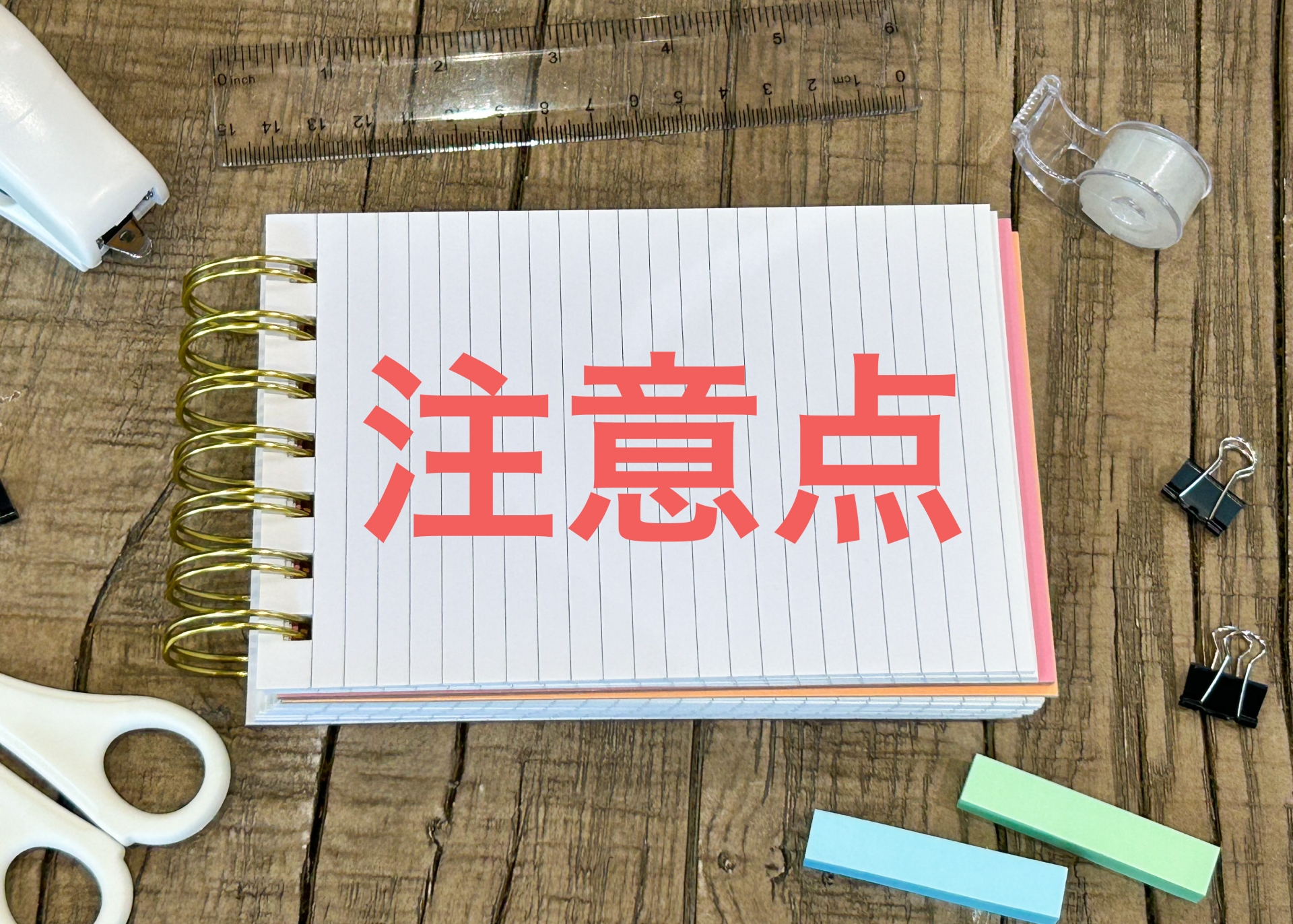
免責金額には知っておきたい注意点もあります。
・全損事故や盗難の場合は免責金額が適用されず、保険金が全額支払われるケースもある
・相手がいる事故(もらい事故)では、免責金額が発生しない場合もある
・事故の種類によって免責金額の適用が異なるケースがあるため、契約内容を確認することが重要
車対車免ゼロ特約について
車両保険には「車対車免ゼロ特約」と呼ばれるオプションがあり、車同士の事故で相手が確認できる場合に限り、免責金額をゼロにできるメリットがあります。
シミュレーション例
例:免責金額を「5万円」に設定している契約者が、修理費用30万円の車同士の事故を起こした場合:
・特約なし → 自己負担5万円、保険会社支払い25万円
・特約あり → 自己負担0円、保険会社支払い30万円
このように、特約があることで自己負担をゼロにできるケースがあります。ただし、適用には「保険期間中の最初の事故に限る」「免責金額が一定以下の場合に限る」など制限がある上、特約を付けると保険料が上がるため、費用対効果を見極めることが重要です。
特約を付けるべき人と不要な人
・付けるべき人 → 新車や高額な車両を所有し、事故時の自己負担をできるだけ回避したい方。家計に余裕があり、安心を求めたい方。
・不要な人 → 車両価値が低く、修理費と保険支払のバランスが悪い場合。少額の負担が許容でき、保険料削減を優先する方。
まとめ:免責金額は保険料と安心のバランス
免責金額は、保険料と事故時の安心感の両方に影響する重要な要素です。契約前には家計や車両の価値、利用頻度などを見極めた上で、最適な選択ができるようシミュレーションをしっかり行いましょう。
参考情報
公的情報として、以下の資料も参考になります:
・金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」 — 保険商品の監督方針や審査基準などを掲載しています
・損害保険料率算出機構「統計集」 — 自動車保険の統計や参考純率などをまとめた資料です
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



