資産運用
資産寿命を延ばす!運用資産取り崩しの基本戦略と実践方法
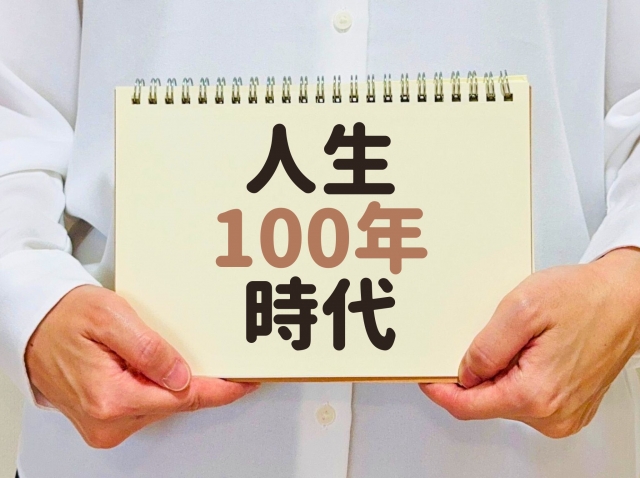
人生100年時代を迎え、老後の資産をいかに長持ちさせるかが重要なテーマとなっています。長寿化が進む現代において、公的年金だけでは生活費をまかなえない場合、自身で形成した運用資産を計画的に取り崩していくことが必要です。本記事では、資産寿命を延ばすための取り崩し戦略について、CFPの視点から詳しく解説します。
運用資産の取り崩しとは何か

運用資産の取り崩しとは、リタイア後に保有している金融資産を生活費として引き出していく行為を指します。金融庁の報告書によれば、夫65歳以上・妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯では毎月の不足額の平均は約5万円とされ、20~30年の人生があるとすれば、不足額の総額は単純計算で1,300万円~2,000万円になると試算されています。
この不足分を補うため、保有する金融資産から計画的に取り崩していく必要があります。取り崩し方法には主に「定額取り崩し」と「定率取り崩し」があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。
定額取り崩しの特徴とメリット・デメリット

定額取り崩しとは
定額取り崩しは、毎月または毎年一定の金額を取り崩していく方法です。例えば「毎月10万円」「毎年120万円」といった形で、固定額を引き出し続けることになります。
定額取り崩しのメリット
・計算がシンプルで分かりやすい
・毎月の収入が一定となり、生活設計が立てやすい
・一定の生活水準を維持しやすい
定額取り崩しのデメリット
・市況の影響を受けやすく、資産寿命が短くなりがち
・相場が下落している時期にも同額を取り崩すため、資産の減少が加速する可能性がある
・収益率の配列リスク(順序リスク)の影響を受けやすい
定額取り崩しでは、市場が下落局面にあっても取り崩す金額は変わりません。そのため、基準価額が安い時期に多くの口数を売却してしまうという問題が発生します。資産残高に余裕がある場合には適していますが、資産を長く維持したい場合には不利な面もあります。
定率取り崩しの特徴とメリット・デメリット

定率取り崩しとは
定率取り崩しは、資産残高に対して一定の割合で取り崩していく方法を指します。例えば「年率4%」と設定した場合、資産残高が3,000万円なら年間120万円、2,000万円なら年間80万円を取り崩すことになります。
定率取り崩しのメリット
・資産寿命を延ばすことができる
・相場が下落した際には取り崩し額も減少するため、資産の過度な減少を防げる
・時間分散の効果により、長期的に資産を維持しやすい
・収益率の配列リスクの影響を受けにくい
定率取り崩しのデメリット
・毎年の取り崩し額が変動するため、生活設計が立てにくい
・相場の状況によって受け取れる金額が大きく変わる
・資産残高の減少に伴い、取り崩し額も減少していく
定率取り崩しの最大の特徴は、資産の時価が下がった時には取り崩し額が減り、時価が上がった時には取り崩し額が増えるという点にあります。これにより、市場の変動に応じて柔軟に対応でき、資産寿命を延ばすことが可能となります。
4%ルールとその考え方

4%ルールの基礎知識
資産取り崩しの分野で広く知られているのが「4%ルール」です。これは1998年にアメリカのトリニティ大学で発表された研究に基づくもので、毎年資産の4%を取り崩していけば、30年以上経過しても資産がなくなる可能性が非常に低いという内容となっています。
4%という数字は、米国株式市場(S&P500)の平均上昇率7%からインフレ率3%を差し引いた実質リターンに基づいて算出されています。年間支出の25倍の資産を築けば、年利4%の定率取り崩しで資産を維持しながら生活できるという考え方です。
4%ルールの2つのパターン
4%ルールには以下の2つの解釈があります。
・定額型:引退時の資産×4%の金額を毎年定額で取り崩す
・定率型:毎年の資産残高×4%を定率で取り崩す
定額型は生活費が安定する一方、定率型は資産寿命が延びやすいという特徴があります。どちらを選択するかは、ライフスタイルやリスク許容度によって判断する必要があります。
日本における4%ルールの適用
4%ルールは米国市場のデータに基づいているため、日本の株式市場では同様の結果が得られない可能性があることに注意が必要です。また、税金や手数料を考慮していないため、実際の取り崩し可能額はやや低くなることも想定されます。
日本のインフレ率は米国より低い傾向にあることから、状況によっては4%よりも高い取り崩し率が可能な場合もありますが、安全性を重視するなら3~3.5%程度の取り崩し率を検討することも一つの選択肢となります。
ハイブリッド戦略の活用

ハイブリッド戦略とは
定額取り崩しと定率取り崩しの長所を組み合わせた方法が「ハイブリッド戦略」です。基本的な生活費は定額で確保しつつ、余裕資金は定率で取り崩すことで、安定性と効率性のバランスを図ります。
ハイブリッド戦略の具体例
・公的年金や不動産収入などの固定収入で基本生活費をカバー
・金融資産は定率取り崩しで運用しながら活用
・必要最低限の生活費は定額取り崩しで確保し、余剰分は定率で運用
前半定率・後半定額という選択肢
もう一つの戦略として、資産が多い老後前半は定率で取り崩し、資産が少なくなった後半は定額に切り替えるという方法もあります。元気で活動的な時期に多めに使い、その後は一定額を確保することで、資産を最後まで使い切ることが可能となります。
資産取り崩しで注意すべきポイント

収益率の配列リスク(順序リスク)
定額取り崩しにおける最大のリスクが「収益率の配列リスク」です。これは、リタイア直後の運用成績によって資産寿命が大きく変わるという現象を指します。リタイア初期に相場が好調であれば資産は長持ちしますが、初期に暴落が発生すると資産が急速に減少する可能性があります。
生活防衛資金の確保
暴落局面に備え、2~5年分の生活費相当の現金を別途確保しておくことが推奨されます。市場が下落している時期には資産を取り崩さず、現金で生活することで、資産の回復を待つことができるためです。
税金と手数料の考慮
実際の取り崩しでは、譲渡益課税や信託報酬などのコストが発生します。手数料の高低は長期投資において資産に大きく影響するため、低コストの商品を選択することが重要となります。
ライフプランに応じた調整
医療費や介護費用など、予期せぬ支出が発生する可能性も考慮しなければなりません。定期的にライフプランを見直し、状況に応じて取り崩し方法や金額を調整していく柔軟性が求められます。
まとめ
運用資産の取り崩しは、老後の生活を支える重要な戦略となります。定額取り崩しは生活の安定性が高く、定率取り崩しは資産寿命を延ばしやすいという特徴があり、それぞれの状況に応じて選択することが大切です。
4%ルールは一つの目安として有用ですが、日本の市場環境や個人の状況によって適切な取り崩し率は異なります。公的年金との組み合わせ、生活防衛資金の確保、税金・手数料への配慮など、総合的な視点で計画を立てることが求められます。
ハイブリッド戦略や前半定率・後半定額といった柔軟な方法も検討しながら、自身のライフスタイルやリスク許容度に合わせた最適な取り崩し戦略を構築していくことが、長寿社会における資産寿命延伸の鍵となるでしょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
金子賢司へのライティング・監修依頼はこちらから。ポートフォリオもご確認ください。



