FPによる貸金業法学習記録
貸金業法における禁止行為等の整理
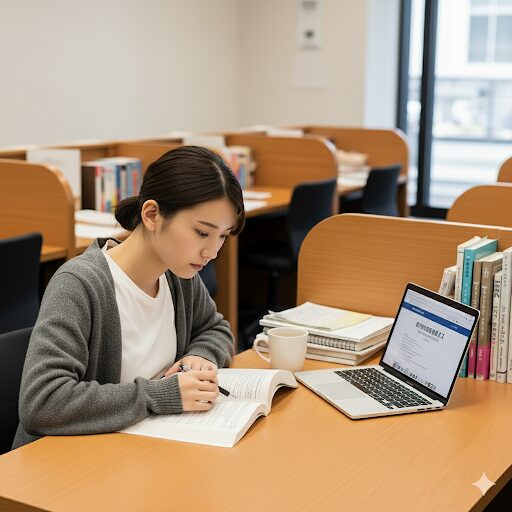
この記事は、CFPが2025年11月16日実施の貸金業務取扱主任者を目指すために、自身の勉強記録として残すブログです。
「※本記事は筆者の学習記録であり、その内容の正確性には万全を期しておりますが、法令改正等により変更される可能性があります。実際の業務や判断においては、必ず最新の法令や専門家の助言を確認してください。
貸金業は、資金需要者等の生活の安定と福祉の向上に寄与するため、その業務の適正な運営を確保することが求められている。そのために、貸金業法(以下、「法」という。)には、貸金業者が行ってはならない行為が明確に規定されている。これらの禁止行為等は、資金需要者等の保護を目的としている。
資金需要者等に対する禁止行為
貸金業者は、資金需要者等(貸付けの相手方または相手方となろうとする者、およびその保証人となろうとする者)に対し、以下の行為をしてはならない。なお、ここでいう「告げる」という行為は、口頭によるものに限らず、文書、電磁的方法等、あらゆる伝達手段を含む。
虚偽告知・重要事項不告知の禁止
・資金需要者等に対し、貸付けの契約について、虚偽のことを告げる行為
・資金需要者等に対し、貸付けの契約について、契約に関する重要な事項を告げない行為
これらの行為は、資金需要者等の誤った判断を誘発する可能性があるため、厳しく禁止されている。虚偽のことを告げた場合は、刑事罰が科される可能性がある。
断定的な判断の提供等の禁止
・資金需要者等に対し、不確実な事項について、断定的な判断を提供する行為
・資金需要者等に対し、不確実な事項について、確実であるかのように誤認させるおそれのあることを告げる行為
この行為は、資金需要者等に将来の不確実な事象について過度な期待を抱かせ、契約締結の判断を誤らせるおそれがあるため禁止されている。ただし、この行為の違反については、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。
保証人に対する誤認行為の禁止
・保証人となる者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であるかのように誤認させる行為
保証人は、主たる債務者が弁済できなくなった場合にその債務を履行する責任を負うため、安易な保証契約の締結を防ぐ目的で禁止されている。この行為に違反すると、貸金業の登録を取り消されるか、または1年以内の期間を定めて、業務の全部または一部の停止を命じられることがある。
不当な行為等の禁止と行政処分・刑事罰
偽り、不正、または著しく不当な行為の禁止
・偽り、その他不正または著しく不当な行為をすること
この行為は、広範な不公正な業務運営を防ぐための包括的な禁止規定である。この行為に違反すると、行政処分の対象となる(刑事罰の対象とはならない)。
・不正な行為とは、違法な行為を指す。
・不当な行為とは、客観的に見て妥当性を欠く、または適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為のことをいう。
【偽り、その他不正または著しく不当な行為に該当するおそれが大きいもの(例)】
・貸金業者が合理的な理由もなく、過大な担保や保証人を徴求すること
・資金需要者等の身体的、精神的障害等で契約内容が理解困難であることを知りながら、契約を締結する行為
・資金需要者等が障害者で、家族や介助者等がいるにもかかわらず、彼らを介して資金需要者等に内容を理解してもらう努力をすることなく、単に障害があることで、貸金業者が契約締結を拒否すること
・確定判決において、消費者契約法第8条から10条までの規定に該当し無効であると評価され、この事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センターまたは、同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と内容が同一である条項を含む貸し付けに関する契約を締結した場合
業務遂行上の禁止行為・義務違反
暴力団員等の業務従事の禁止
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を貸金の業務に従事させたり、補助者として使用させたりすること
この違反は、行政処分だけでなく、刑事罰の対象となる。
従業者証明書の携帯義務違反
・従業者であることを証明する証明書を携帯させることなく、貸金業の業務に従事させること
この違反は、行政処分だけでなく、刑事罰の対象となる。
保証料に関する確認義務
・貸金業者は業として保証を行う者(保証業者)と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ契約を締結するまでに、保証業者と貸し付けにかかる契約の相手方または相手方になろうとする者の間における、保証料にかかる契約の締結の有無と、保証料にかかる契約を締結する場合には、当該保証料の額を確認しなければならない
この義務は、保証料の二重取りなど、資金需要者等に不利益を与えることを防ぐための措置である。



