FPによる貸金業法学習記録
貸金業における法定帳簿・証明書の義務
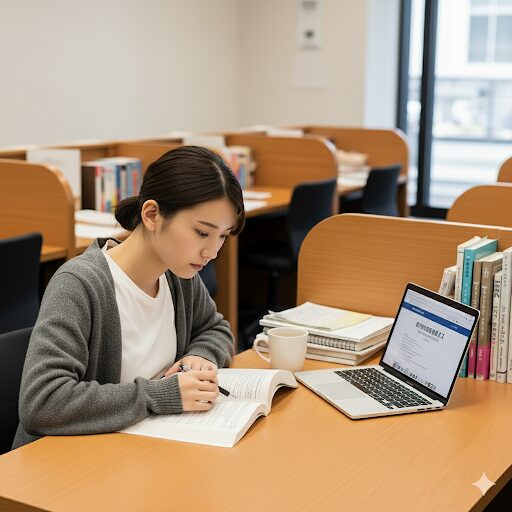
この記事は、CFPが2025年11月16日実施の貸金業務取扱主任者を目指すために、自身の勉強記録として残すブログです。
「※本記事は筆者の学習記録であり、その内容の正確性には万全を期しておりますが、法令改正等により変更される可能性があります。実際の業務や判断においては、必ず最新の法令や専門家の助言を確認してください。
貸金業者の業務遂行に関する法令上の義務
貸金業者が負う業務上の義務は、貸金業法によってその根拠が定められ、詳細な手続きや期間は内閣府令(貸金業法施行規則)に委任されているという構造を持つ。この法的構造を正確に理解し、「法律で定められていること」と「府令で定められていること」を明確に区別する必要がある。
従業者の証明書に関する義務
従業者証明書の携帯義務と提示
貸金業者は、業務に従事する者に対し、従業者証明書を携帯させなければ、業務に従事させることはできない(貸金業法)。
この法律の規定は携帯義務のみを定めているが、実務上、資金需要者等から請求があった場合には、この携帯義務の一環として、証明書を提示する必要がある。
ただし、「勧誘を伴わない広告のみを行う業務や、資金需要者等と対面することなく行う業務」に従事する者については、従業者証明書の携帯は不要とされている。
従業者名簿の備え付けと保存義務
名簿の備え付け・記載義務と保存期間の法的構造
貸金業者は、営業所等ごとに従業者名簿を備え、内閣府令で定めるところにより、記載し、これを保存しなければならない(貸金業法)。
この条文は名簿の備え付けと保存の義務を定めるものであり、具体的な記載事項や保存期間については、貸金業法施行規則に委任されている。法施行規則によって、従業者名簿は最終の記載をした日から10年間保存することが義務づけられている。
従業者名簿の対象となる者
従業者名簿の記載対象となるのは、勧誘や契約の締結を行う営業、審査、債権の管理や回収、およびこれらの付随する事務に従事している者であり、雇用関係・雇用形態を問わない。
人事、総務、経理、システム管理などの業務のみに従事する者は対象とならない。また、「勧誘を伴わない広告のみを行う業務や、資金需要者等と対面することなく行う業務」を行う者も、貸金業務に該当するため、従業者名簿の記載対象となる。
業務に関する帳簿の備え付けと保存義務
業務に関する帳簿の備え付け・保存義務の法的構造
貸金業者は、その営業所等ごとに、その業務に関する帳簿を備え、内閣府令で定めるところにより、記載し、これを保存しなければならない(貸金業法)。
この法律の条文が、帳簿の備え付け、記載、および保存のすべての義務を内閣府令への委任も含めて規定している。
ただし、営業所等が現金自動設備(ATMなど)であるときは、帳簿の備え付けは不要とされる(貸金業法ただし書き)。
帳簿の具体的な保存期間
帳簿の保存期間についても、法律の規定に基づき、貸金業法施行規則で詳細が規定されている。
具体的には、貸付の契約ごとに、最終の返済期日から少なくとも10年間保存が必要である。また、債務が弁済などにより消滅した場合は、債務消滅の日から少なくとも10年間保存する必要がある。



