FPによる貸金業法学習記録
貸金業における内部管理体制の要点
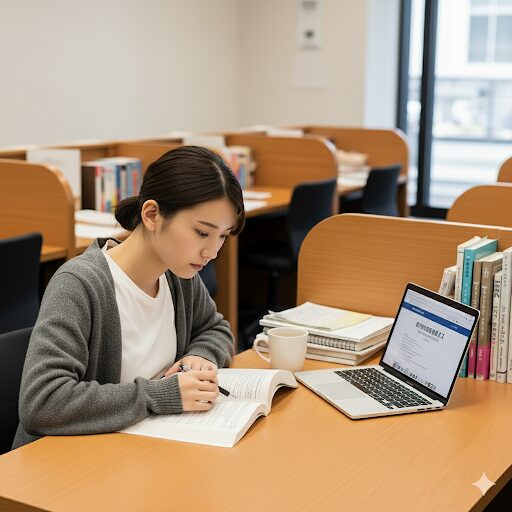
この記事は、CFPが2025年11月16日実施の貸金業務取扱主任者を目指すために、自身の勉強記録として残すブログです。
「※本記事は筆者の学習記録であり、その内容の正確性には万全を期しておりますが、法令改正等により変更される可能性があります。実際の業務や判断においては、必ず最新の法令や専門家の助言を確認してください。
貸金業者が健全な事業運営を行うためには、法令遵守を前提とした厳格な内部管理体制の確立が不可欠である。特に、顧客との間で生じる苦情等への対応と、社内全体の統制を目的とした内部管理体制の整備は、事業の信頼性を維持する上で極めて重要となる。
苦情等対処に関する内部管理態勢の確立
貸金業者は、顧客からの苦情や問い合わせに適切に対応するため、以下の点に留意して内部管理体制を構築する必要がある。
受付窓口の整備と対応の充実
・資金需要者等の利便性を考慮し、電話、メール、ファックス、手紙など多様なアクセス手段と、時間帯に応じた対応体制を整備することが求められる。
・苦情は単なる手続き上の問題として捉えるのではなく、事後的な説明態勢の問題として位置づけ、十分なヒアリングを通じて顧客の事情を理解し、可能な限り顧客の理解と納得を得て解決することを目指す。
情報共有と再発防止策
・重要案件と判断された苦情については、速やかに内部監査部門や経営陣に報告し、関係者間で情報共有を図る態勢を整備することが重要である。ただし、軽微な案件はこの報告対象から除外される場合がある。
・自社で対処したものだけでなく、外部機関が対処した苦情についても、その内容と対処結果を適切かつ正確に記録・保存する必要がある。これらの記録を再発防止策や未然防止策に活用する態勢を整備することが求められる。
内部管理体制の整備
貸金業者は、事業の規模や特性に応じた創意工夫を凝らし、法令や法の趣旨を踏まえて自主的に社内規則等を策定する必要がある。この際、日本貸金業協会が策定する自主規制規則に則った内容が求められる。これは、協会員か非協会員かを問わない共通の着眼点である。
内部管理部門の役割
・内部管理部門は、法令および社内規則を遵守した業務運営を確保するための部署である。
・この部門では、業務運営全般について、法令や社内規則に則った適正な業務遂行がなされているかを適切なモニタリングや検証によって確認する必要がある。
・重大な問題が発覚した場合には、経営陣に対して速やかに報告する体制が不可欠である。
個人の貸金業者等の特例
・貸金業に従事する者が1名のみである場合(個人の貸金業者や役員が一人で代表者となっている法人など)は、業務の適切性を確保するための十分な態勢が求められる。
・具体的には、自身の行う業務について、最低でも月1回以上検証を行うなど、業務の適正を確保するための態勢が整備されているかどうかが着眼点となる。
経営陣の責任
・経営陣は、利益相反が生じる可能性のある業務における内部牽制や、営業店長の権限に応じた監視など、適切な業務運営を確保するためのモニタリング、検証、および改善策の策定等を行う態勢を整備しなければならない。
・これにより、経営陣自らが主体的に事業の健全性を維持していくことが期待される。



