自動車保険
自動車保険の等級制度を徹底解説|仕組み・割引率の目安・等級変動と最新保険料改定情報

ここでは、等級制度の仕組みや割引率、等級が上がる・下がる具体的な条件を分かりやすく解説します。
自動車保険の等級制度とは
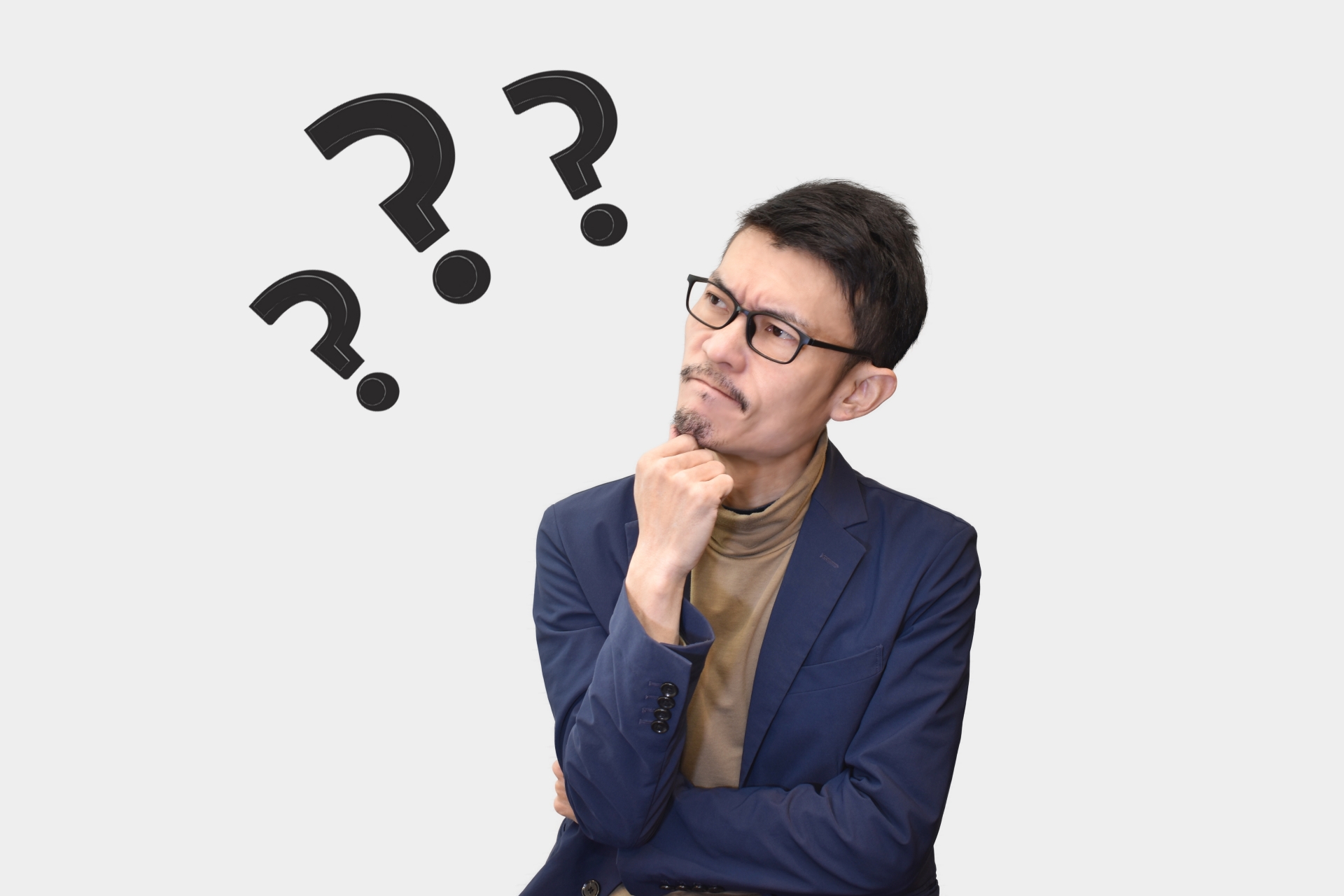
自動車保険の等級制度は、契約者の過去の事故歴に応じて保険料を増減させる仕組みです。ほとんどの損害保険会社で共通して採用されており、一般的には「1等級」から「20等級」まで存在します。初めて加入する場合は通常「6等級」からスタートし、1年間無事故であれば等級が1つ上がり、事故を起こすと等級が下がります。
この制度の目的は、事故リスクの低い契約者には保険料の割引を、リスクの高い契約者には割増を適用することで、公平な保険料負担を実現することにあります。
等級と割引率の関係

等級が高くなるほど割引率が大きくなります。例えば、20等級では割引率が約60%前後になることもあり、長期間無事故でいることが保険料節約の鍵です。一方、1等級や2等級は大きな割増(+60%程度)が適用され、保険料が高額になります。
※割引率や割増率は保険会社や契約条件によって異なります。本記事で示す数値はあくまでも目安であり、実際の適用率は各社の約款・見積もりで必ず確認してください。
割引率は保険会社や契約条件によって若干異なりますが、目安として以下のような傾向があります。
・6等級(新規):割引率約20%
・10等級:割引率約40%
・20等級:割引率約60%
なお、事故を起こして等級が下がった場合は「事故有係数適用期間」が設定され、一定期間は割引率が低く抑えられる点にも注意が必要です。
等級が上がる条件

等級を上げるためには、契約期間中に保険金を請求する事故を起こさないことが基本です。具体的には、次のようなケースでは等級が上がります。
・1年間無事故で経過した場合
・車両入れ替えや契約内容変更だけで事故がない場合
また、契約の更新時には自動的に等級が1つ上がります。無事故を積み重ねることで保険料の負担が年々軽くなるため、安全運転の継続が最も効果的な節約方法です。
等級が下がる条件

等級が下がるのは、保険金を請求する事故を起こした場合です。ただし、全ての事故が同じ影響を与えるわけではありません。
主な等級ダウンのケースは以下の通りです。
・1等級ダウン事故:飛び石や台風被害など、保険会社が特例扱いとする事故
・3等級ダウン事故:人身事故や物損事故など、多くの事故が該当
さらに、1度の事故で複数の保険金請求を行った場合、それぞれがカウントされるため、等級が大きく下がることもあります。
事故有係数適用期間とは

事故を起こすと、等級が下がるだけでなく「事故有係数適用期間」が設けられ、その間は割引率が低く設定されます。この期間は通常3年間で、その間は無事故でも割引率が小さい状態が続きます。つまり、事故による保険料増加は長期的に影響するのです。
事故を起こした場合の保険料増加シミュレーション

ここでは、40歳・年間走行距離10,000km・車両保険付き・12等級・無事故の場合を基準に、3等級ダウン事故を起こしたケースをシミュレーションします。(割引率は損害保険各社の公表データを基に概算)
・【事故前】12等級(割引率約45%)→年間保険料:約7万円
・【事故翌年】9等級(事故有係数・割引率約20%)→年間保険料:約10.5万円
差額は年間約3.5万円の増加。さらに事故有係数適用期間(3年間)が続くため、合計で約10万円以上の追加負担となります。
※このシミュレーションは2024年時点の参考水準であり、2025年1月からの自動車保険料改定(平均3.5%〜5%値上げ予定)や軽自動車の料率クラス変更前の条件に基づいています。実際の金額は最新の料率を必ずご確認ください。
つまり、修理費が10万円程度の軽微な事故であれば、保険を使わず自己負担にした方が総支払いは抑えられる可能性が高いのです。ただし、人身事故や高額修理が必要な場合は、無理に自己負担せず保険を活用することが重要です。
軽微な事故の自己負担ラインの判断基準

事故を起こした際、保険を使うべきか自己負担にすべきかは、修理費用と将来の保険料増加額を比較して判断します。目安として、3等級ダウン事故の場合、事故有係数適用期間3年間での保険料増加額はおよそ10万円〜15万円が一般的です(契約条件や等級によって異なる)。
例えば、以下のケースを考えてみましょう。
・修理見積額:12万円
・3等級ダウンによる保険料増加額:年間3.5万円 × 3年=10.5万円
この場合、修理費が増加額とほぼ同程度のため、将来の等級回復までのトータル負担は変わらないか、むしろ自己負担の方が有利になる可能性があります。
ただし、自己負担を選ぶ際には次の点に注意が必要です。
・人身事故や高額修理(目安としては30万円以上)の場合は、保険利用を優先する
・相手方がいる事故は、賠償リスクや後日のトラブルを避けるため保険を活用
・無理に自己負担を選び、生活資金を圧迫しないこと
また、保険を使わない場合でも事故記録が残るケースがあるため、事前に保険会社に確認することが大切です。
FP視点での等級制度活用アドバイス

等級制度を理解して活用するには、次のポイントが重要です。
・軽微な事故は自己負担とする選択も検討(保険料増加を防ぐ)
・等級の高い契約を引き継ぐ「中断証明書制度」を活用
・複数台契約の場合は事故リスクの低い車を高等級で契約
特に中断証明書は、海外転勤や一時的に車を手放す場合でも最大10年間等級を保持でき、再契約時に高い割引率からスタートできます。
まとめ
自動車保険の等級制度は、長期的な保険料に直結する重要な仕組みです。等級を上げるには無事故を続けることが基本であり、逆に事故を起こすと長期にわたって保険料が増加します。制度を正しく理解し、安全運転を心がけながら、賢く保険料を抑えていきましょう。
なお、2025年1月からの自動車保険料改定や軽自動車の料率クラス変更により、今後の保険料水準は変動が予想されます。契約更新時は必ず最新情報を確認し、複数社の見積もりを比較することをおすすめします。
最新の割引率や等級制度の詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会の公式情報を参考にしてください。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



