外貨建保険
老後資金は円預金だけで大丈夫?インフレ時代の「外貨建て保険」活用術

そこで注目されているのが、外貨で資産を持ちながら保険の保障も受けられる「外貨建て保険」。
この記事では、外貨建て保険の仕組みやメリット・注意点を、初心者にも分かりやすく解説し、どんな人に向いているかを紹介します。
なぜ今、円預金だけでは資産が目減りするリスクがあるのか

日本は長年、物価があまり変わらない「デフレ」の時代が続いてきましたが、近年は状況が変わってきました。総務省統計局の消費者物価指数(CPI)は2023年に前年比で3%台前半の上昇となり、2025年6月時点では+約3.3%に達しています。これは約40年ぶりの高い水準です。
一方、銀行預金の金利は極めて低く、たとえば普通預金の金利は年0.001%程度(日本銀行統計)、事実上「ほぼゼロ」に近い状況です。つまり、預金の利息よりも物価の上昇率の方が圧倒的に高く、お金の実質的な価値は目減りしてしまいます。
さらに為替市場では、2022年以降の円安傾向が続き、2023年には1米ドル=150円台に達する時期もありました(財務省 為替レート統計)。輸入品の価格は上昇し、生活コストが上がる一方で、円の購買力は低下しています。
このような環境下では、円だけで資産を持つことがリスクになる可能性があります。
インフレと円安が老後資金に与える影響

インフレは物価上昇を意味します。例えば、今100万円で購入できる商品やサービスが、物価年2%の上昇が30年続くと、将来必要な金額は約181万円になります。つまり、今の100万円では将来同じ生活水準を維持できないのです。
円安は海外資産の価値を押し上げる一方、円の価値を下げます。海外からの輸入品や原材料の価格は上昇し、日常生活にも影響しますが、逆に外貨資産を持っていれば円安によって評価額が上昇することもあります。
老後資金の一部を外貨で持つことで、この円安リスクを分散できます。
特に外貨建て保険は、保険契約を通じて長期的に外貨資産を積み立てられるため、外貨の価格変動によるリスク分散と保障を同時に得られる手段として注目されています。
外貨建て保険がインフレ対策になる理由

外貨建て保険は、米ドルや豪ドルなどの外貨で保険料を支払い、その通貨で運用・満期受取を行う商品です。外貨で資産を保有するため、円安時には円換算での受取額が増える可能性があります。例えば、1米ドル=120円で契約し、満期時に1米ドル=150円になっていた場合、同じドル建ての満期金でも円換算額は約25%増加します。これは円資産だけを保有している場合には得られない効果です。
さらに、外貨建て保険は保険としての機能も持ち、死亡保障や高度障害保障を付けられるため、単なる外貨投資よりも「保障と運用の両立」が可能です。加えて、保険期間が長期にわたるため、複利効果を活用しやすい点もメリットです。
実際の運用シミュレーション(概算目安)

例として、毎月300米ドルを10年間積み立てた場合の概算です(運用年利2%、複利計算ベース)。
将来価値は約39,800米ドルとなり、円換算額は為替変動により以下のように変化します。
・円高(1ドル=110円):約437万円
・為替変動なし(1ドル=130円):約517万円
・円安(1ドル=150円):約597万円
これはあくまで手数料や保険関係費用を考慮しない概算値であり、実際の契約では為替手数料や運用コストにより受取額が変動します。詳細な条件は契約前に保険会社の試算を必ず確認してください。
外貨建て保険の注意点
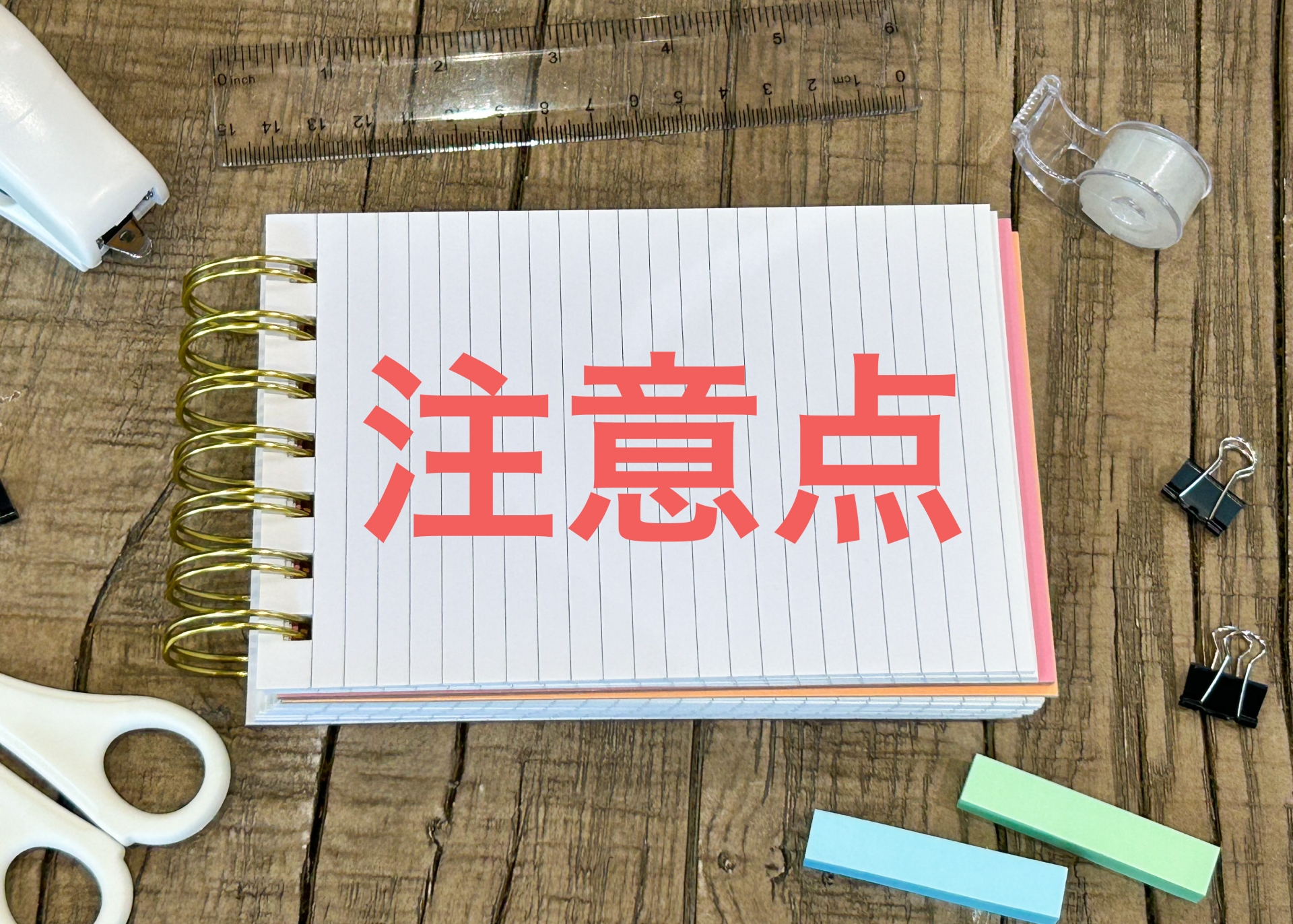
外貨建て保険には以下のような注意点があります。
・為替リスク:円高になると円換算額が減少する可能性
・手数料:為替手数料や保険関係費用、運用費用を含めた総コストは年1%台前半〜中程度となるケースもあるため要確認
・途中解約リスク:契約初期に解約すると元本割れの可能性が高い
・販売資格制度:2022年4月から、外貨建保険の販売には金融庁・生命保険協会の外貨建保険販売資格制度が導入され、十分な説明と顧客の理解が法的に求められるようになっています
加えて、保険は長期契約が前提となるため、3〜5年以内に資金が必要になる可能性が高い人には向きません。また、為替相場や金利環境の変化により、予定利率が下がることもあるため、契約前に最新の条件を必ず確認しましょう。
資産形成の基本は分散投資です。外貨建て保険に全額を投入するのではなく、円資産・株式・投資信託など他の金融商品と組み合わせることで、リスクとリターンのバランスを取りやすくなります。
まとめ:どんな人が外貨建て保険での資産形成に向いているか
外貨建て保険は、次のような人に向いています。
・老後資金を長期的に準備したい人
・円安やインフレによる資産目減りを防ぎたい人
・保険の保障と資産運用を同時に行いたい人
一方で、短期的に解約する可能性がある人や、為替変動に不安を感じる人には不向きです。20代・30代のうちから少額で始めることで、長期の複利効果と外貨資産の分散効果を得やすくなります。外貨建て保険は、あくまで資産形成の一つの選択肢です。預貯金・投資信託・株式などと組み合わせ、リスク分散を心がけながら計画的に老後資金を準備していきましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



