火災保険
火災保険の水災補償は必要?不要?リスクと保険料の考え方

火災保険を検討する際、多くの人が迷うのが水災補償の必要性です。台風や豪雨による洪水、土砂災害などは、家計に大きな損害を与える可能性があります。しかし、すべての地域で水災リスクが高いわけではありません。
そのため、まずはハザードマップで自宅の水災リスクを確認し、さらに2024年から導入された水災等地(1等地〜5等地)による地域別料率を踏まえて判断することが重要です。
この記事では、水災補償が対象とする損害の範囲、必要か不要かの判断基準、支払い条件、そして保険料への影響や最新の制度改定について解説します。
火災保険の「水災補償」が対象とする損害の範囲

水災補償は、台風や集中豪雨などによる洪水・高潮・土砂災害などで住宅や家財が損害を受けた場合に適用されます。主な対象は以下のとおりです。
・河川の氾濫による浸水被害
・台風による高潮や高波による浸水
・土砂崩れや地滑りによる家屋の損壊
・大雨による地盤の崩落や建物の傾き
水災補償の支払い条件(よくある基準)

火災保険の水災補償には、実際に保険金が支払われるための一定条件が設定されています。代表的なものは以下の通りです。
・床上浸水した場合(1階部分の居住スペースまで浸水)
・地盤面から45cm以上の浸水被害を受けた場合
・建物や家財の時価評価額の30%以上に相当する損害を受けた場合
軽微な損害は対象外
これらの条件を満たさない軽微な浸水では支払い対象外となることも多く、契約前に必ず約款を確認することが重要です。
水災補償が「必要な地域」と「不要な地域」の判断方法

水災補償の必要性は、居住地域のリスクに大きく依存します。判断のポイントは以下の通りです。
・河川や海に近い地域は洪水・高潮のリスクが高い
・山間部や斜面地は土砂災害のリスクがある
・都市部でも近年はゲリラ豪雨による内水氾濫が増加傾向
一方で、高台や浸水履歴のない地域では水災リスクは低く、補償を外しても合理的な場合があります。判断の際は、ハザードマップを活用することが重要です。
水害リスクの確認方法

水害リスクを調べるには、自治体の公開情報と国土交通省のハザードマップポータルサイトを利用するのが基本です。特に、ハザードマップで浸水想定区域に該当する場合、2024年導入の水災等地においても高ランクに分類される傾向があります。
つまり、ハザードマップは水災等地の根拠のひとつであり、両者を併せて確認することで、より実態に近いリスク判断が可能になります。
【2024年最新】水災補償の保険料が地域別5段階制に変更

2024年10月より、火災保険の水災補償料率が大きく変わりました。従来は全国一律だった水災保険料が、地域のリスクに応じて5段階に細分化され、最もリスクの高い地域と低い地域では約1.2倍の保険料差が生じるようになりました。
最新の水害被害統計(2021年以降)

2019年の台風19号による約2.15兆円の被害以降も、水害による被害は継続しています。2021年の水害被害額は約3,700億円となり、過去10年間(2013-2022年)の水害被害総額は7兆円以上に達しています。
近年の主な水害被害事例
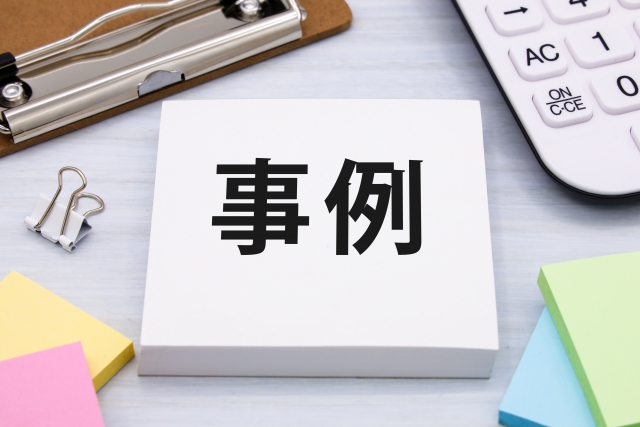
2022年台風15号(静岡県):床上・床下浸水合わせて9,682棟の被害が発生。一時6万戸以上が断水する深刻な被害となりました。
2023年梅雨前線豪雨:6月下旬から7月中旬にかけて線状降水帯が各地で発生。総降水量が1,200mmを超える地域もあり、広範囲にわたって浸水被害が発生しました。
水災補償の加入状況
損害保険料率算出機構の調査によると、火災保険における水災補償の加入率は約65〜69%となっており、約3分の2の世帯が水災補償を付帯していることがわかります。
近年の保険料改定動向
火災保険料は近年頻繁に改定されており、2024年10月の改定では過去最大となる全国平均13%の保険料引き上げが実施されました。これは台風の大型化、集中豪雨の増加など、気候変動による自然災害の激甚化が主な要因です。
自分の地域の水災等地を確認する方法
2024年の制度改革により、お住まいの地域がどの水災等地(1等地〜5等地)に分類されるかで保険料が決まります。損害保険料率算出機構のサイトや各保険会社で確認できるため、見積もり時に必ず確認しましょう。
注意:地震による津波は対象外
火災保険の水災補償は台風や豪雨による水害が対象で、地震による津波や土砂崩れは対象外です。これらは地震保険でカバーされます。火災保険と地震保険をセットで契約することで、幅広いリスクに対応できます。
まとめ:ハザードマップと水災等地で賢く判断
火災保険の水災補償は、洪水や土砂災害など大規模な損害から生活を守る重要な補償です。ただし、地域によって必要性は異なります。
今すぐ実践すべき3ステップ:
1. ハザードマップで自宅の水災リスクを確認
2. 保険会社に自分の地域の水災等地(1〜5等地)を問い合わせ
3. リスクと保険料を比較して水災補償の要否を判断
不要と判断できる地域では補償を外す選択も合理的ですが、災害の発生頻度は年々変化しているため、定期的に見直すことをおすすめします。
よくある質問

Q: マンション住まいでも水災補償は必要?
A: 低層階や地下駐車場がある場合、内水氾濫により浸水リスクがあります。ハザードマップで確認しましょう。
Q: 水災等地はどこで確認できる?
A: 損害保険料率算出機構のサイトや各保険会社で確認可能です。見積もり時に必ず確認を。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



