医療保険
椎間板ヘルニアの手術費用と医療保険|給付金の対象となるケース

椎間板ヘルニアは、腰や足に激しい痛みやしびれを引き起こす病気です。症状が重い場合、手術が必要になることがあります。手術費用は、手術の方法や入院日数によって高額になる可能性があるため、医療保険で備えたいと考える方も多いでしょう。
この記事では、椎間板ヘルニアの手術費用と医療保険の関係を解説します。どのようなケースで給付金の対象となるか、そして医療保険の選び方まで。椎間板ヘルニアの手術に備えるための賢い保険戦略を提案します。
椎間板ヘルニアの手術と医療保険の給付金

椎間板ヘルニアの手術は、内視鏡手術や顕微鏡手術など、様々な方法があります。手術費用は、公的医療保険の対象となります。
公的医療保険の自己負担割合と高額療養費制度
自己負担割合:
・70歳未満:原則3割
・70歳以上:原則2割(現役並み所得者は3割)
・75歳以上:原則1割(現役並み所得者は3割)
高額療養費制度:
ひと月の自己負担額が一定の上限を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。
給付金の対象となるケース
給付金の支払い条件:
医療保険の給付金は、病気やケガで入院・手術をした際に支払われます。
椎間板ヘルニアの手術:
椎間板ヘルニアの手術は、病気の治療目的であるため、医療保険の給付金の対象となります。
医療保険の給付金と、賢い選び方

椎間板ヘルニアの手術に備える医療保険は、以下のポイントを考慮して選びましょう。
入院給付金
入院給付金日額:
入院日数に応じて支払われる給付金です。
入院日数の目安:
・現在の椎間板ヘルニア手術は、低侵襲手術が主流であり、入院期間は大幅に短縮されています。
・内視鏡手術(MED、PED等): 日帰り〜1泊2日
・顕微鏡手術: 2〜5日程度
・従来の開放手術: 1〜2週間
入院一時金:
入院日数に関わらず、まとまったお金を受け取れる「入院一時金」という特約もあります。短期入院の医療費負担をカバーできます。
手術給付金
給付金の計算方法:
手術給付金の金額は、入院給付金日額に、手術の種類に応じた「給付倍率」をかけて計算されます。
給付金の金額:
入院給付金日額の10倍、20倍といった形で設定するのが一般的です。
加入時の告知と注意点
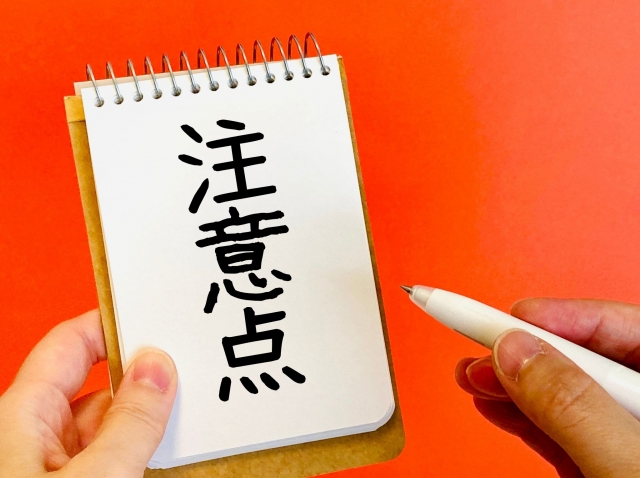
椎間板ヘルニアと診断されている場合、医療保険に加入する際には告知義務を正しく履行することが重要です。
告知義務
告知のポイント:
過去の病歴や現在の健康状態などを正確に告知する義務があります。
告知義務違反のリスク:
告知義務違反が判明した場合、保険契約が解除されたり、給付金が支払われなかったりするリスクがあります。
既往症がある場合の注意点
保険料の割増:
椎間板ヘルニアと診断されている場合、保険会社によっては、保険料が割増されたり、特定の病気や部位を保障の対象外とする「特別条件」を付けて加入できる場合もあります。
引受基準緩和型保険:
一般的な医療保険に加入できない場合、告知項目を少なくした「引受基準緩和型保険」を検討しましょう。
引受基準緩和型保険について、詳しくは以下の記事を参考にしてください。
【徹底解説】引受基準緩和型保険とは?持病があっても入れる保険の選び方
まとめ:椎間板ヘルニアの手術費用に備える
椎間板ヘルニアの手術費用は、医療保険の給付金の対象となります。
・給付金の対象:
椎間板ヘルニアの手術は、医療保険の給付金の対象となりますが、保障内容を事前に確認しておくことが重要です。
・医療保険の選び方:
入院給付金、手術給付金、入院一時金など、複数の給付金を組み合わせることで、万全の備えができます。
・加入時の注意点:
持病がある場合は、告知義務を正しく履行し、引受基準緩和型保険も検討しましょう。
この記事を参考に、椎間板ヘルニアの手術費用に備えるための賢い保険選びをしてください。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



