学資保険
学資保険の特約は必要?加入前に知っておくべき種類と注意点
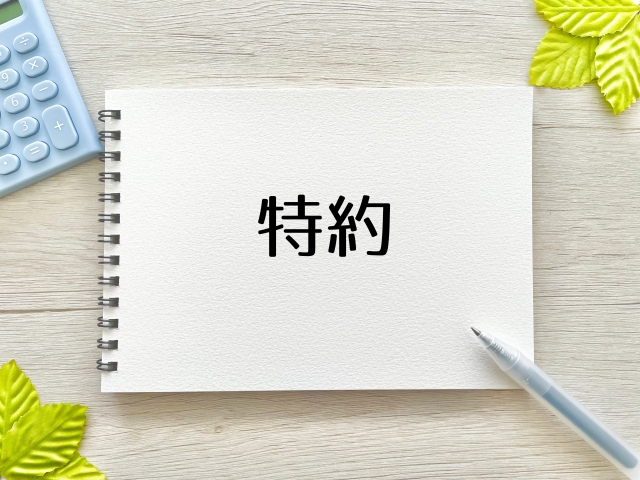
子どもの教育資金を計画的に準備するために学資保険を検討していると、「特約を付けますか?」と聞かれることがあります。特約を付けると保障が増える一方、保険料も上がるため、本当に必要か迷う方は多いでしょう。実際、「特約を付けておけば安心」と安易に判断すると、家計の負担が増え、積立部分が減るケースもあります。
この記事では、学資保険に付けられる代表的な特約の種類と、加入前に押さえておくべき注意点を解説します。
学資保険の特約とは?

学資保険の特約とは、基本契約に追加して付けられるオプション保障のことです。基本契約は「満期保険金」や「祝金」で教育資金を準備するのが目的ですが、特約を付けることで、親や子どもの病気・死亡など万が一の事態にも備えられます。
特約のメリットは、ひとつの契約で保障と貯蓄を同時に確保できる点です。しかし、保険料は上乗せされるため、教育資金を効率よく貯めたい人にとっては負担になる場合もあります。そのため、「何を優先するか」を明確にして選ぶことが大切です。
親の死亡保障特約
親(契約者)が死亡した場合、その後の保険料が免除され、満期時には予定通り保険金が受け取れる特約です。多くの場合、死亡だけでなく高度障害状態になった場合も対象となります。
この特約の利点は、万一の際でも子どもの教育資金計画が途切れないことです。特に一家の収入を支える大黒柱が契約者の場合、保険料免除の仕組みは安心材料になります。
ただし、すでに生命保険や収入保障保険で必要な死亡保障が確保できている場合、重複加入となる可能性があります。加入前に既存の保障額と照らし合わせて検討しましょう。
医療特約
子どもや親の入院・手術に備える特約です。保障範囲は入院日額や手術給付金などが一般的で、病気やケガの医療費をカバーします。
学資保険に医療特約を付けるメリットは、子どもが小さいうちから医療保障を確保できる点です。ただし、医療保険単体で加入するよりも保障内容が限定的なことが多く、保険料の割高感が出るケースもあります。また、子どもの医療費は自治体の医療費助成制度で自己負担が軽減されることも多いため、本当に必要かを見極めることが重要です。
障害保障特約
契約者や子どもが不慮の事故や病気で障害状態になった場合、保険金や年金が支払われる特約です。特に契約者が障害で働けなくなった際の生活費や教育費の補填として役立ちます。
一方で、障害基準は保険会社によって異なり、支払い対象となる範囲が限定される場合もあります。公的な障害年金制度や労災保険などと重複する可能性があるため、制度とのバランスを確認することが大切です。
特約を付けるときの注意点
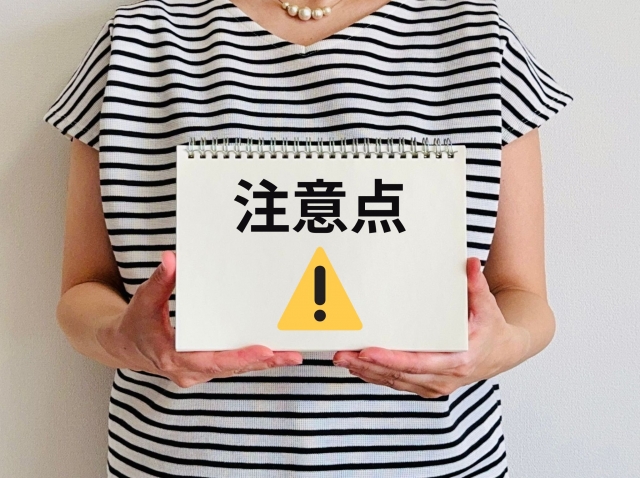
・特約を付けると保険料が上がり、満期金額が減る場合がある
・すでに加入している生命保険や医療保険と保障が重複しないか確認する
・公的保障制度(遺族年金、障害年金、医療費助成など)も踏まえて検討する
・長期契約のため、将来の家計変動も考慮して保険料負担を見積もる
公的制度と特約の比較

特約を検討する際には、まず公的制度でどの程度カバーできるかを知っておくことが重要です。
例えば、親の死亡保障特約と似た役割を果たす制度に「遺族基礎年金」があります。18歳までの子がいる世帯であれば、年間およそ100万円以上(子の人数によって加算あり)が受け取れます。加えて、厚生年金加入者なら「遺族厚生年金」も上乗せされます。このため、世帯の必要保障額が公的制度である程度賄えるなら、特約を最小限にする選択も可能です。
医療特約の場合、子どもは自治体の医療費助成制度により、入院・通院の自己負担がゼロ〜数百円に抑えられる地域が多くあります。親についても高額療養費制度により、医療費が一定額以上になれば自己負担が軽減されます。これらを踏まえると、医療特約の必要性は限定的になることもあります。
障害保障特約は、公的な障害年金や労災保険などと内容が重複する場合があります。障害年金は等級に応じて月額数万円〜十数万円が支給されるため、生活費の一部は確保可能です。特約で上乗せが必要かは、現在の生活費と将来の支出見込みから判断すると良いでしょう。
特約による満期金減少シミュレーション

・基本契約:月額保険料 10,000円
・契約期間:18年(子どもが0歳から18歳まで)
・満期保険金:200万円
・特約追加:月額 2,000円(親の死亡保障・医療・障害保障をセット)
【結果】
特約なし:総支払保険料 216万円 → 満期金 200万円(返戻率 約92.6%)
特約あり:総支払保険料 259.2万円 → 満期金 200万円(返戻率 約77.2%)
特約を付けると保険料が約43万円増える一方で、満期金は変わらないため返戻率が大きく低下します。公的制度で一定の保障を確保できるなら、教育資金の積立効率を優先する方が有利になる場合があります。
まとめ
学資保険の特約は、万一の事態に備える安心材料になりますが、保険料負担や積立効率への影響もあります。公的制度で保障できる部分を把握したうえで、本当に必要な部分だけを特約でカバーすることが、家計と教育資金計画の両立につながります。
参考文献
・金融庁「公的保険について(民間保険の検討にあたって)」
https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance_leaflet.pdf
・厚生労働省「医療保険(国民皆保険制度)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/index.html
・日本年金機構「遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)」制度について
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



