公的年金制度
学生時代の年金を追納すべきかどうか?判断基準とメリット・デメリットを徹底解説

学生納付特例制度と追納制度の基本

まずは、学生納付特例制度と追納制度の仕組みについて正しく理解することが重要です。それぞれの制度の概要を見ていきましょう。
学生納付特例制度とは
学生納付特例制度は、大学や専門学校などに在学する学生で、本人の前年所得が一定基準以下の場合に国民年金保険料の納付が猶予される制度となっています。この制度を利用することで、学生期間中の経済的負担を軽減することが可能です。
令和7年度の国民年金保険料は月額17,510円であり、学生にとって決して小さな負担ではありません。そのため、多くの学生がこの特例制度を利用しています。
出典:国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構
追納制度の概要
追納制度は、学生納付特例などで保険料の納付を猶予された期間について、10年以内であれば後から保険料を納付できる制度です。追納することで、将来受け取る老齢基礎年金の額を増やすことができます。
学生納付特例の承認を受けた期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、追納しなければ年金額には反映されない点が重要です。つまり、年金を受け取る権利は確保できるものの、受給額が減額されてしまうことになります。
出典:国民年金保険料の追納制度|日本年金機構
追納すべき3つの主なメリット

追納を検討する際には、まずそのメリットを理解することが大切です。追納には主に3つの大きなメリットがあります。
将来の年金受給額を増やせる
追納する最大のメリットは、将来受け取る老齢基礎年金の額を増やせる点にあります。令和7年度の老齢基礎年金の満額は年額831,700円(昭和31年4月2日以後生まれの場合)です。
学生納付特例を2年間利用した場合、追納しなければ将来の年金額は年間約4万円程度減額されることになります。老齢基礎年金は生涯にわたって受給できるため、長期的に見ると大きな差となります。
例えば、65歳から85歳までの20年間で計算すると、追納しなかった場合は約83万円の損失となる計算です。
出典:老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構
社会保険料控除による節税効果
追納した国民年金保険料は、その全額が社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税の負担を軽減できます。
例えば、2年分の保険料(約40万円)を追納した場合、課税所得が200万円の方であれば、所得税率10%と住民税率10%を合わせて約8万円の税負担が軽減されます。実質的な追納額は約32万円となり、負担が大幅に軽減される計算です。
この社会保険料控除を受けるためには、年末調整または確定申告の際に、日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付する必要があります。
出典:No.1130 社会保険料控除|国税庁
追納期限が10年以内という明確な期限
追納できる期間は承認された月の前10年以内に限定されています。この期限を過ぎると、たとえ追納を希望しても保険料を納めることができなくなります。
10年という期間は意外と短く、社会人として働き始めてから「いずれ追納しよう」と考えているうちに、あっという間に期限を迎えてしまうケースが少なくありません。実際、厚生労働省の調査によれば、学生納付特例における追納率は8.9%にとどまっており、多くの方が追納の機会を逃している現状があります。
出典:第22回社会保障審議会年金部会|厚生労働省
追納のデメリットと注意点

メリットがある一方で、追納にはデメリットや注意すべき点も存在します。追納を判断する際には、これらの点も十分に考慮する必要があります。
追納には相応の費用負担が必要
学生納付特例を2年間(24カ月)利用した場合、追納には令和7年度の保険料で計算すると約42万円の費用が必要となります。社会人になったばかりの時期に、この金額を一括で支払うことは容易ではありません。
ただし、追納は1カ月分から分割して納付することも可能です。経済的に余裕ができた時点から、少しずつ追納していく方法も検討できます。
3年度目以降は加算額が発生する
学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合は加算額が上乗せされます。加算額は経過した期間に応じて増加し、当時の保険料に対して計算されます。
加算額を抑えるためには、できるだけ早期に追納することが重要となります。とはいえ、加算額が発生しても追納するメリットは十分にあります。将来受け取る年金額の増加と比較すれば、加算額は相対的に小さな負担といえるでしょう。
出典:国民年金保険料の追納制度|日本年金機構
追納は義務ではない
追納は任意の制度であり、法的な義務はありません。追納しなくても罰則などは一切ありません。ただし、追納しない場合は将来の年金額が減額されることを理解しておく必要があります。
現在の家計状況や将来のライフプランを総合的に考慮して、追納するかどうかを判断することが大切です。
追納すべき人の特徴

追納のメリット・デメリットを踏まえた上で、どのような人が追納すべきなのでしょうか。追納に向いている人の特徴を見ていきましょう。
経済的に余裕がある方
社会人として安定した収入を得ており、追納による一時的な費用負担が家計を圧迫しない方は、積極的に追納を検討すべきです。早期に追納すれば加算額も抑えられ、節税効果も得られます。
将来の年金受給額を重視する方
老後の生活において公的年金を重要な収入源と位置付けている方にとって、追納は有効な選択肢となります。特に、自営業やフリーランスなど、厚生年金に加入していない方は、老齢基礎年金が老後の主要な年金となるため、追納による年金額の増加は大きな意味を持ちます。
健康で長生きする見込みがある方
年金は生涯にわたって受給できる制度であるため、長生きすればするほど追納のメリットは大きくなります。約10年で追納した費用を回収できる計算となるため、65歳から受給を開始した場合、75歳以降は追納した分がプラスに転じます。
追納を慎重に検討すべき人

一方で、現在の状況によっては追納を慎重に検討すべきケースもあります。以下のような方は、追納以外の選択肢も含めて検討することをおすすめします。
現在の生活に余裕がない方
追納によって現在の家計が圧迫される場合は、無理に追納する必要はありません。住宅ローンの返済や子どもの教育費など、他に優先すべき支出がある場合は、そちらを優先するのも賢明な判断です。
他の投資や資産形成を優先したい方
追納する費用を、つみたてNISAやiDeCoなど他の資産形成に回したいと考える方もいます。ただし、公的年金には物価スライド制度があり、インフレに強いという特徴があることも考慮に入れる必要があります。
追納の手続き方法
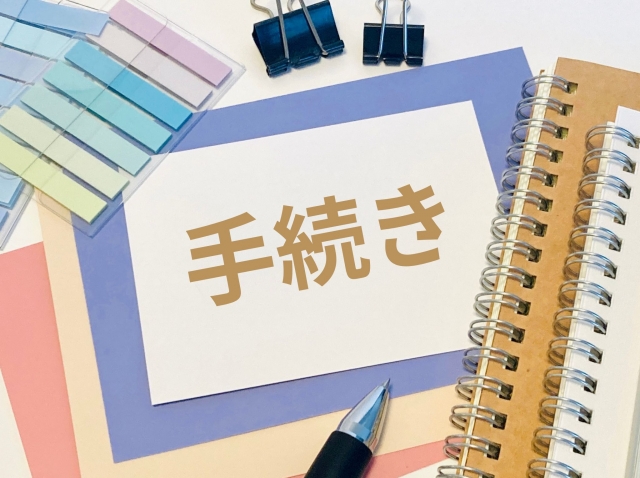
追納すると決めた場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。申込みの手順と追納の順序について説明します。
申込みの手順
追納を希望する場合は、以下の手順で手続きを行います。
・最寄りの年金事務所または市区町村の国民年金窓口で「国民年金保険料追納申込書」を入手(日本年金機構のホームページからダウンロードも可能)
・申込書に必要事項を記入し、年金事務所に提出(郵送も可能)
・承認されると、日本年金機構から納付書が送付される
・納付書を使って、金融機関やコンビニエンスストアで保険料を納付
出典:国民年金保険料の追納制度|日本年金機構
追納の順序
複数年度にわたって学生納付特例を受けていた場合、原則として古い期間から順に納付することになります。これは、古い期間ほど10年の期限が早く到来するためです。
追納しなかった場合の選択肢
60歳以降の任意加入制度
追納の期限(10年)を過ぎてしまった方や、現時点で追納する余裕がない方には、60歳以降の任意加入制度という選択肢があります。
任意加入制度は、60歳以上65歳未満の方で、20歳から60歳までの保険料納付済期間が480カ月(40年)未満の場合に利用できる制度です。この制度を利用すれば、60歳以降も国民年金に加入して保険料を納付し、年金額を増やすことができます。
任意加入のメリットは、追納と異なり加算額が発生しない点にあります。ただし、60歳時点での保険料を支払うことになるため、保険料額自体は追納時より高くなる可能性があります。
出典:任意加入制度|日本年金機構
追納と任意加入の比較
追納は10年以内という期限がある一方、社会保険料控除による節税効果を即座に得られる点がメリットです。また、若い時期に納付することで、その後の人生における年金額増加のメリットを長く享受できます。
任意加入は60歳以降の選択肢となるため時期が限定されますが、加算額が発生しない点と、追納の期限を過ぎた方でも年金額を増やせる点がメリットとなります。
まとめ:追納の判断は総合的な視点で
学生時代の年金を追納すべきかどうかは、個々の経済状況やライフプランによって異なります。以下のポイントを押さえて判断することが重要です。
・追納のメリット:将来の年金額増加、社会保険料控除による節税効果、10年以内という明確な期限
・追納のデメリット:相応の費用負担、3年度目以降の加算額
・追納すべき人:経済的余裕がある、将来の年金を重視する、健康で長生きする見込みがある
・追納の代替案:60歳以降の任意加入制度も選択肢として存在する
追納は義務ではなく、将来の年金額を増やすための選択肢の一つです。現在の家計状況を無理なく維持しながら、将来の安心を確保するために、ご自身の状況に合わせて最適な判断を行うことをおすすめします。
迷った場合は、最寄りの年金事務所や年金相談センターで相談することも可能です。専門家のアドバイスを受けながら、納得のいく選択をしていただければと思います。
出典:日本年金機構
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
金子賢司へのライティング・監修依頼はこちらから。ポートフォリオもご確認ください。



