火災保険
地震保険は火災保険とセットで必要?加入率と仕組みを徹底解説

地震保険は火災保険に付帯して契約する保険で、単独加入はできません。この記事では、火災保険だけでは補償できない理由に加え、制度の限度額・支払区分・割引・税制優遇・再保険制度などを整理し、地域差がある加入率の現状や必要性の判断基準を解説します。
地震保険の仕組みと火災保険だけではカバーできない理由

地震保険は火災保険に付帯する形でのみ契約できます。対象となるのは地震・噴火・津波が原因で生じた建物や家財の火災・損壊・埋没・流失などです。
一方、火災保険は火事や落雷などを補償しますが、地震が原因で起きた火災や倒壊は対象外です。そのため、火災保険とセットで加入しなければ、地震由来の損害には備えられません。制度の基本は財務省の「地震保険制度の概要」に整理されています:財務省
地震保険の加入率はどのくらい?現状と地域差を解説

損害保険料率算出機構の発表によると、2023年度の地震保険付帯率は69.7%で、前年度の69.4%から0.3ポイント上昇しました。2003年度以降21年連続で増加し、統計開始以来の最高水準です。
なお、この付帯率は「火災保険に地震保険を付帯した割合」であり、JA共済などの共済契約は含まれていません。そのため、実際の世帯レベルでの加入状況とは数値が異なる可能性があります。
地域別の詳細データ
地震保険の付帯率には地域差があります。例えば、2023年度の付帯率上位は以下のとおりです。
・宮城県:89.4%
・高知県:87.2%
・熊本県:86.2%
これらはいずれも大地震や津波のリスクが高い地域で、過去の被災経験や将来予測が加入意識を高めていると考えられます。
地震保険の必要性が高いケースと判断基準
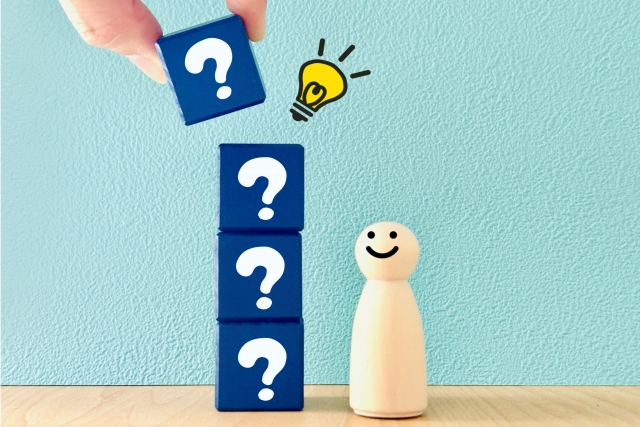
地震保険が特に必要とされるのは、以下のようなケースです。
・活断層が多く、大地震の発生が想定される地域に居住している場合
・住宅ローンが残っており、全損時に返済が大きな負担となる場合
・旧耐震基準の木造住宅など耐震性が低い建物に住んでいる場合
・沿岸部や埋立地など、津波や液状化のリスクが高い地域に住んでいる場合
判断の目安は、「住宅再建に必要な費用」と「自己資金・公的支援でカバーできる金額」の差です。この差が大きい家庭ほど、地震保険の必要性は高まります。
地震保険の制度で押さえるべき重要ポイント

制度の特徴を理解しておくことで、誤解や過不足のない備えが可能となります。
・保険金額の制限:火災保険の保険金額の30〜50%の範囲で設定。上限は建物5,000万円、家財1,000万円
・保険金の支払い方法:損害の程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分で判定し、それぞれ100%/60%/30%/5%を支払い
・支払いスピード:修理費の見積もり精算ではなく定額支払い方式のため、比較的早期に保険金が受け取れる利点あり
・再保険制度:大規模災害に備え、政府が民間保険会社の責任を再保険で引き受ける仕組みを持つ公共性の高い制度
・地震保険料控除:支払った保険料は所得控除の対象。所得税で最大5万円、住民税で最大2万5千円を控除可能
・割引制度:建築年割引・耐震等級割引・免震建築物割引・耐震診断割引の4種類。条件により10〜50%の割引
・補償対象外:工場・事務所専用建物、30万円超の貴金属や美術品、自動車などは対象外
まとめ:地震保険で地震・津波・噴火による損害に備える
火災保険だけでは地震由来の損害を補償できません。付帯率69.7%(2023年度)と過去最高水準を記録する中で、地震保険は多くの家庭で重要な備えとなっています。制度の限度額や支払区分、税制優遇、割引制度、さらに政府の再保険制度と支払スピードの特徴も踏まえ、自分の住まいや家計に合った選択を検討することが大切です。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



