医療保険
仕事中のぎっくり腰、保険は使える?医療保険・傷害保険の対象と注意点

突然の激痛に襲われるぎっくり腰は、誰にでも起こりうる身近な症状です。病院での治療費や、仕事を休んだ間の収入減など、金銭的な不安を感じる方も多いでしょう。特に、「入院や手術を伴わないぎっくり腰」の場合、医療保険で給付金がもらえるのかどうか、疑問に思う方も少なくありません。
この記事では、仕事中にぎっくり腰になった場合に、医療保険や傷害保険が給付金の対象となるかを解説します。また、労災保険の可能性や、医師の診断結果による判断の違いまで。ぎっくり腰になった際に慌てないための、賢い保険の備え方を紹介します。
ぎっくり腰の治療費と医療保険の保障範囲
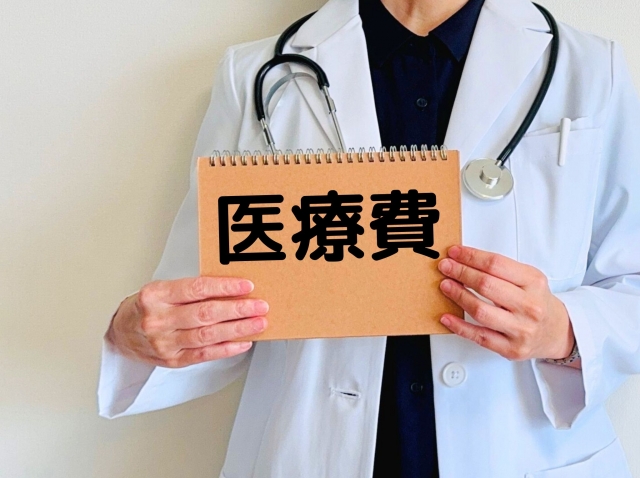
ぎっくり腰の治療は、安静期間を経て、通院での治療や投薬が中心となります。医療保険で保障されるのは、主に「入院」と「手術」が前提です。
公的医療保険と医療費の自己負担
公的医療保険:
ぎっくり腰の治療費は、公的医療保険の対象です。自己負担は原則3割に抑えられます。
高額療養費制度:
ひと月の自己負担額が一定の上限を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。
入院・手術を伴わないぎっくり腰は給付対象外
入院給付金:
入院給付金は、入院日数に応じて支払われる給付金です。ぎっくり腰で入院を伴わない場合は、給付対象になりません。
手術給付金:
手術給付金は、手術を受けた場合にまとまった給付金が支払われるものです。ぎっくり腰で手術をしない限り、給付対象になりません。
就業不能保険:
就業不能保険は、病気やケガで長期間、全く仕事ができない状態が続いた場合に給付金が支払われます。ぎっくり腰は一般的に数日から数週間で回復するため、長期就業不能の条件(通常60日以上など)を満たさず、給付対象となるのは難しいでしょう。
ぎっくり腰は傷害保険の対象になる?

ぎっくり腰は一般的に「ケガ」ではなく「病気」と診断されるため、傷害保険の給付対象外となるケースが多いです。
傷害保険の保障範囲
保障の前提:
傷害保険は、急激かつ偶然な外来の事故によるケガを保障します。ぎっくり腰は、日常的な動作で発症することが多いため、この「事故」とみなされないことが一般的です。
約款の規定:
多くの傷害保険の約款には、「むち打ち症、ぎっくり腰などの症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの」は給付金の対象外であると記載されています。
仕事中のぎっくり腰は「労災保険」の可能性も

仕事中にぎっくり腰になった場合でも、労災認定は厳しいのが現状です。
労災保険の認定条件
仕事との因果関係:
労災認定を受けるためには、ぎっくり腰が仕事との因果関係が明確である必要があります。
労災認定が難しい理由:
・ぎっくり腰は、日常生活で突然発症することが多いため、仕事との因果関係を証明することが難しいです。
・例えば、継続的に無理な体勢での作業が蓄積された結果である場合や、突発的な事故が原因である場合など、条件は厳しいです。
勤務先への相談:
労災認定の可能性について、まずは勤務先の総務など担当部署へ相談しましょう。
ぎっくり腰になった際の初期対応
ぎっくり腰になった際の初期対応を正しく行うことが、保険金請求をスムーズに進める上で重要です。
医師の診断を受ける:
まずは、整形外科などで医師の診断を受けましょう。医学的他覚所見を診断書に記載してもらうことで、傷害保険や労災保険の請求時に役立つ可能性があります。
診断書を保管する:
診断書は、保険金請求に不可欠な書類です。大切に保管しておきましょう。診断書が不要なケースもあるため、事前に保険会社に確認しておくことをおすすめします。
診断書については、以下の記事を参考にしてください。
医療保険の診断書は必要?診断書の費用と請求方法
保険会社に事前確認:
給付金請求を検討している場合は、事前にご加入中の保険会社に問い合わせて、給付対象になるか確認しましょう。
まとめ:ぎっくり腰の備えは「多角的な視点」が大切
ぎっくり腰になった際、医療保険だけで備えが十分とは言えません。
・医療保険: 入院や手術を伴わない場合は、給付対象外となるケースが多いです。
・傷害保険: ぎっくり腰は一般的に「病気」とみなされるため、給付対象外となるケースがほとんどです。
・労災保険: 仕事中のぎっくり腰は、労災認定される可能性もゼロではありませんが、条件は厳しいです。
この記事を参考に、ぎっくり腰になった際に慌てないよう、ご自身の保険の保障内容を事前に確認しておくことをお勧めします。ご加入中の保険会社に直接問い合わせることで、より明確な回答を得られるでしょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



