自動車保険
人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いと併用メリットを徹底解説|選び方とシミュレーション付き

自動車保険に加入する際、「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」のどちらを優先すべきか、あるいは併用するべきか迷う方は多いのではないでしょうか。補償内容が似ているように見えても、実は仕組みや支払条件が大きく異なります。この記事では、両者の違いを整理しつつ、併用することで得られるメリットと注意点、さらにライフスタイルや利用シーンごとの具体的な選び方を解説します。自分や家族に最適な保険プランを見極める判断材料としてご活用ください。
人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いを整理

人身傷害保険の特徴
・実際にかかった治療費や休業損害、逸失利益などを「実損額」で補償
・過失割合にかかわらず補償される
・生活再建や高額な治療費に強い
搭乗者傷害保険の特徴
・事故で死傷した場合に、あらかじめ決められた金額を「定額」で補償
・入通院は「日数払い型」と「部位・症状別払い型」があり、保険会社ごとに異なる
・「事故日から180日以内に治療が必要」など、支払条件がある
・小さなケガや短期入院に役立つ
人身傷害と搭乗者傷害を併用するメリット
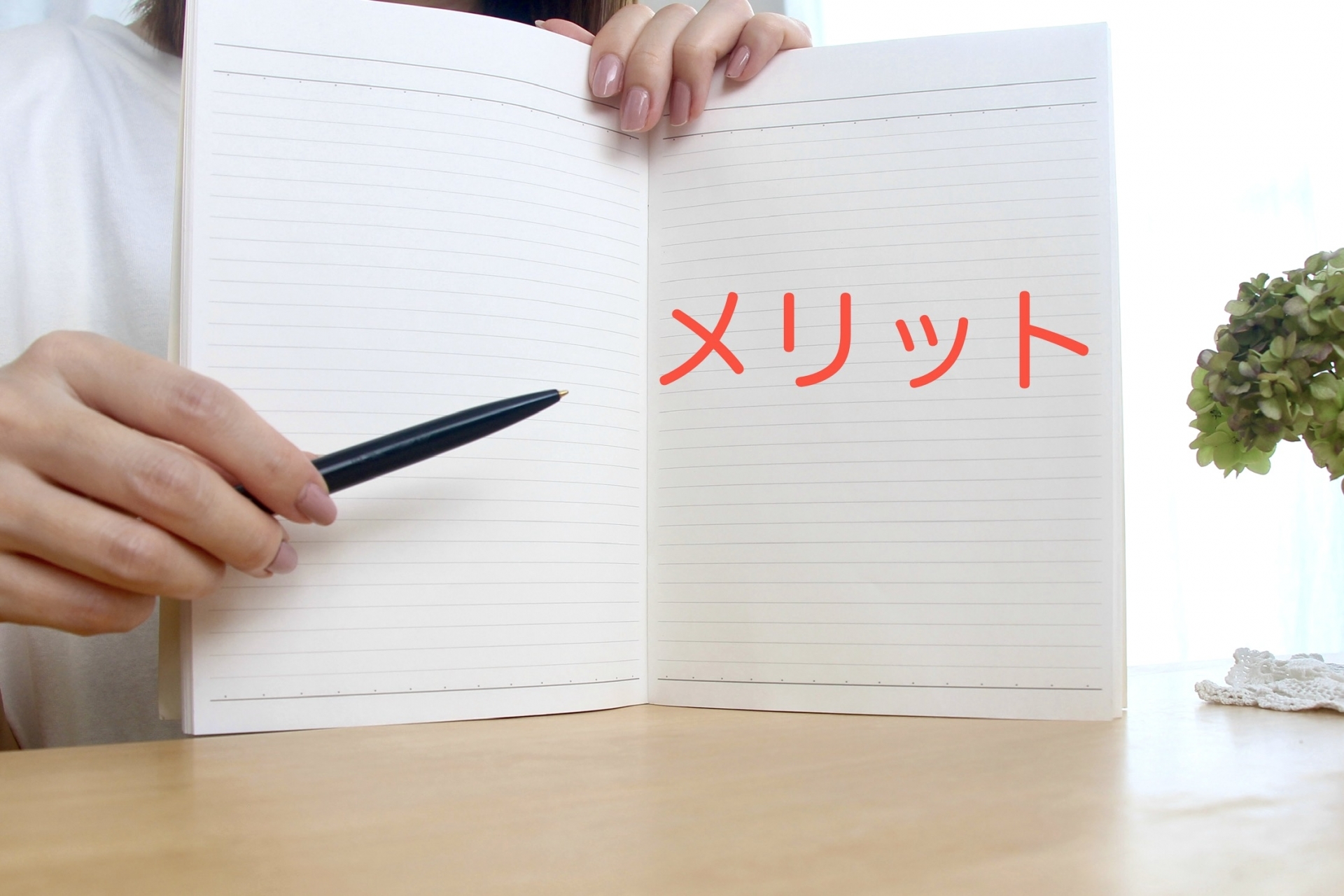
小さなケガでも迅速に補償を受けられる
人身傷害は実損額ベースのため、領収書や証明が必要ですが、搭乗者傷害なら定額でスムーズに支払われます。軽傷でもすぐに補填が可能です。
実損補償と定額補償を組み合わせて手厚くカバー
人身傷害で大きな損害をカバーし、搭乗者傷害で追加給付を受けることで、想定外の出費や差額負担を抑えることができます。
同乗者への補償を強化できる
家族や友人を同乗させる機会が多い場合、搭乗者傷害をプラスすれば補償が厚くなり安心感が増します。
シミュレーション:併用した場合の違い

具体的に金額例で比較してみましょう。
ケース1:交通事故で骨折し、30日間入院+20日間通院した場合
人身傷害保険のみ
・実際の治療費:150万円
・休業損害(30日間):30万円
→ 合計 約180万円が補償される
人身傷害+搭乗者傷害を併用(日額5,000円、部位別給付あり)
・人身傷害から 約180万円
・搭乗者傷害(入院30日×5,000円=15万円、通院20日×3,000円=6万円、骨折一時金10万円)
→ 合計 約211万円が補償される
ケース2:交通事故で死亡した場合(契約者本人、40歳、年収500万円)
人身傷害保険のみ
・逸失利益(将来得られたはずの収入):約5,000万円
・葬儀費用など:200万円
→ 合計 約5,200万円が補償される
人身傷害+搭乗者傷害を併用(死亡保険金1,000万円)
・人身傷害から 約5,200万円
・搭乗者傷害から 定額1,000万円
→ 合計 約6,200万円が補償される
ケース3:交通事故で後遺障害が残った場合(下半身に後遺障害、労働能力喪失率50%)
人身傷害保険のみ
・逸失利益(労働能力50%喪失、40歳、年収500万円、67歳まで就労想定):約6,000万円
・治療費や介護費用:約500万円
→ 合計 約6,500万円が補償される
人身傷害+搭乗者傷害を併用(後遺障害給付 500万円)
・人身傷害から 約6,500万円
・搭乗者傷害から 定額500万円
→ 合計 約7,000万円が補償される
後遺障害の場合、人身傷害で長期的な生活費を補えますが、搭乗者傷害からの定額給付が追加されることで、住居改修や介護サービス導入などに充てられる余裕資金を確保できます。
どちらを優先すべきか?

基本的には「人身傷害保険」を優先すべきです。実損額を幅広く補償できるため、生活再建の基盤になります。そのうえで、短期的な現金給付や軽傷の補填を重視するなら「搭乗者傷害保険」を追加する形が有効です。
搭乗者傷害保険と人身傷害保険の選び方:具体的なケースごとに解説

次に、実際にどのような人がどちらを選ぶべきか、具体例で整理します。
ケース1:生活費や治療費の不安が大きい家庭
事故後の生活費や長期治療が必要になる可能性を考えると、人身傷害保険を優先すべきです。高額な入院費や収入減少に対応できるからです。
ケース2:自営業やフリーランスで収入が不安定な人
事故後すぐに収入が途絶えるリスクがあるため、搭乗者傷害保険を併用して「早期の現金給付」を確保すると安心です。
ケース3:家族や友人をよく同乗させる人
人身傷害でカバーできても、同乗者に迅速な補償を届けたいなら搭乗者傷害をプラスするのが有効です。
ケース4:保険料をなるべく抑えたい人
最低限の安心を得たい場合は人身傷害のみでも十分。ただし小さなケガへの補償は弱いため、その点を理解したうえで選びましょう。
まとめ:人身傷害を基本に、ライフスタイルに応じて搭乗者傷害を追加
人身傷害保険は生活再建の柱となる重要な補償であり、基本的にこちらを優先するのが安心です。そのうえで、収入面の不安や同乗者への配慮が必要な場合には、搭乗者傷害を組み合わせることでより安心感が高まります。シミュレーションで見たように、併用すれば小さなケガから後遺障害、死亡事故まで幅広く補償が厚くなり、日常生活の不安を和らげる効果があります。自分や家族の状況を踏まえて、最適な組み合わせを検討しましょう。
参考情報
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



