家計管理
サブスクで損する人得する人の違いとは?家計を圧迫しないための見極めポイント

動画配信や音楽配信をはじめ、生活のあらゆる場面で利用されるようになったサブスクリプションサービス。月額定額で利用できる手軽さから市場は拡大を続けていますが、その一方で国民生活センターには毎月500件以上の相談が寄せられています。利用頻度が低いまま支払いを続けてしまうケースや、解約し忘れによる無駄な出費など、サブスクで損をしている人は少なくありません。本記事では、公的機関のデータを基に、サブスクで損する人と得する人の違いを明確にし、家計管理の観点から賢い利用方法を解説します。
サブスクリプション市場の現状と利用実態

まずは、サブスクリプション市場がどのように拡大しているのか、そして実際の利用状況について公的機関のデータから見ていきましょう。
拡大を続けるサブスク市場
サブスクリプションサービスとは、月額料金などの定額を支払うことで、契約期間中に商品やサービスを利用できる仕組みを指します。消費者庁が2019年に実施した調査では、動画配信や音楽配信などのデジタルコンテンツを中心に、サブスクリプション市場は着実な成長を続けていることが明らかになりました。
市場を牽引しているのは、動画配信や音楽配信、電子書籍などのデジタルコンテンツ分野です。近年では家具・家電、ファッション、飲食サービスなど、生活に密着した分野にも広がりを見せています。
主要なサブスクサービスの利用状況
消費者庁が実施した調査では、サブスクリプションサービスの利用実態が明らかになりました。利用率が高いサービスの上位は以下の通りです。
・動画配信サービス
・音楽配信サービス
・電子書籍・マンガ配信サービス
・ゲーム
・オンラインストレージ
デジタルコンテンツが大半を占める一方で、飲食やファッション、自動車などの非デジタルコンテンツのサービス利用率は5%未満と低い水準にとどまっています。ただし「今後利用してみたい」と考える人は多く、潜在的なニーズが存在していることがわかります。
サブスクで損する人の特徴

サブスクリプションサービスで損をしてしまう人には、いくつかの共通した特徴が見られます。家計を圧迫する原因となっているポイントを理解することが重要です。
利用頻度が低いまま契約を継続している
消費者庁の調査によれば、サブスクサービスに不満を持つ理由の第1位は「思っていたよりも利用頻度が低い」で40.9%を占めています。契約時は頻繁に使うつもりでも、実際には月に数回しか利用しないケースが多く見られます。
例えば、月額1,000円のサービスを1か月に2回しか利用しない場合、1回あたりの実質コストは500円となります。都度利用であれば300円で済むサービスなら、サブスクにすることで逆に割高になってしまうのです。
出典:消費者庁「サブスクリプション・サービスに関する意識調査結果」
複数契約による支出の累積に気づいていない
動画配信、音楽配信、電子書籍など、類似サービスを複数契約している場合、月々の支出が想像以上に膨らみます。個々のサービスは数百円から千円程度でも、5つ契約すれば月額5,000円、年間6万円の固定費となるのです。
家計における固定費の増加は、可処分所得を圧迫します。特に使っていないサービスまで含まれていれば、明らかに無駄な支出と言えるでしょう。
無料期間終了後の自動課金に気づかない
国民生活センターには、サブスクリプションに関する相談が毎月500件以上寄せられています。その多くが「無料期間内に解約を忘れ、自動的に有料サービスに移行された」というトラブルです。
無料トライアル期間中は支払いが発生しないため、利用を開始したこと自体を忘れてしまうケースがあります。期間終了後は自動で有料プランに切り替わる仕組みのため、気づいたときには数か月分の料金が引き落とされていたという相談が後を絶ちません。
解約方法がわからず継続してしまう
消費者庁の調査では、不満理由の第2位に「プランの変更や解約のための手続が煩わしい」が27.1%で挙がっています。契約時は簡単でも、解約方法が複雑だったり、電話でしか受け付けていなかったりするサービスも存在するのです。
解約の手間を惜しんで、使っていないサービスの支払いを続けてしまう人は多く見られます。月額料金が少額であればあるほど、「まあいいか」と放置しがちになるのが実情です。
契約内容を把握していない
国民生活センターによる相談事例の分析では、以下の問題点が指摘されています。
・サブスクがどのような契約なのか正しく理解していない
・契約内容や契約先の事業者を誤って認識している
・解約したつもりが、解約できていなかった
契約時に自動更新の条件や解約方法を確認せず、後からトラブルになるケースが頻発しているのです。
サブスクで得する人の特徴

一方で、サブスクリプションサービスを上手に活用し、家計にプラスの効果をもたらしている人も存在します。得する人の使い方には明確なパターンがあるのです。
高頻度で利用している
サブスクで得をするための最も重要な条件は、サービスを十分に活用していることです。消費者庁の調査では、利用理由の第1位に「都度利用したり、購入したりするよりも安価に利用できる」が挙がっています。
例えば、1回300円のレンタルを月に10回利用する人が、月額1,000円で見放題のサービスに加入すれば、3,000円かかっていたコストが1,000円で済みます。年間では24,000円の節約になるのです。
利用頻度が高ければ高いほど、1回あたりのコストは下がり、お得度は増していきます。
契約内容を定期的に見直している
得する人は、契約しているサブスクの内容を定期的にチェックしています。以下のような見直しを行うことで、無駄な支出を防いでいるのです。
・過去3か月の利用頻度を確認する
・類似サービスの重複契約をチェックする
・月額料金と利用回数から1回あたりのコストを計算する
・使っていないサービスは即座に解約する
見直しの頻度は、少なくとも3か月に1回が望ましいでしょう。利用状況は時期によって変動するため、定期的な確認が重要になります。
年間プランを賢く活用する
多くのサブスクサービスでは、月額プランに加えて年間プランを用意しています。年間プランは月額換算で10~20%程度割安に設定されているケースが多く見られます。
確実に1年間利用すると判断できるサービスについては、年間プランを選択することで支出を抑えられます。ただし、途中解約しても返金されない場合がほとんどなので、慎重な判断が必要です。
無料トライアルを計画的に利用する
得する人は、無料トライアルを上手に活用しています。重要なのは以下の点です。
・トライアル開始日をカレンダーに記録する
・有料切り替え日の2~3日前にリマインダーを設定する
・継続の判断基準を事前に決めておく
・不要と判断したら即座に解約手続きを行う
無料期間を有効に使えば、サービスの質を見極めたうえで継続の可否を判断できます。
家族でアカウント共有を活用する
多くのサブスクサービスでは、1つのアカウントで複数のデバイスでの利用や、家族アカウントの作成が可能です。家族で利用すれば、1人あたりのコストはさらに下がります。
例えば、月額2,000円のサービスを家族4人で利用すれば、1人あたり500円の負担で済みます。ただし、アカウント共有のルールはサービスによって異なるため、利用規約の確認が必要です。
家計を守るためのサブスク管理術

サブスクリプションサービスが家計を圧迫しないようにするには、適切な管理が不可欠です。CFPの視点から、具体的な管理方法を提案します。
契約リストを作成し可視化する
まず着手すべきは、現在契約しているすべてのサブスクをリスト化することです。記録すべき項目は以下の通りとなります。
・サービス名
・月額料金
・契約開始日
・次回更新日
・解約方法
・過去3か月の利用回数
可視化することで、契約の全体像が把握でき、不要なサービスが明確になります。
月間・年間の上限額を設定する
サブスクの支出に上限を設けることで、契約の無秩序な増加を防げます。家計における娯楽費の割合を考慮し、例えば「月額3,000円まで」「年間36,000円まで」といった基準を設定しましょう。
新しいサービスを追加したい場合は、既存の契約を解約してから加入するルールにすれば、常に上限内に収まります。
クレジットカード明細を毎月確認する
サブスクの多くはクレジットカード決済のため、明細に引き落とし履歴が残ります。月に1回は必ず明細をチェックし、認識していない引き落としがないか確認することが重要です。
特に注意すべきは、少額の定期支払いとなります。数百円の引き落としは見落としやすく、長期間気づかないケースがあるのです。
契約前に自問する3つの質問
新しいサブスクを契約する前に、以下の3つの質問を自分に投げかけることを推奨します。
・このサービスを週に何回以上使う予定があるか
・都度利用と比較して本当に安くなるか
・既存の契約で代替できないか
すべての質問に明確な答えが出せない場合は、契約を見送るべきでしょう。
2022年に策定された消費者保護の指針
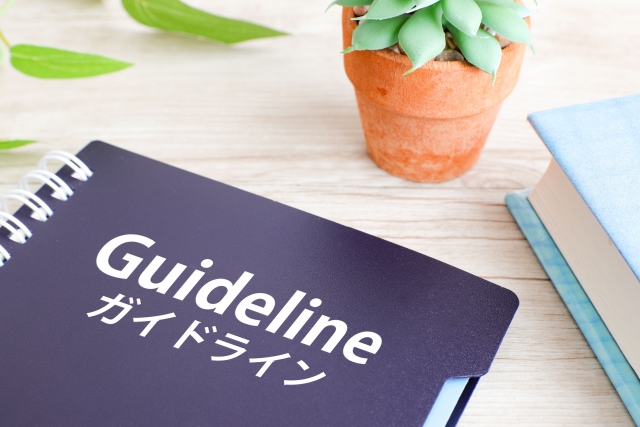
サブスクリプションに関する消費者トラブルの増加を受け、消費者庁は事業者向けの指針を策定しました。契約時の注意点とともに確認していきましょう。
契約内容の明示を求める新指針
消費者庁は2022年2月に初の指針を公表しました。事業者に対し、インターネット上の契約の最終画面に以下の項目を明示するよう求めています。
・無料から有料に切り替わる時期
・支払い内容
・契約期間
・自動更新の有無
・解約方法の制限
これらの情報は、文字の大きさや色を工夫して目立たせる必要があるとされました。「初回無料」の文字よりも有料料金の記載が小さい場合は、指針に違反する可能性が高いと明示されています。
出典:消費者庁
契約時の確認ポイント
指針の策定により、以前よりも契約内容が分かりやすくなっていますが、それでも利用者側の確認は必須です。特に以下の点には注意が必要となります。
・無料期間がいつまでか
・自動更新されるのか
・解約はいつまでに手続きが必要か
・解約方法は簡単か(オンラインで完結するか)
これらの情報は契約前に必ず確認し、メモやスクリーンショットで記録しておくことを推奨します。
トラブルに遭遇したときの対処法

万が一、サブスクリプションサービスでトラブルに遭遇した場合の対処法を知っておくことも重要です。
消費生活センターへの相談
サブスクリプションに関して困ったことがあれば、消費者ホットライン「188」に電話すれば、最寄りの消費生活センターにつながります。相談は無料で、専門の相談員が対応してくれるのです。
相談の際は、契約時の画面のスクリーンショットや、メールでのやり取り、クレジットカードの明細など、証拠となる資料を準備しておくとスムーズに進みます。
事業者との交渉ポイント
解約を申し出ても引き止められたり、解約方法が不明確だったりする場合は、以下の対応を取りましょう。
・やり取りは記録に残る方法(メール、チャット)で行う
・解約の意思を明確に伝える
・消費者庁の指針に言及する
・応じない場合は消費生活センターに相談する旨を伝える
正当な理由なく解約を拒否することは、消費者契約法に抵触する可能性があります。
まとめ:サブスクを味方につける賢い利用法
サブスクリプションサービスは、適切に利用すれば家計の支出を抑え、生活を豊かにする有用なツールとなります。しかし、契約内容を把握せず、利用頻度が低いまま放置すれば、家計を圧迫する固定費の塊となってしまうのです。
損する人と得する人の差は、契約の管理にあります。契約しているサービスを可視化し、定期的に見直しを行い、本当に必要なサービスだけを継続する。この基本を守れば、サブスクは強い味方となるでしょう。
国民生活センターへの相談件数が月500件を超えている現状は、多くの人がサブスクの管理に苦慮していることを示しています。本記事で紹介した管理方法を実践し、無駄な支出を削減することで、より豊かな家計運営を実現していただきたいと考えます。
サブスクは便利なサービスですが、だからこそ油断は禁物です。定期的な見直しと適切な管理が、家計を守る鍵となります。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
金子賢司へのライティング・監修依頼はこちらから。ポートフォリオもご確認ください。



