ニーサ
NISA非課税期間終了後の選択肢!売却?移管?具体的な対応策

2023年末で旧NISA(一般NISAとつみたてNISA)の新規投資は終了しましたが、それ以前にNISA口座で投資した商品は、それぞれの非課税期間(一般NISAは最長5年、つみたてNISAは最長20年)が終了するまで非課税で運用できます。しかし、その期間が終了した時、どうすれば良いか迷う方も多いでしょう。
この記事では、旧NISAの非課税期間終了後、あなたの資産をどう扱うべきか、「売却」と「課税口座への移管」という二つの具体的な選択肢に焦点を当てて解説します。それぞれのメリット・デメリット、そして税金への影響まで、あなたの資産を「損」させないための具体的な対応策を詳しくご紹介します。
旧NISA非課税期間終了後の基本:自動的に課税口座へ
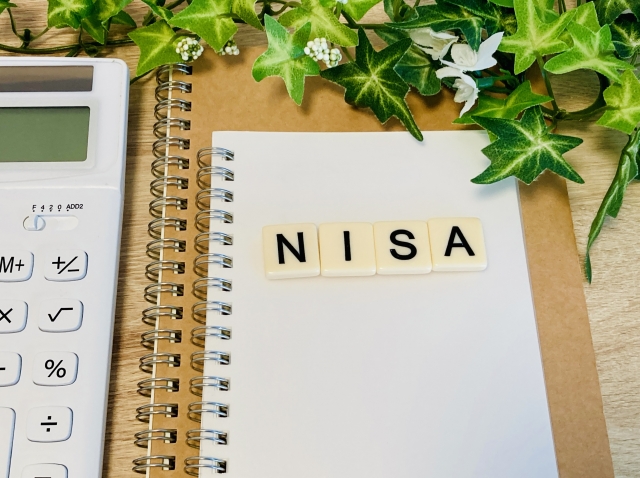
旧NISA口座で保有している株や投資信託は、非課税期間が終了すると、原則として自動的に「課税口座(特定口座または一般口座)」へ移管されます。
この「課税口座への自動移管」は、あなたが特に何も手続きをしなかった場合に起こるデフォルトの対応です。移管された後は、その商品から得られる利益(売却益や配当金・分配金)には、通常の税金(20.315%)がかかるようになります。
しかし、自動移管以外にも選択肢があります。それが「売却する」という方法です。この2つの選択肢について、詳しく見ていきましょう。
選択肢1:非課税期間終了前に「売却」する
非課税期間が終了するのを待たずに、期間中に保有商品を売却して現金化する方法です。
メリット
・利益が非課税で確定する: もし売却時に利益(含み益)が出ていれば、その利益はNISAの恩恵により全額非課税で受け取れます。
・資金の自由度が高い: 売却した現金は、必要な時に自由に使うことができます。
・「みなし取得価格」問題を回避: 後述する、課税口座移管後の複雑な税金の問題を避けることができます。
デメリット
・含み損があれば損失が確定: 売却時に含み損(購入時より価値が下がっている状態)がある場合、その損失が確定してしまいます。NISA口座の損失は、他の利益と損益通算できないため、税制上のメリットは得られません。
・最適なタイミングでの売却が難しい: 資金ニーズや非課税期間終了のタイミングによっては、市場価格が低い状態で売却せざるを得ない場合があります。
こんな人におすすめ
・非課税期間中に目標金額に達した人: 利益を確定して、現金を確保したい場合。
・損失が出ているが、これ以上損失を広げたくない人: 一旦区切りをつけたい場合。
・課税口座への移管後の税金計算をシンプルにしたい人: 複雑な手続きや税務を避けたい場合。
選択肢2:非課税期間終了後も「課税口座へ移管」して保有を続ける
非課税期間が終了した商品を売却せず、そのまま課税口座(特定口座または一般口座)へ移管し、保有し続ける方法です。
メリット
・継続的な長期保有が可能: 非課税期間終了後も、売却せずに商品を保有し続けることができます。これにより、市場回復を待ったり、さらなる成長に期待したりできます。
・売買のタイミングをずらせる: 資金ニーズがない場合や、市場状況が良くない場合に、焦って売却する必要がなくなります。
デメリットと「みなし取得価格」の注意点
課税口座へ移管する際に最も注意すべきは、「みなし取得価格」の考え方です。
・移管時の時価が新しい取得価格に: 旧NISA口座から課税口座へ移管された時点の時価(市場価格)が、課税口座における「新しい取得価格」として扱われます。これ以降、その価格を基準に利益・損失が計算され、売却時に税金がかかることになります。
ケース1:移管時に利益が出ている場合(含み益がある場合) 例えば、100万円で買った商品が、移管時に150万円になっていたとします。この場合、移管後の取得価格は150万円となります。その後、160万円で売却すれば、利益は10万円とみなされ、この10万円に課税されます。NISAの非課税期間中に得た50万円の利益は非課税のままです。 → このケースは税制上有利になりやすいです。
ケース2:移管時に損失が出ている場合(含み損がある場合) 例えば、100万円で買った商品が、移管時に80万円になっていたとします。この場合、移管後の取得価格は80万円となります。その後、90万円に回復して売却した場合、税制上は「10万円の利益が出た」とみなされ、この10万円に課税されてしまいます。実際は100万円で買って90万円で売ったので「10万円の損失」ですが、課税上は「利益」扱いになる、という点に注意が必要です。 → このケースは、税制上不利になる可能性があるため、特に注意が必要です。
こんな人におすすめ
・非課税期間終了後もその商品を長期保有したい人: 売却せずに運用を継続したい場合。
・移管時に含み益が出ている人: 移管後の税負担を抑えやすい傾向があるため。
・非課税期間中に損失を抱えており、売却せずに回復を待ちたい人: ただし、「みなし取得価格」の問題を理解しておく必要があります。
「ロールオーバー」は新NISAにはない

旧NISAの「一般NISA」では、非課税期間終了後に「ロールオーバー」(翌年のNISA枠を使って非課税で運用を継続)という選択肢がありましたが、新NISA制度にはこのロールオーバーの仕組みはありません。新NISAは非課税期間が無期限になったため、そもそもロールオーバーの必要がなくなったためです。
旧NISA口座で保有している資産については、前述の「売却」か「課税口座への移管」のどちらかの対応を取ることになります。
あなたの状況に合わせた賢い対応策を選ぶために
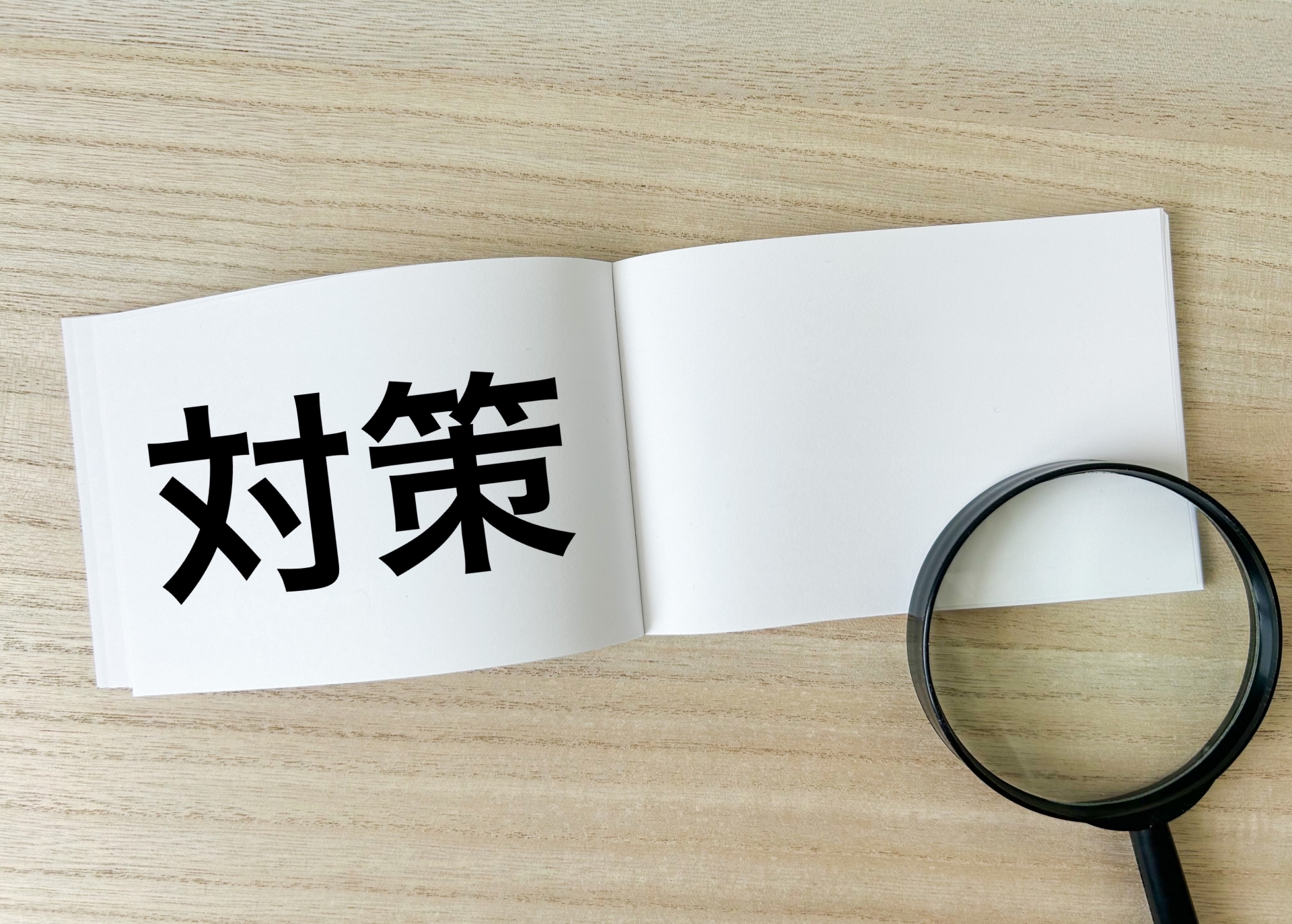
旧NISAの非課税期間終了後の対応は、あなたの資産状況や今後のライフプランによって最適な選択肢が異なります。
1.まずは保有商品の現状を確認する: 非課税期間の終了時期と、現在の含み益・含み損の状況を把握しましょう。金融機関の取引画面で確認できます。
2.今後の資金ニーズを考える: 近いうちにその資金を使う予定があるのか、それとも長期的に使う予定がないのかを確認します。
3.「みなし取得価格」の理解を深める: 特に含み損がある状態で課税口座へ移管する際は、税制上の「みなし取得価格」の問題をしっかりと理解し、不利にならないか検討しましょう。
4.必要に応じて専門家へ相談する: 判断に迷う場合や、複雑な資産状況の場合は、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することも有効です。
まとめ:旧NISAの「出口」を賢く管理し、新NISAに集中しよう
旧NISAの非課税期間終了は、資産管理の見直しをする良い機会です。「売却」と「課税口座への移管」、それぞれのメリット・デメリットや税金への影響を理解し、あなたの資産状況とライフプランに合わせた最適な対応策を選びましょう。
旧NISAの管理を適切に行いつつ、今後は非課税期間が無期限である新NISAの年間投資枠を最大限に活用し、あなたの資産形成をより効率的かつ柔軟に進めていくことが重要です。



