ニーサ
NISA出口戦略の難しさを解決|具体的な5つのポイントと実践方法

2024年から開始された新NISA制度では、非課税保有期間が無期限となり、投資の自由度が大きく向上しました。しかし、この自由度の高さが逆に「いつ、どのように資産を引き出すべきか」という出口戦略の難しさを生んでいます。
従来の一般NISAやつみたてNISAでは、5年または20年という明確な非課税期間の期限があったため、その期限に合わせて売却や課税口座への移管を検討すればよかったものです。新NISAではこうした期限がなくなり、投資家自身が最適な出口を見極める必要があります。
新NISAで出口戦略が難しくなった3つの理由
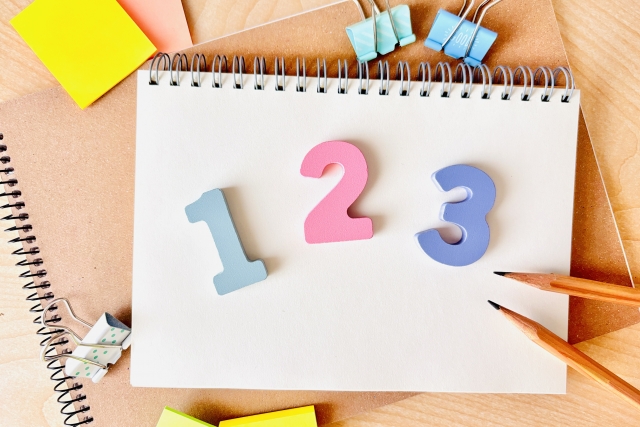
非課税期間の無期限化による判断の複雑化
新NISAでは非課税保有期間が無期限となったことで、売却のタイミングを自ら決定する必要が出てきました。従来制度では非課税期間終了時に必然的に判断を迫られましたが、現在はいつまでも保有し続けられる仕組みになっています。
この自由度の高さは、裏を返せば「適切な売却タイミングの判断が難しい」という課題を生んでいるのが実情でしょう。市場の変動に一喜一憂して早期に売却してしまったり、逆に必要な時期に資金を引き出せなかったりするリスクがあります。
年間投資枠と生涯投資枠の管理
新NISAでは、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円で、合計360万円の年間投資上限額が設定されました。さらに、生涯での非課税保有限度額は1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)となっています。
売却した商品の取得価額分は翌年以降に非課税投資枠として復活しますが、年間投資上限額は変わりません。この枠の管理と、いつ売却して枠を復活させるかの判断が、出口戦略を考える上で重要なポイントになります。
出典:金融庁 NISAとは
ライフステージに応じた柔軟な対応の必要性
マイホーム購入、子どもの教育費、退職後の生活資金など、人生の各段階で必要となる資金は異なります。新NISAは無期限で運用できるため、こうしたライフイベントに合わせて資産を取り崩すことが可能になりました。
しかし同時に、各ライフステージでどれくらいの資産を残し、どれくらい取り崩すべきかという判断が求められるようになったのです。
NISA出口戦略における5つの重要ポイント

ポイント1:4%ルールを活用した計画的な取り崩し
出口戦略で広く知られているのが「4%ルール」という考え方になります。これは1998年に米国トリニティ大学の研究で導き出された理論で、保有資産の4%を毎年取り崩していけば、30年以上経っても資産が枯渇しない確率が高いとされるものです。
具体的には、年間支出額の25倍の資産があれば、その4%を取り崩して生活できるという計算です。例えば年間240万円の生活費が必要な場合、6,000万円の資産があれば4%ルールを適用できることになります。
ただし注意が必要な点もあります。この研究は米国株式の成長率(約7%)から物価上昇率(約3%)を引いた実質リターン4%を前提としており、日本の投資環境にそのまま適用できるとは限りません。また、為替リスクや日本独自の経済環境も考慮する必要があるでしょう。
ポイント2:定期売却サービスの活用
証券会社が提供する定期売却サービスを利用することで、毎月一定額または一定口数を自動的に売却し、現金化することができます。このサービスには主に3つの方式があり、それぞれの特徴を理解して選択することが重要です。
・定額売却:毎月同じ金額を受け取る方式で、生活費の計画が立てやすいメリットがあります
・定率売却:保有資産に対して一定の割合を売却する方式で、資産残高に応じて受取額が変動します
・定口売却:毎月同じ口数を売却する方式で、基準価額の変動により受取額が変わります
定期売却サービスを利用することで、感情に左右されず計画的な資産取り崩しが実現でき、相場の変動時にも冷静な判断を保つことができるでしょう。
ポイント3:コア・サテライト戦略による段階的取り崩し
資産をコア資産(堅実に増やす長期保有資産)とサテライト資産(積極的にリターンを狙う資産)に分けて運用し、取り崩す際はまずサテライト資産から始める戦略が有効です。
コア資産は全体の70~90%程度を占め、インデックス型の投資信託など値動きが比較的安定した商品で構成することが一般的になります。一方、サテライト資産は10~30%程度で、個別株式や新興国株式など高いリターンを期待できる商品で構成するのが基本です。
この戦略により、コア資産を維持しながら必要な資金を確保でき、長期的な資産の安定性を保つことができるでしょう。
ポイント4:市場環境に応じたタイミング調整
出口戦略では、可能な限り市場が好調な時期に売却することが望ましいといえます。しかし、完璧なタイミングを狙うことは現実的ではありません。
重要なのは、市場が大きく下落している時期に慌てて売却しないことになります。新NISAは非課税期間が無期限のため、市場の回復を待つ時間的余裕があるのが大きな利点です。
また、定期的に少しずつ売却する「ドルコスト平均法」の考え方を取り崩しにも応用することで、タイミングリスクを分散できるでしょう。
ポイント5:年金受給とのバランス設計
退職後の生活では、公的年金とNISA資産からの取り崩しをバランスよく組み合わせることが重要になります。年金受給開始前の期間、受給開始後の補填額、医療費増加に備えた予備費など、段階的な資金計画が必要です。
特に65歳前後で退職する場合、年金受給開始までの期間をどうカバーするかが重要な検討事項となります。この期間のためにNISA資産の一部を取り崩す計画を立てておくことで、安心して退職を迎えることができるはずです。
出口戦略実践における3つの注意点

損益通算ができない点を理解する
NISA口座で購入した商品が値下がりして損失が出た場合でも、他の課税口座での利益と損益通算することができません。これはNISAのデメリットの一つといえるでしょう。
したがって、値下がりした商品を損切りする際は、その損失を他の利益と相殺できないことを理解した上で判断する必要があります。
旧NISA口座の資産は別管理
2023年以前に開設した一般NISAやつみたてNISAの口座で保有している商品は、新NISA口座とは別枠で管理され、新NISA口座にロールオーバー(移管)することはできません。
一般NISAは購入から5年間、つみたてNISAは購入から20年間、それぞれ非課税で保有できる仕組みになっています。非課税期間終了後は課税口座に払い出されるか、売却する必要があるため、この点も含めて総合的な出口戦略を考えることが大切です。
出典:金融庁 よくある質問
過度な取り崩しリスクへの対処
4%ルールはあくまで目安であり、必ずしも成功を保証するものではありません。市場が長期的に低迷した場合や、想定以上の出費が発生した場合には、資産が早期に枯渇するリスクもあるのです。
そのため、取り崩し率を3~3.5%程度に抑える、緊急予備資金を別途確保しておく、年金以外の収入源を持つなど、複数のリスク対策を講じることが賢明でしょう。
ライフステージ別の出口戦略の考え方

40~50代:資産形成と出口準備の両立期
この年代では、まだ資産形成の途中段階にありながら、出口戦略を意識し始める時期になります。年間投資上限額を活用して積極的に投資を続けつつ、退職後の生活に必要な金額を試算し始めることが重要でしょう。
また、子どもの教育費など一時的な大きな支出に備えて、成長投資枠の一部を流動性の高い商品で保有しておくことも検討すべきポイントです。
60代前半:退職準備と取り崩し開始期
退職が近づくこの時期は、リスクを徐々に抑えた運用に移行しながら、実際の取り崩しを開始する準備をします。株式の比率を下げ、債券やバランス型ファンドの比率を高めることで、値動きを安定させることができます。
公的年金の受給開始年齢との関係で、65歳までの生活資金をどう確保するかも重要な検討事項となるでしょう。
60代後半以降:安定的な取り崩し実行期
年金受給が始まったこの時期は、年金だけで不足する生活費をNISA資産から計画的に取り崩していきます。定期売却サービスを活用し、毎月一定額を受け取る仕組みを作ることで、安定した生活を送ることができるはずです。
また、医療費や介護費用の増加に備えて、取り崩し額に余裕を持たせることも考慮すべきでしょう。
まとめ:計画的な出口戦略で安心の資産活用を
新NISAの出口戦略は、非課税期間の無期限化により自由度が増した反面、投資家自身が適切な判断を下す必要がある点で難しさを感じる方も多いでしょう。
重要なのは、早い段階から出口を意識した資産運用を心がけることになります。4%ルールや定期売却サービスなどの具体的な手法を理解し、コア・サテライト戦略で段階的に取り崩しを行うことで、資産寿命を延ばすことができます。
また、市場環境や自身のライフステージの変化に応じて、柔軟に戦略を見直すことも大切です。年金受給とのバランス、医療費や介護費用への備え、相続対策なども含めた総合的な視点で、最適な出口戦略を設計していくことが求められるでしょう。
新NISAは長期的な資産形成を支援する優れた制度ですが、その恩恵を最大限に活用するためには、入口だけでなく出口の戦略も同じくらい重要です。専門家のアドバイスも活用しながら、自分に合った出口戦略を早めに検討し始めることをお勧めします。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
金子賢司へのライティング・監修依頼はこちらから。ポートフォリオもご確認ください。



