iDeCo
iDeCoの解約はできる?例外的な解約条件と手続き

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金を準備するための強力な制度ですが、その資産は原則として60歳になるまで引き出すことができません。この「資金拘束」が、iDeCoを始める上で不安に感じる大きな理由の一つでしょう。
この記事では、iDeCoが原則として解約できないことを再確認した上で、どのような場合に例外的に解約が可能なのか(脱退一時金の受給)を詳しく解説します。さらに、解約手続きと必要書類まで、iDeCoの制度とリスクを正しく理解するためのヒントを提案します。
iDeCoは原則として解約できない

iDeCoは、老後資金を確実に準備することを目的とした「私的年金制度」です。そのため、途中で資金が使われてしまうことを防ぐために、以下のような強い資金拘束のルールが設けられています。
・原則60歳まで引き出し不可:
iDeCoで積み立てた資産は、原則として60歳まで(正確には、加入期間が10年以上などの受給要件を満たした上で)引き出すことができません。
・途中で脱退できない:
iDeCoは、年金制度に加入している間は、原則として脱退できません。掛金の拠出を一時的に停止することは可能ですが、口座を解約して資産を引き出すことはできないのです。
・最大のメリットとの引き換え:
この資金拘束があるからこそ、iDeCoは「掛金の所得控除」や「運用益非課税」といった、他の金融商品にはない強力な税制メリットが認められています。
したがって、iDeCoは「いつでもお金を自由に使える貯蓄」ではなく、「老後資金を確実に守り育てるための特別な制度」であると理解することが重要です。
例外的な「脱退一時金」の解約条件

iDeCoは原則解約できませんが、ごく限られた状況で、年金として受け取る年齢になる前に解約し、資産を「脱退一時金」として受け取ることが認められています。
脱退一時金を受け取るには、複数の厳格な要件をすべて満たす必要があります。
脱退一時金を受け取るための主な要件
脱退一時金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.現在、確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)に加入者でも運用指図者でもないこと。
2.国民年金の被保険者でないこと(ただし、日本国籍を持つ海外居住者など一部例外あり)。
3.国民年金保険料の免除者など、iDeCoに加入できない状況にあること。
4.最後に確定拠出年金の加入者資格を喪失した日から2年以内であること。
5.iDeCoの通算拠出期間が1ヶ月以上5年以下、または個人別管理資産額が25万円以下であること。
6.障害給付金の受給権者でないこと。
これらの要件をすべて満たす人は非常に限られており、通常の生活者が途中で「お金が必要だから」という理由で解約することは、ほぼ不可能です。
また、上記とは別の要件で、年金資産が15,000円以下で、かつ、最後に確定拠出年金の加入者資格を喪失した日から6ヶ月以内であることなど、特定の要件を満たす場合に解約が認められるケースもあります。
【重要】脱退一時金の要件は非常に複雑かつ厳格です。詳細は、必ずご自身のiDeCo口座を開設している金融機関にご確認ください。
解約手続きと必要書類
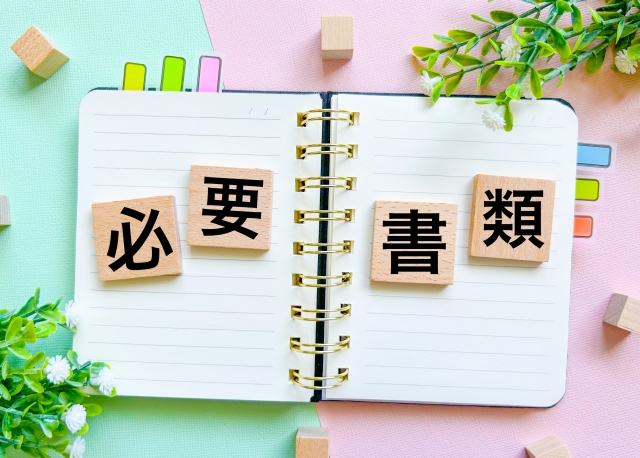
例外的な解約条件に当てはまる場合、または将来の受け取り時(60歳以降)の解約(一時金請求)の手続きは、iDeCoの運営管理機関を通じて行います。
解約手続きの流れ
1.脱退一時金の支給要件の確認:
まずは、ご自身が例外的な解約条件を満たしているか、iDeCo口座を開設している金融機関(運営管理機関)に確認しましょう。
2.必要書類の請求:
要件を満たしている場合、運営管理機関に「脱退一時金裁定請求書」などの書類を請求します。
3.必要書類の提出:
請求書に記入し、以下の必要書類(ご自身の状況による)を添付して提出します。
・本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカードなど
・国民年金保険料の納付状況を確認できる書類
・年金手帳のコピーなど
4.審査と支払い:
提出された書類は国民年金基金連合会で審査され、要件を満たしていれば、数ヶ月後に指定の金融機関口座へ脱退一時金が支払われます。
注意点: 脱退一時金を受け取ると、それまでに積み立ててきた期間がリセットされ、将来iDeCoに再度加入する際に、以前の加入期間が通算されないなどの制約が生じることがあります。
まとめ:iDeCoの解約は難しい!老後資金と他資産のバランスが重要
iDeCoは、原則60歳まで解約できない資金拘束が最大の特徴です。
・老後資金と割り切る: 60歳まで引き出せないことを前提に、「確実に老後資金を貯める」ための制度だと理解しましょう。
・「生活防衛資金」は別途確保: 病気や失業、急な出費に備える「生活防衛資金」は、iDeCoとは別に、いつでも引き出せる預貯金として確保しておくことが、iDeCo運用を安心して続けるための大前提です。
・NISAとの使い分け: 資金の柔軟性を求めるのであれば、いつでも引き出し可能なNISAとiDeCoを併用し、役割を分担させることが賢明です。
iDeCoは、途中で解約できないからこそ、老後資金形成のための強力な税制優遇が受けられます。この制度の特性を正しく理解し、他の資産とのバランスを考慮した上で、賢く活用していきましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



