iDeCo
iDeCoの受け取りとNISAの取り崩し:老後資金活用の出口戦略比較
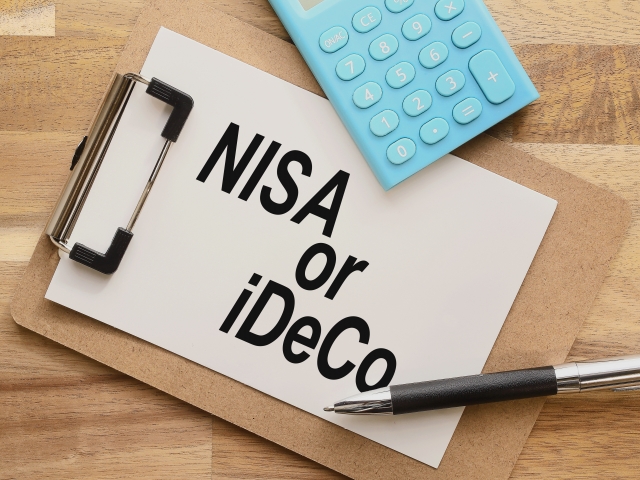
「iDeCoって60歳になったらどうやって受け取るの?税金はかかる?」
「NISAで貯めたお金は、老後にどうやって使えば一番お得なの?」
「老後資金って、iDeCoとNISA、どっちから使うのが正解なんだろう…」
iDeCo(個人型確定拠出年金)とNISA(少額投資非課税制度)は、どちらも老後資金形成に欠かせない強力な税制優遇制度です。しかし、これらの制度は「お金を増やす」段階だけでなく、「お金を受け取る・取り崩す」段階、つまり「出口戦略」においても、その仕組みと税制が大きく異なります。
この記事では、iDeCoの一時金・年金受け取り時の税制優遇の詳細を解説し、NISAの非課税取り崩しと徹底比較します。そして、あなたの老後資金を最大限に有効活用するために、受取計画におけるiDeCoとNISAそれぞれの役割を明確にし、賢い出口戦略を提案します。
iDeCoの受け取りは「原則60歳以降」から
iDeCoで積み立てた資産は、原則60歳まで引き出せません。しかし、60歳になったからといって自動的に受け取りが始まるわけではありません。受け取りを開始できるのは、あなたがiDeCoの加入期間が10年以上であるなど、受給要件を満たした後です。
受給要件(加入期間に応じた受給開始年齢)
・加入期間が10年以上の場合: 60歳から受給可能
・加入期間が8年以上10年未満の場合: 61歳から受給可能
・加入期間が6年以上8年未満の場合: 62歳から受給可能
・加入期間が4年以上6年未満の場合: 63歳から受給可能
・加入期間が2年以上4年未満の場合: 64歳から受給可能
・加入期間が1ヶ月以上2年未満の場合: 65歳から受給可能
ほとんどの人は、20歳代や30歳代からiDeCoを始めるため、60歳には受給要件を満たし、受け取りが可能です。ただし、60歳以降も運用を継続し、75歳まで受け取り開始を遅らせることもできます(2022年5月改正で上限年齢が70歳から75歳に拡大)。
iDeCoの主な受け取り方法3種類

iDeCoの老齢給付金は、以下の3つの方法で受け取ることができます。
一括で受け取る「一時金」
積み立てた資産を一括で受け取る方法です。退職金と同じ「退職所得」として扱われ、退職所得控除が適用されます。
年金として分割で受け取る「年金」
積み立てた資産を、例えば5年、10年、20年といった一定期間にわたって分割して年金形式で受け取る方法です。公的年金と同じ「雑所得」として扱われ、公的年金等控除が適用されます。
「一時金」と「年金」を組み合わせて受け取る「併用」
一部を一時金として受け取り、残りを年金として分割で受け取る方法です。税制優遇を最大限に活用するために、この併用を選ぶ人も多いです。
それぞれの受け取り方にかかる税金と仕組み

iDeCoの最大の魅力である税制優遇は、受け取り時にも適用されます。しかし、一時金か年金かによって適用される控除が異なるため、税金計算の仕組みを理解しておくことが重要です。
一時金で受け取る場合の税金(退職所得控除)
一時金として受け取る場合、受け取った金額は「退職所得」として扱われ、以下の計算式で税金がかかる部分(課税対象額)が算出されます。
(一時金受取額 − 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の課税対象額
この「退職所得控除額」は非常に大きく、勤続年数によって計算されます。
・勤続年数20年以下の場合: 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
・勤続年数20年超の場合: 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)
出典:国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
【重要ポイント】
・会社からの退職金とiDeCoの一時金を合算して控除額が計算されます。 そのため、会社からの退職金が多い人は、iDeCoの一時金に税金がかかる可能性が高まります。
・iDeCoは、退職金と受け取る年が異なれば、別々に控除枠を利用できる「5年ルール」(※2026年1月からは「10年ルール」に変更される予定)という優遇もあります。例えば、退職金を受け取ってから5年(改正後は10年)経過後にiDeCoの一時金を受け取れば、新たに退職所得控除枠を利用できるため、税負担を大幅に軽減できます。
2. 年金で受け取る場合の税金(公的年金等控除)
年金として分割で受け取る場合、受け取った金額は「雑所得」として扱われ、公的年金等控除が適用されます。
・仕組み: 公的年金等(国民年金、厚生年金など)の合計額から、年齢に応じた一定の控除額が差し引かれます。控除額を超えた部分が課税対象となります。
公的年金等控除額の目安(65歳以上の場合、2025年7月現在の制度):
・公的年金等の収入金額が110万円以下の場合: 全額控除(雑所得なし)
・公的年金等の収入金額が110万円超160万円以下の場合: 60万円控除
※年収によって変動する場合があります
出典:国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
【重要ポイント】
・公的年金とiDeCoの年金を合算して控除額が計算されます。 公的年金の受給額が多い場合、iDeCoの年金が課税対象となる可能性が高まります。
・年金として受け取る場合は、毎年税金計算が必要になります。
NISAの取り崩しとiDeCoとの比較

NISA口座で運用してきた資産は、原則としていつでも自由に売却し、現金として引き出すことができます。
NISAの非課税取り崩し
税制優遇: NISA口座内で得た運用益は、売却時に非課税です。つまり、投資した元本と、その元本から生じた利益(売却益、配当金など)の全額を、税金がかかることなく手元に受け取ることができます。
【特徴】
・自由度が高い: 必要な時に必要な金額だけ売却・引き出しが可能です。資金使途に制限もありません。
・非課税期間が無期限(新NISA): いつまで保有しても運用益は非課税のままです。
・売却枠の復活(新NISA): 売却した元本分の非課税投資枠は翌年以降に復活するため、再投資することも可能です。
【注意点】
・iDeCoのような所得控除はなし: NISAの取り崩し自体に、iDeCoの退職所得控除や公的年金等控除のような特別な控除はありません。あくまで「運用益が非課税」というメリットのみです。
・損失の損益通算不可: もし売却時に損失が出たとしても、他の利益と損益通算することはできません。
iDeCoとNISAの出口戦略における主な違い

資金使途:
・iDeCo: 老後資金に限定(原則60歳まで引き出し不可)。
・NISA: 自由(老後資金、教育資金、住宅資金など)。
受け取り方:
・iDeCo: 一時金(退職所得控除)、年金(公的年金等控除)を選べます。
・NISA: 必要な時に必要な金額を売却・引き出し(運用益非課税)。
税制優遇の質:
・iDeCo: 一時金は退職所得控除により税負担が大幅軽減、年金は公的年金等控除により税負担軽減。入口(掛金控除)から出口まで税制優遇が手厚い。
・NISA: 運用益が非課税。(受け取り時の特別な所得控除はなし)。
資金の柔軟性:
・iDeCo: 低い(原則60歳まで引き出し不可、受け取り方・期間に制限)。
・NISA: 高い(いつでも引き出し可能、使途自由)。
他の収入との兼ね合い:
・iDeCo: 一時金は退職金、年金は公的年金との合算に注意。
・NISA: 他の収入との兼ね合いは比較的少ない(非課税枠内であれば)。
老後資金の受取計画における両者の役割

iDeCoとNISAは、それぞれの特性を活かすことで、老後資金の受取計画において異なる、しかし重要な役割を担います。
iDeCo:老後資金の「コア」として、税制優遇を最大限に活用
iDeCoは、現役時代の掛金控除から運用益非課税、そして受け取り時の控除まで、「入口から出口まで」手厚い税制優遇が特徴です。まずはiDeCoの掛金上限まで拠出し、老後資金の確実な土台を築きましょう。
受け取り方の検討:
・退職金が少ない・ない場合: iDeCoの一時金を退職所得控除の枠内で受け取ることで、税負担を大幅に軽減できます。
・退職金が多い場合: 退職金との合算を避け、iDeCoを年金形式で受け取る、または受け取り時期をずらすことを検討しましょう。公的年金等の受給額とのバランスも重要です。
・税理士やFPへの相談: iDeCoの受け取り方は、その時の所得状況や他の年金・退職金の有無によって最適な選択が変わります。専門家への相談が不可欠です。
NISA:老後資金の「柔軟な補完」と「緊急資金」の役割
NISAは、運用益が非課税であることに加え、資金の柔軟性が非常に高いのが特徴です。iDeCoだけでは足りない老後資金を補完する役割として活用します。
・必要な時に必要なだけ: 老後生活に入ってから、年金やiDeCo年金だけでは足りない月や、急な出費(医療費、旅行など)があった際に、NISA口座から必要な金額だけを非課税で取り崩すことができます。
・「もう一つの年金」: NISAの非課税枠内で計画的に取り崩すことで、公的年金やiDeCo年金とは別に、「自分年金」のような形で老後資金の柱とすることも可能です。
・緊急資金: 資金使途が自由であるため、万が一の緊急時にも対応できる「流動性の高い老後資金」として機能します。
両者の連携で「税負担を抑えた長寿時代の資金計画」を

iDeCoとNISAは、それぞれ異なる強みを持つため、老後資金の出口戦略においても連携させることが重要です。
・iDeCoで税制優遇を最大限に: まずはiDeCoの非課税メリットを最大限に活かし、税負担を抑えながら老後資金の「コア」を形成します。
・NISAで柔軟性と流動性を確保: NISAでは、iDeCoで固定した資金以外の「柔軟に使えるお金」を非課税で増やし、老後の様々なニーズに対応できる「サテライト」を構築します。
このように、iDeCoとNISAを両輪で活用することで、税負担を抑えつつ、長寿時代を安心して暮らせるための計画的な資金活用が可能になります。
まとめ:iDeCoとNISA、出口戦略も計画的に!
iDeCoとNISAは、老後資金を「増やす」段階だけでなく、「受け取る・取り崩す」段階においても、それぞれの特性を理解した出口戦略が重要です。
・iDeCo: 「退職所得控除」や「公的年金等控除」といった強力な受け取り時優遇がある一方で、資金拘束や受け取り方法の選択が必要です。
・NISA: 運用益が非課税で自由に引き出せる高い柔軟性があります。
あなたの老後資金の全体像を見据え、公的年金や退職金なども含めて、iDeCoとNISAからどのように資金を受け取っていくかを計画的に考えることが、豊かな老後生活を送るための鍵となります。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています



