iDeCo
iDeCoのデメリットと注意点:原則60歳まで引き出せないって本当?

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金準備のための強力な税制優遇制度です。しかし、その大きなメリットの一方で、事前にしっかり理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。特に「原則60歳まで引き出せない」という資金拘束は、iDeCoを始める上で多くの人が不安に感じるポイントでしょう。
この記事では、iDeCoのデメリットと注意点に焦点を当てて解説します。資金拘束のリスクとその裏にあるメリット、運用期間中に発生する各種手数料、元本割れのリスクと対策、そして転職・退職時の手続きの複雑さまで、あなたがiDeCoを始める前に知っておくべき情報を網羅的にご紹介します。
iDeCo最大のデメリット?「原則60歳まで引き出せない」資金拘束

iDeCoは、老後資金を準備するための制度であるため、積み立てた資産は原則として60歳まで引き出すことができません。これがiDeCo最大のデメリットであり、始める上で最も重要な注意点です。
資金拘束のリスク
・急な資金ニーズに対応できない: 病気やケガ、失業、住宅購入、子どもの教育費など、60歳より前にまとまったお金が必要になったとしても、iDeCoの資産は使えません。
・流動性の低い資産となる: 自由に使えるお金がiDeCoに固定されるため、緊急時の資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。
資金拘束の裏にある「メリット」
一見デメリットに思えるこの資金拘束には、実は老後資金準備における大きなメリットが隠されています。
・半強制的な老後資金の確保: 強制的に引き出せないため、途中で使ってしまう誘惑に駆られることなく、着実に老後資金を積み立てられます。これにより、「貯蓄が苦手」な方でも安心して老後資金を形成できます。
・長期投資の継続: 資金拘束があることで、市場の短期的な変動に一喜一憂して売買を繰り返すことを防ぎます。結果的に、長期投資の恩恵である複利効果やドルコスト平均法のメリットを最大限に享受しやすくなります。
・税制優遇の維持: 資金拘束があるからこそ、掛金の所得控除や運用益非課税といった手厚い税制優遇が認められています。
この資金拘束は、「老後資金を確実に作る」という目的を達成するための重要な仕組みだと理解しましょう。
iDeCo運用期間中に発生する各種手数料

iDeCoは税制優遇が手厚い反面、運用期間中にいくつかの手数料が発生します。これらは、運用成果に影響を与えるため、事前に把握しておくことが大切です。
運営管理機関手数料(毎月)
iDeCo口座を開設している金融機関(証券会社や銀行)に支払う手数料です。この手数料は金融機関によって異なり、月額で無料の金融機関から、数百円かかる金融機関まで様々です。長期で運用するため、この手数料が無料の金融機関を選ぶことは、運用コストを抑える上で非常に重要です。
運用商品の信託報酬(日々)
投資信託などの運用商品にかかる手数料で、運用資産額に対して年率でかかります。毎日、基準価額から自動的に差し引かれるため、気づきにくいですが、長期運用では運用成果に最も大きな影響を与えます。できるだけ信託報酬の低い運用商品を選ぶようにしましょう。
国民年金基金連合会手数料(毎月)
iDeCoの制度全体を運営するために必要な費用で、国民年金基金連合会に支払います。加入者全員に一律でかかる手数料です。
事務委託先金融機関手数料(毎月)
信託銀行(事務委託先)に支払う手数料です。加入者全員に一律でかかります。
加入・移換時手数料(初回のみ)
iDeCoに新規で加入する際や、企業型DCからiDeCoに資産を移換する際に発生する手数料です。初回のみの費用となります。
これらの手数料は、税制優遇によるメリットを上回るかどうかを判断する上で重要です。特に、毎月かかる手数料と運用商品の信託報酬は、長期運用で負担が大きくなるため、できるだけ手数料の低い金融機関や運用商品を選ぶようにしましょう。
iDeCoの「元本割れ」のリスクと対策
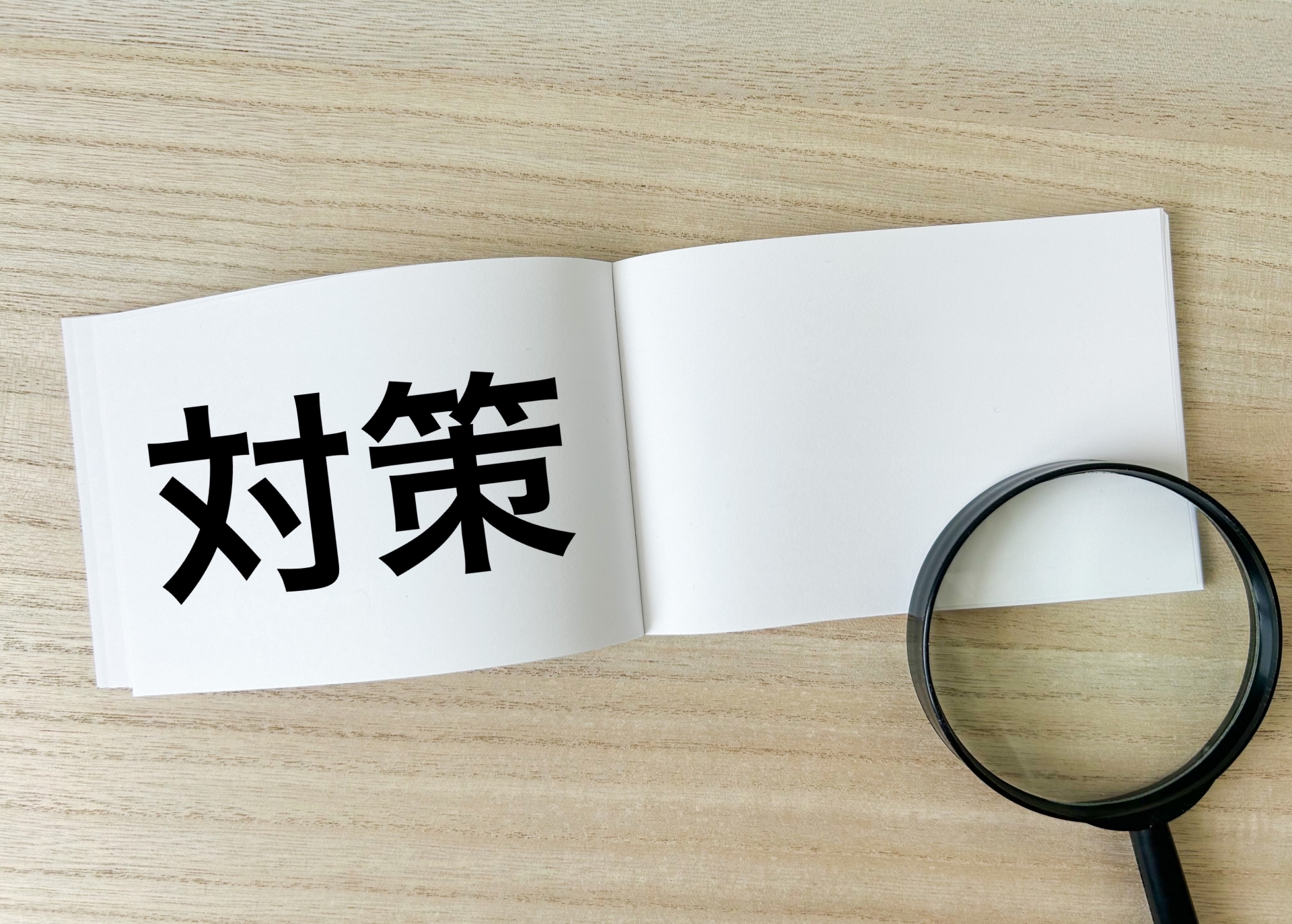
iDeCoで元本確保型商品(定期預金や保険)を選ばない限り、元本変動型である投資信託で運用する場合は、元本割れのリスクがあります。
元本割れのリスク
・市場変動リスク: 株式市場全体が下落する局面では、投資信託の評価額も下がり、元本を割り込む可能性があります。
・運用失敗リスク: 選んだ投資信託が、市場全体のリターンに劣る運用成績となる可能性もあります。
元本割れのリスクを抑える対策
元本割れのリスクを完全にゼロにすることはできませんが、以下の対策でその影響を抑えることができます。
・長期投資を徹底する: iDeCoは原則60歳まで引き出せないため、必然的に長期投資になります。歴史的に見ると、株式市場は長期で運用するほど、一時的な下落を乗り越えて回復し、利益を生む傾向があります。
・分散投資を行う:
時間の分散: 毎月一定額を積み立てる「積立投資」により、高値掴みを避け、平均購入単価を平準化する「ドルコスト平均法」の恩恵を受けられます。
資産・地域の分散: 株式だけでなく債券を組み合わせたり、日本だけでなく全世界の株式に投資したりすることで、リスクを軽減できます。iDeCoで人気の「全世界株式インデックスファンド」は、これ1本で地域・資産(一部)の分散が可能です。
・低コストのインデックスファンドを選ぶ: 高い信託報酬は運用成果を確実に削ります。できるだけ手数料が低いインデックスファンドを選ぶことで、運用効率を高め、元本割れのリスクを相対的に低減できます。
・リスク許容度に応じた商品選び: 損失が出た場合にどこまで許容できるか、自身のリスク許容度を把握し、それに合った資産配分(株式と元本確保型の比率など)を設定しましょう。
転職・退職時の手続き(移換)の複雑さ
iDeCoは、転職や退職、働き方の変化に伴い、手続きが必要になる場合があります。これが、iDeCoのデメリットの一つとして挙げられることがあります。
主な手続きと複雑さ
1.企業型DCからiDeCoへの移換: 勤務先に企業型確定拠出年金(企業型DC)があった場合、転職や退職時にその資産をiDeCoへ移し替える手続き(移換)が必要です。期限内に手続きしないと、手数料の高い「自動移換」となり、資産が減ってしまうリスクがあります。
2.iDeCoの加入者区分の変更: 会社員から自営業になった、専業主婦になった、などの働き方の変化があった場合、加入者区分(第1号〜第3号被保険者)の変更手続きが必要です。これにより、掛金の上限額も変わる可能性があります。
3.必要書類の多さ: 移換や区分変更の手続きには、複数の書類提出が必要となり、記入も複雑に感じる場合があります。
対策
・転職・退職時は早めに確認: 勤務先の担当者やiDeCoの運用管理機関に早めに連絡し、必要な手続きや書類を確認しましょう。
・自動移換を避ける: 転職・退職時には、必ず期限内に移換手続きを行い、資産が自動移換されないように注意しましょう。
・不安なら専門家へ相談: 手続きが複雑で不安な場合は、金融機関のiDeCo相談窓口やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談しましょう。
まとめ:iDeCoのデメリットを理解し、賢く活用しよう
iDeCoには「原則60歳まで引き出せない」という大きな資金拘束のデメリットがありますが、これは老後資金を確実に確保するための仕組みでもあります。また、各種手数料や元本割れリスク、手続きの複雑さも存在します。
しかし、これらのデメリットを事前に理解し、「無理のない掛金設定」「長期・分散・積立投資」「低コスト商品選び」といった対策を講じることで、iDeCoの最大の魅力である強力な税制優遇を最大限に享受し、安心して老後資金を準備できます。
デメリットを上回るメリットがあるiDeCoを賢く活用し、あなたの安心できるセカンドライフを築いていきましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。



