iDeCo
iDeCoとNISAは夫婦で活用すべき?世帯全体の節税と資産形成
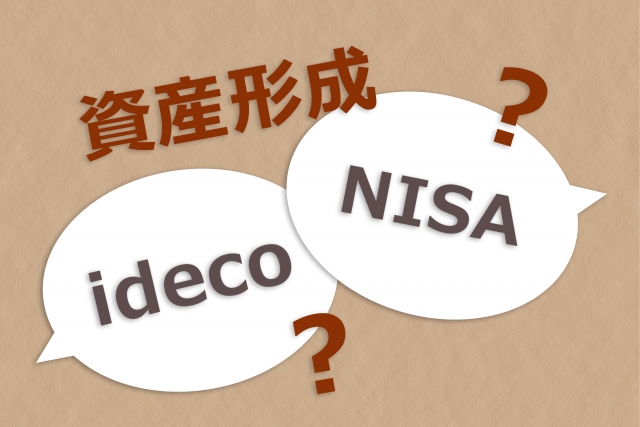
この記事では、夫婦それぞれがiDeCoとNISAに加入するメリットを徹底解説します。世帯全体の非課税枠と所得控除を最大化する方法、そして夫婦の所得バランスに応じた掛金設定の最適化まで、賢い資産形成を目指す夫婦のための具体的な戦略を提案します。
夫婦それぞれがiDeCoとNISAに加入するメリット

iDeCoとNISAは、それぞれ一人につき一口座しか開設できません。だからこそ、夫婦それぞれが加入することで、世帯全体で利用できる税制優遇の「枠」が単純に2倍になります。
世帯全体の非課税枠と所得控除枠を2倍に
iDeCoの所得控除: 夫婦それぞれがiDeCoに加入し掛金を拠出すると、その掛金は拠出した本人の所得から全額控除されます。これにより、夫婦それぞれに所得がある場合は、夫婦それぞれの所得税と住民税が安くなり、世帯全体での節税効果が最大化されます。
iDeCoとNISAの非課税運用枠: 夫婦それぞれがiDeCoとNISAの口座を持つことで、運用益が非課税になる枠が2人分になります。
・iDeCo: 2人分の掛金上限額まで、運用益が非課税に。
・NISA: 2人分の年間合計360万円(つみたて投資枠年間120万円+成長投資枠年間240万円)の枠、生涯1,800万円(合計3,600万円)の非課税枠をフル活用できます。
資産運用のリスク分散と柔軟性の向上
・銘柄・運用方針の分散: 夫婦それぞれが別の運用商品を選ぶことで、資産運用のリスクを分散できます。また、夫婦間で異なるリスク許容度に応じて、それぞれ最適なポートフォリオを組むことも可能です。
・資金ニーズへの対応力向上: NISAは柔軟に引き出し可能ですが、iDeCoは原則60歳まで引き出せません。夫婦それぞれがNISAを持つことで、万が一どちらか一方に大きな資金ニーズが生じた場合でも、必要な分だけNISAから引き出すといった柔軟な対応がしやすくなります。
・iDeCoの受取タイミングの分散: 夫婦それぞれのiDeCoの受取開始時期や受取方法(一時金/年金)をずらすことで、退職所得控除や公的年金等控除を効率的に活用し、老後の税負担を最適化できます。
世帯全体の節税効果を最大化する!夫婦の所得バランスに応じた掛金設定

夫婦でiDeCoとNISAを活用する際、特に重要なのがiDeCoの掛金設定です。所得税の仕組みを理解し、夫婦の所得バランスに応じて掛金を設定することで、世帯全体の節税効果を最大化できます。
夫婦ともに所得がある場合(共働き)
夫婦それぞれに所得があり、所得税・住民税を支払っている場合は、夫婦それぞれがiDeCoに加入し、それぞれの掛金上限額まで拠出することを検討しましょう。
・所得が高い方がiDeCoのメリット大: 所得税は累進課税のため、所得が高い人ほど税率が高くなります。そのため、所得が高い方がiDeCoに拠出する掛金が多いほど、節税効果は大きくなります。
具体例:
・夫:年収800万円(所得税率20%)
・妻:年収500万円(所得税率10%)
・夫婦ともに企業年金がない会社員でiDeCo掛金上限が月2.3万円の場合、それぞれが月2.3万円を拠出すれば、年間合計で2.3万円 × 2人 × (所得税率+10%) の節税効果が得られます。
夫のiDeCo節税額:2.3万円 × 12ヶ月 × (20% + 10%) = 8.28万円
妻のiDeCo節税額:2.3万円 × 12ヶ月 × (10% + 10%) = 5.52万円
世帯合計:約13.8万円の節税
夫婦のどちらか一方に所得がある場合(片働き・専業主婦世帯)
所得がある方がiDeCoに加入し、その掛金を全額所得控除することで節税メリットを享受します。
・所得がある方がiDeCoを優先: 所得がある方が優先してiDeCoに加入し、掛金上限額まで拠出しましょう。
・専業主婦(夫)のiDeCo: 第3号被保険者(専業主婦・夫)もiDeCoに加入でき、掛金上限は月2.3万円です。しかし、専業主婦(夫)自身に所得がない場合、iDeCoの掛金が所得控除になるメリットは受けられません。専業主婦(夫)のiDeCoのメリットは、運用益が非課税になることのみです。
重要: 所得控除による節税は、掛金を拠出した本人の所得に対して行われるため、所得がない専業主婦(夫)の掛金は、配偶者の所得からは控除されません。
NISAは夫婦それぞれが最大限活用
NISAには掛金控除がないため、所得の大小に関わらず、夫婦それぞれが年間合計360万円(つみたて投資枠年間120万円+成長投資枠年間240万円)の非課税枠を最大限活用することが世帯全体の資産形成には効果的です。特に、iDeCoの掛金上限まで拠出した後、残りの余裕資金をNISAに回すのが賢い戦略です。
iDeCoとNISAを組み合わせた具体的な資産形成シミュレーション

夫婦でiDeCoとNISAを併用した場合、単独で利用するよりもどれだけ老後資金を効率的に準備できるか、具体的なシミュレーションで見ていきましょう。
【シミュレーションの前提】
・年齢:30歳
・老後目標年齢:60歳(運用期間30年)
・年収:夫500万円(所得税率10%、住民税率10%とする)
・年収:妻400万円(所得税率5%、住民税率10%とする)
・夫婦それぞれiDeCo掛金:月額2.3万円(年間27.6万円、企業年金なし会社員を想定)
・夫婦それぞれNISA積立:月額10万円(年間120万円、つみたて投資枠を想定)
・運用利回り:年率5%(税引前、あくまで試算であり、将来を保証するものではありません)
夫婦それぞれがiDeCoのみを利用した場合
・世帯年間拠出額:2.3万円 × 2人 × 12ヶ月 = 55.2万円
・世帯年間節税額:
夫のiDeCoによる所得控除:2.3万円 × 12ヶ月 × (10% + 10%) = 5万5,200円
妻のiDeCoによる所得控除:2.3万円 × 12ヶ月 × (5% + 10%) = 4万1,400円
世帯合計約9.66万円の節税
さらに、
・30年後の世帯合計資産額:約1,920万円 × 2人 = 約3,840万円
夫婦それぞれがNISAのみを利用した場合
・世帯年間積立額:10万円 × 2人 × 12ヶ月 = 240万円
・世帯年間節税額:0円(NISAに掛金控除はないため)
・30年後の世帯合計資産額:約8,300万円 × 2人 = 約1億6,600万円
夫婦それぞれがiDeCoとNISAを併用した場合
・世帯年間投資総額:(2.3万円+10万円) × 2人 × 12ヶ月 = 295.2万円
・世帯年間節税額(iDeCoによる所得控除):約9.66万円
・30年後の世帯合計資産額:(約1,920万円 + 約8,300万円) × 2人 = 約2億40万円
このシミュレーションからわかるように、夫婦それぞれがiDeCoとNISAを最大限に活用することで、単身で利用するよりも圧倒的に大きな資産を築ける可能性が高まります。現役時代の節税メリットも享受しつつ、老後資金を大きく増やすことが期待できます。
まとめ:夫婦でiDeCoとNISAを活用し、世帯全体の未来を豊かに
iDeCoとNISAは、それぞれ異なる強みを持つ税制優遇制度ですが、夫婦それぞれがこれらを活用することで、世帯全体の節税効果と資産形成効果を最大限に引き出すことができます。
・iDeCo: 夫婦それぞれが加入し、所得がある人が掛金上限まで拠出することで、所得税・住民税を確実に軽減し、老後資金の確実な土台を築きます。所得のない専業主婦(夫)は所得控除の恩恵は受けられませんが、運用益の非課税メリットは享受できます。
・NISA: 夫婦それぞれが年間合計360万円(つみたて投資枠年間120万円+成長投資枠年間240万円)の非課税枠をフル活用することで、非課税で運用できる資産額を最大化し、老後資金だけでなく、教育資金や住宅資金など多様な目的に備えられます。
夫婦の所得バランスやライフプランに合わせて最適な掛金設定を行い、iDeCoとNISAを賢く併用すること。それが、あなたの世帯の未来を豊かにする「最強の資産形成戦略」となるでしょう。ぜひ今日から夫婦で資産形成について話し合い、一歩を踏み出してみませんか。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています



