火災保険
地震保険の必要性を徹底解説!「万が一」に備えるために

地震保険とは?火災保険との違い

地震保険は「地震保険に関する法律」に基づき運営される公的性格の強い保険制度であり、どの保険会社で加入しても補償内容と保険料が同一である点が特徴です。
地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を直接・間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失による建物や家財の損害を補償します。政府と民間損害保険会社が共同で運営しており、巨大地震でも確実に保険金が支払われる仕組みとなっています。
一方、火災保険では地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・拡大した損害は補償されません。火災保険が火事や風水害などによる損害を補償するのに対し、地震による損害は予測困難で被害規模が膨大になるため、別途地震保険に加入する必要があります。
出典:財務省「地震保険制度の概要」
なぜ地震保険が必要なのか?

日本に住む以上、地震リスクへの備えは欠かせません。ここでは地震保険の必要性を3つの視点から解説します。
地震はいつどこで起きるかわからない
日本周辺では世界の地震の約1割が発生するとされ、国内のどの地域でも大きな地震が起きる可能性があります。
地震調査研究推進本部によると、南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率は「80%程度」(2025年1月時点)とされており、首都直下地震についても30年以内に70%程度の確率で発生すると予測されています。また、日本国内の多くの地域で今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率は26%以上とされており、地震リスクは全国に及んでいます。
過去には発生確率が低いとされた地域でも1983年の日本海中部地震や2005年の福岡県西方沖地震のような大きな地震が発生しており、油断は禁物といえるでしょう。
出典:地震調査研究推進本部「長期評価結果一覧」
火災保険では地震による被害はカバーされない
火災保険では、地震・噴火・津波を原因とする損害は補償対象外となっています。
地震による火災で建物が焼失したり、地震の揺れで建物が倒壊したりした場合でも、地震保険に加入していなければ保険金を受け取ることができません。火災保険に付帯される「地震火災費用」で一部費用が支払われる場合もありますが、本格的な補償には地震保険への加入が不可欠となります。
被災後の生活再建に不可欠な経済的支援
大規模地震が発生した場合、住宅の損壊や家財の損失により生活再建に多額の費用がかかります。
住宅ローンが残っている状態で被災した場合、倒壊した住宅のローン返済と新たな住居費用が二重負担になる可能性も考えられます。地震保険は被災者の生活の安定に寄与することを目的としており、受け取った保険金は住宅の修繕・再建費用や当面の生活費など、使い道が限定されていない点が特徴となっています。
出典:政府広報オンライン「被災後の生活再建を助けるために。もしものときの備え『地震保険』を」
地震保険の補償内容と仕組み

地震保険の補償対象や保険金の支払い方法について、具体的に確認していきましょう。
補償対象となるもの
地震保険の対象は居住用の建物と家財(生活用動産)です。建物には門や塀などの付属物も含まれ、家財には家具、家電、衣類などが該当します。
ただし、以下は補償対象外となります。
・工場や事務所専用の建物など、住居として使用されない建物
・1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう
・通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手
・自動車
損害の程度に応じた4段階の保険金
地震保険では、損害の程度を4段階に区分して保険金を算定する仕組みとなっています。迅速な保険金支払いを可能にするため、実際の修理費ではなく損害区分に応じた定額払いとなっている点が特徴です。
・全損:地震保険金額の100%(時価額が限度)
・大半損:地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)
・小半損:地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)
・一部損:地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)
※損害の程度が一部損に満たない場合は、保険金は支払われません。
出典:財務省「地震保険制度の概要」
総支払限度額の仕組み
地震保険では、1回の地震等で支払われる保険金の総支払限度額が12兆円と定められています。
この限度額は、関東大震災クラスの巨大地震が発生した場合でも対応可能な範囲として設定されたものです。阪神・淡路大震災や東日本大震災といった巨大地震においても、保険金の支払額は総支払限度額内に収まっており、円滑に保険金が支払われた実績があります。
保険金が支払われないケース

地震保険に加入していても、以下の場合は保険金が支払われない点に注意が必要です。
・故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
・地震等が発生した日の翌日から起算して10日経過後に生じた損害
・戦争、内乱などによる損害
・地震等の際の紛失・盗難の場合
・門、塀、垣のみに生じた損害
・損害の程度が一部損に至らない損害
地震保険の保険料と割引制度

地震保険料は建物の所在地(都道府県)と構造によって決まり、割引制度を活用することで負担を軽減できます。
4つの割引制度
地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた4種類の割引制度が設けられています。ただし、複数の条件に該当する場合でも、最も割引率の高い1つのみが適用される点に注意が必要です。
【免震建築物割引】
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」である場合
→ 50%割引
【耐震等級割引】
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」等に基づく耐震等級を有している場合
・耐震等級3:50%割引
・耐震等級2:30%割引
・耐震等級1:10%割引
【耐震診断割引】
地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合
→ 10%割引
【建築年割引】
昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合
→ 10%割引
出典:財務省「地震保険制度の概要」
地震保険料控除
平成19年1月より、地震保険料控除制度が創設されました。
その年に支払った地震保険料に応じて、所得控除を受けることが可能です。控除の限度額は、所得税で最高5万円、住民税で最高2万5千円となっています。会社員は年末調整で、自営業やフリーランスは確定申告で控除の手続きを行えます。
出典:国税庁「地震保険料控除」
地震保険加入時の注意点
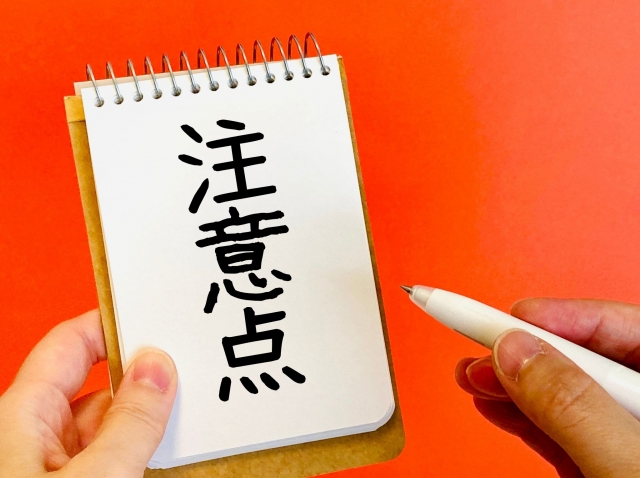
地震保険への加入を検討する際に、押さえておきたいポイントを解説します。
火災保険とセットで加入が必須
地震保険は火災保険に付帯する方式での契約となるため、単独では加入できません。火災保険への加入が前提となります。
すでに火災保険に加入している場合は、契約期間の途中からでも地震保険を追加することが可能です。地震保険は国と民間保険会社が共同で運営しているため、どの保険会社で加入しても補償内容と保険料は同一となっています。
損害のすべてを補償する仕組みではない
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で設定する必要があります。
また、上限額として建物は5,000万円、家財は1,000万円が設けられています。
そのため、地震保険の保険金だけで被災前の状態に完全に建て直すことは難しい場合があります。これは、地震保険が住まいの完全復旧ではなく、被災者の「生活の安定」に寄与することを目的としているためです。
不足分は貯蓄等で備えるほか、火災保険に付帯する「地震上乗せ特約」などを検討することも選択肢となります。この特約は、地震保険の保険金額を火災保険の保険金額の50%に設定した場合に、最大で100%まで補償額を上乗せできる場合があります(一部損は対象外となるケースもあります)。ただし、特約の有無や内容は保険会社によって異なるため、事前の確認をおすすめします。
まとめ
地震は予測が困難であり、一度発生すれば甚大な被害をもたらす可能性があります。火災保険だけでは地震による損害はカバーされないため、被災後の生活再建に備えて地震保険への加入を検討することが重要です。
資産状況や住宅ローンの有無、建物の耐震性能などを考慮したうえで、地震保険の必要性を改めて検討してみてはいかがでしょうか。万が一の事態に備えた経済的準備が、被災後の生活再建を支える力となります。
お金に関する相談はファイナンシャルプランナーの金子賢司まで。日本FP協会の「CFP®認定者検索システム」、またはJ-FLEC(金融経済教育推進機構)のサイトの、J-FLEC認定アドバイザー検索で検索することも可能です。北海道エリアに絞って検索していただくと容易に検索できます。



