医療保険
非正規雇用者・パート主婦のための医療保険|選び方と保険料の節約術

非正規雇用者やパートで働く主婦の方にとって、医療保険の必要性や保険料の負担は、大きな悩みの一つかもしれません。正社員とは異なり、勤務先の福利厚生が薄かったり、ご自身で健康保険に加入する必要があったりするため、万が一の事態に備えるには、より賢い保険選びが求められます。
この記事では、非正規雇用者・パート主婦のための医療保険の選び方を解説します。公的医療保険の仕組みを再確認し、保険料を抑える方法、そして選び方のポイントまで。無理のない保険料で、安心して日々の生活を送るためのヒントを提案します。
非正規雇用者・パート主婦の公的医療保険の仕組み

非正規雇用者やパート主婦の場合、ご自身の働き方によって、加入する公的医療保険が異なります。
健康保険の扶養に入っている場合
対象者:
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)で、配偶者の扶養に入っている場合。
仕組み:
・ご自身で健康保険料を支払う必要はありません。
・医療費の自己負担割合は、原則3割です。
【補足】2025年10月の制度変更:
・19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者(配偶者を除く)の収入要件が130万円未満から150万円未満に引き上げられることが決定しました。
・これは主にお子様の扶養に関する変更で、大学生のアルバイトの就業調整に対応することを目的としています。
・なお、この変更は学生であるか否かは問われません。
自分で健康保険に加入する場合
対象者:
年収が130万円以上で、配偶者の扶養から外れている場合。
仕組み:
・勤務先の健康保険(社会保険)または国民健康保険に加入します。
・健康保険料や国民健康保険料は、ご自身で支払う必要があります。
保険料を抑える方法:無理なく続けられる保険選び

非正規雇用者やパート主婦の場合、収入が限られているため、医療保険の保険料は無理のない範囲で設定することが重要です。
保障内容を厳選する
入院給付金日額を少額に:
入院給付金日額を5,000円など、少額に抑えることで、保険料を安くできます。
不要な特約を外す:
・「あれば安心だから」と付加した特約が、今も本当に必要か見直しましょう。
・公的医療保険(高額療養費制度など)でカバーできる部分や、貯蓄で賄える部分は、特約で備える必要がないかもしれません。
定期型保険を選ぶ
仕組み:
保障期間が決められている保険です。
メリット:
保険料が割安: 終身型に比べて保険料が安く、家計への負担が少ないです。
デメリット:
更新時に保険料が上がる: 更新時に保険料が上がります。
非正規雇用者・パート主婦のための医療保険の選び方
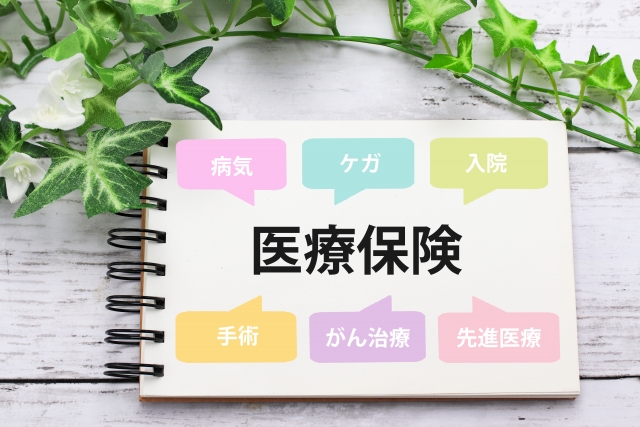
非正規雇用者やパート主婦の医療保険選びには、以下の点が重要です。
公的医療保険との違い
公的医療保険:
・医療費の自己負担割合を、原則3割に抑えてくれます。
・高額療養費制度があります。
民間医療保険:
公的医療保険では賄えない、差額ベッド代や先進医療費、入院中の食事代などをカバーします。
貯蓄とのバランス:
医療費の自己負担分を、貯蓄で賄うことも可能です。ご自身の貯蓄額に応じて、医療保険でどこまで備えるか、そのバランスを考えましょう。
おすすめの保険タイプ
終身医療保険:
・特徴: 一生涯保障が続く保険です。
・メリット: 若いうちに加入すれば、保険料が安価なまま、一生涯の保障を確保できます。
定期型医療保険:
・特徴: 一定期間のみ保障される保険です。
・メリット: 保険料が安く、家計への負担が少ないです。
医療保険の定期型と終身型の違いを知りたい方は以下の記事が参考になります。
定期型と終身型、どっちがいい?医療保険の種類と特徴を比較
まとめ:賢く医療保険を選んで、将来に備える
非正規雇用者やパート主婦の医療保険は、無理のない保険料で、必要な保障を確保することが大切です。
・公的医療保険を最大限に活用し、不足する部分を民間保険で補いましょう。
・保障内容の見直し、定期型保険の活用、不要な特約を外すなど、保険料を安くする方法も検討しましょう。
・終身型と定期型、それぞれのメリット・デメリットを理解し、あなたのライフプランに合わせた最適な医療保険を選びましょう。
限られた収入の中でも、賢い保険選びによって必要な保障を確保することは可能です。ご自身のライフスタイルに合わせた医療保険で、将来への不安を軽減していきましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



