相続
遺留分侵害額請求とは?遺留分の計算方法・請求期限・手続きの流れをわかりやすく解説

遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって法律上保障された最低限の相続分(遺留分)を受け取れなかった相続人が、侵害された金額に相当する金銭の支払いを求める制度です。民法第1046条に基づき、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)が請求権を持ちます。令和元年(2019年)7月の民法改正により、従来の「遺留分減殺請求」から金銭請求へと一本化され、手続きがわかりやすくなりました。ただし、請求には「知った時から1年」「相続開始から10年」という期限があり、期限を過ぎると権利が消滅してしまいます。この記事では、遺留分の計算方法や請求の流れ、注意点まで解説します。
遺留分とは?相続人に保障された最低限の取り分

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人に保障された、相続財産に対する最低限の取り分のことです。
被相続人は遺言によって財産の行き先を自由に決められますが、残された家族の生活保障などの観点から、民法はこの自由に一定の制限を設けています。たとえば「全財産を長男に相続させる」という遺言があっても、配偶者や他の子どもには遺留分として最低限の相続分が認められるのです。
遺留分が認められる人(遺留分権利者)
民法第1042条によると、遺留分を持つのは「兄弟姉妹以外の相続人」と定められています。具体的には以下の方が該当します。
・配偶者(夫または妻)
・子(養子・非嫡出子を含む)
・直系尊属(父母、祖父母)
・代襲相続人(被相続人より先に亡くなった子の子=孫など)
兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、遺言で兄弟姉妹の取り分がゼロとされていても、遺留分侵害額請求はできない点に注意が必要です。
遺留分の割合
遺留分の割合は、民法第1042条第1項により、相続人の構成によって異なります。
・直系尊属のみが相続人の場合:相続財産の3分の1
・それ以外の場合(配偶者や子がいるケース):相続財産の2分の1
相続人が複数いる場合は、上記の割合(総体的遺留分)にそれぞれの法定相続分を掛けて、個人ごとの遺留分(個別的遺留分)を算出します(民法第1042条第2項)。
たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合、総体的遺留分は2分の1です。配偶者の法定相続分は2分の1、子はそれぞれ4分の1となるため、個別的遺留分は以下のようになります。
・配偶者:2分の1 × 2分の1 = 4分の1
・子(1人あたり):2分の1 × 4分の1 = 8分の1
遺留分の計算方法|3ステップでわかる算出手順
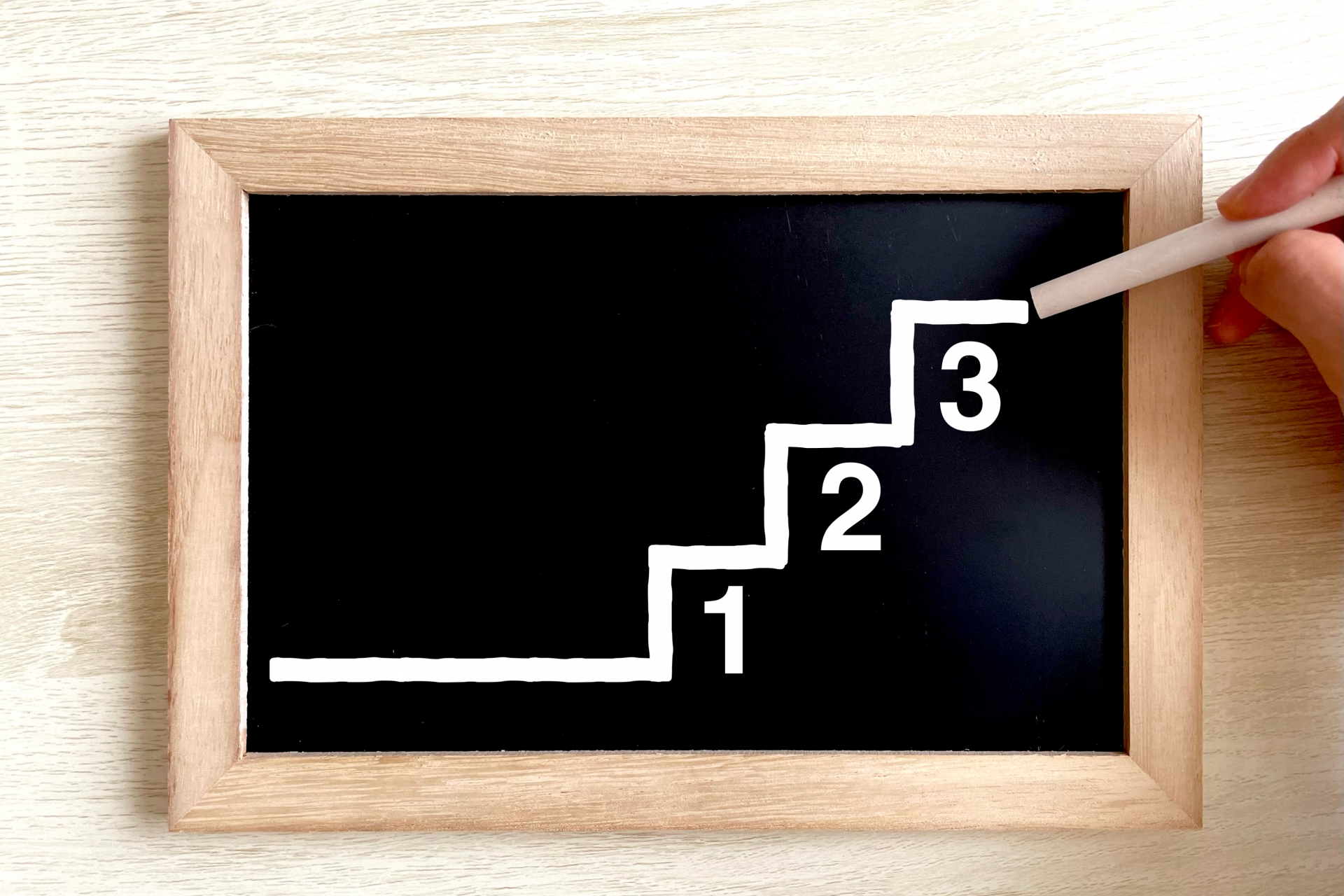
遺留分侵害額の計算は、民法第1043条・第1046条に基づき、基礎となる財産額の算定から始まります。
ステップ1:遺留分算定の基礎となる財産額を求める
遺留分を計算するための財産額は、民法第1043条第1項により次の計算式で算出できます。
遺留分算定の基礎財産 = 相続開始時の財産 + 贈与した財産 − 債務の全額
ここで加算される「贈与した財産」には、範囲に関するルールがあります(民法第1044条)。
・相続人以外への贈与:相続開始前1年以内のもの
・相続人への贈与(特別受益に該当するもの):相続開始前10年以内のもの
・当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合は、上記期間より前のものも含まれる
令和元年の民法改正により、相続人への贈与の算入期間が10年間に限定されました。改正前は期間の制限がなかったため、何十年も前の贈与まで遡って計算に含められるケースがありましたが、現在は期間が区切られています。
ステップ2:個別的遺留分を計算する
ステップ1で求めた基礎財産額に、先述の遺留分割合を掛けて個別的遺留分を算出します。
個別的遺留分 = 遺留分算定の基礎財産 × 総体的遺留分割合 × 法定相続分
【具体例】
被相続人の相続開始時の財産が8,000万円、相続人への生前贈与(10年以内)が2,000万円、債務が500万円の場合で、相続人が配偶者と子2人のケースを考えてみましょう。
・基礎財産額:8,000万円 + 2,000万円 − 500万円 = 9,500万円
・配偶者の遺留分:9,500万円 × 2分の1 × 2分の1 = 2,375万円
・子1人あたりの遺留分:9,500万円 × 2分の1 × 4分の1 = 1,187.5万円
ステップ3:遺留分侵害額を算出する
民法第1046条第2項により、遺留分侵害額は次のように求めます。
遺留分侵害額 = 遺留分 − 遺留分権利者が受けた遺贈・贈与の価額 − 遺産分割で取得すべき財産の価額 + 遺留分権利者が承継する債務の額
上記の計算の結果、遺留分侵害額がプラスになる場合に請求が可能です。
遺留分侵害額請求の手続き|意思表示から調停・訴訟までの流れ

遺留分侵害額請求は、意思表示から始まり、協議・調停・訴訟の順に段階的に進みます。
手順1:内容証明郵便で意思表示をする
遺留分侵害額請求は、まず相手方(受遺者や受贈者)に対して「遺留分侵害額を請求する」という意思表示を行うことから始まります。法律上、意思表示の方法に特別な決まりはありませんが、内容証明郵便で行うのが一般的です。
内容証明郵便を利用すると、「いつ・誰が・誰に・どのような内容を送ったか」の記録が残ります。後述する時効(1年)との関係で、期限内に請求した事実を証明できる手段として重要な役割を果たします。
手順2:当事者間で協議する
意思表示の後は、まず当事者間での話し合い(協議)を行います。金額や支払い方法、支払い時期などについて合意が得られれば、合意書を作成して解決です。
手順3:家庭裁判所の調停を利用する
当事者間の協議で解決しない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てることが可能です。裁判所によると、調停では裁判官1名と調停委員2名で構成される調停委員会が、双方の事情を聴いたうえで解決案の提示や助言を行い、合意形成を促します。
調停の申立てに必要な費用は以下のとおりです。
・収入印紙:1,200円
・連絡用の郵便切手(裁判所によって異なる)
注意すべき点として、調停を申し立てただけでは遺留分侵害額請求の「意思表示」とはなりません。調停とは別に、内容証明郵便等で請求の意思表示を行う必要があります。
手順4:訴訟(裁判)を提起する
調停でも合意に至らない場合は、地方裁判所または簡易裁判所に民事訴訟を提起します。遺留分に関する問題は「調停前置」とされており、原則として訴訟の前に調停を経る必要があります(家事事件手続法第257条第1項)。
訴訟を起こす裁判所は、請求額が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所が管轄となります。
遺留分侵害額請求の期限(時効)に注意

遺留分侵害額請求権には期限があり、期限を過ぎると権利が消滅するため、行使のタイミングが重要です。
民法第1048条により、遺留分侵害額請求権は以下のいずれかの期間が経過すると行使できなくなります。
・相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年(消滅時効)
・相続開始の時から10年(除斥期間)
遺留分の侵害に気づいた場合は、早めに内容証明郵便で意思表示を行い、時効の完成を防ぐことが重要です。
また、遺留分侵害額請求権を行使すると、相手方に対する金銭債権が発生します。この金銭債権は、行使できることを知った日から5年、または行使できる日から10年で時効にかかる点にも留意が必要です。
令和元年の民法改正で変わったポイント

令和元年(2019年)7月1日施行の民法改正により、遺留分制度に重要な変更がありました。
改正前:遺留分減殺請求(現物返還が原則)
改正前の制度では「遺留分減殺請求」と呼ばれ、請求が認められると遺贈や贈与の効力が遺留分を侵害する限度で失われ、目的財産が共有状態になっていました。たとえば不動産が遺留分の対象になると、受遺者と遺留分権利者の共有となり、不動産の処分や利用に制約が生じるという問題がありました。
改正後:遺留分侵害額請求(金銭請求に一本化)
改正後は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する制度に変わりました(民法第1046条第1項)。これにより、相続財産が共有状態になることを防ぎ、金銭で清算できるようになっています。
なお、請求を受けた側がすぐに金銭を用意できない場合は、裁判所に申し立てることで支払期限の猶予を受けられる制度も設けられています(民法第1047条第5項)。
出典:法務省「民法(相続法)改正 相続に関するルールが大きく変わります」
遺留分侵害額請求ができないケース

遺留分が認められる相続人であっても、請求ができない場合があります。主なケースを確認しておきましょう。
兄弟姉妹は遺留分を持たない
前述のとおり、民法第1042条により兄弟姉妹には遺留分が認められていません。兄弟姉妹が相続人となるケース(被相続人に子も直系尊属もいない場合)では、遺言で兄弟姉妹の取り分がゼロとされていても請求はできないことになります。
相続放棄をした場合
相続放棄をした方は、はじめから相続人でなかったものとみなされるため、遺留分侵害額請求を行うことはできません。
遺留分の放棄をした場合
相続開始前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することも可能です(民法第1049条)。遺留分を放棄した場合、その方は遺留分侵害額請求権を行使できません。ただし、ある相続人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分が増えることはありません。
時効・除斥期間を過ぎた場合
前述のとおり、知った時から1年、または相続開始から10年を経過すると、権利が消滅します。
遺留分侵害額請求を行う際の注意点

実際に遺留分侵害額請求を検討する際に、押さえておきたいポイントをまとめます。
不動産の評価方法で金額が変わる
遺産に不動産が含まれる場合、その評価方法によって遺留分の金額が変動する可能性があります。相続税評価額(路線価等)を用いるか、時価(実勢価格)を用いるかで結果が異なるため、不動産の評価をめぐって争いになるケースも少なくありません。
請求を受けた側にも猶予制度がある
遺留分侵害額を請求された側が金銭をすぐに準備できない場合は、裁判所に対して支払期限の猶予を求めることが可能です(民法第1047条第5項)。生活資金や事業資金が遺産の多くを占めるケースなどでは、この猶予制度が活用されることがあります。
遺留分を考慮した遺言書の作成が重要
遺留分侵害額請求は相続トラブルの代表的な原因の一つです。遺言書を作成する際に、あらかじめ各相続人の遺留分を考慮した内容にしておくことで、相続発生後の紛争を未然に防げる可能性があります。
専門家への相談を早めに検討する
遺留分の計算は、不動産の評価や生前贈与の把握など専門的な知識を要する場面が多いため、弁護士や税理士への相談を早い段階で検討することが望ましいといえます。特に時効が1年と短いため、遺留分の侵害に気づいた段階で速やかに行動を起こすことが大切です。
まとめ:遺留分侵害額請求のポイント
遺留分侵害額請求について、押さえておくべきポイントを整理しておきましょう。
・遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障された最低限の相続分
・遺留分の割合は、直系尊属のみの場合は3分の1、それ以外は2分の1
・令和元年の民法改正により、遺留分の請求は金銭で行う制度に変更された
・請求期限は「知った時から1年」「相続開始から10年」のいずれか早い方
・手続きは内容証明郵便での意思表示 → 協議 → 調停 → 訴訟の順に進む
・遺留分の計算には不動産評価や生前贈与の把握が必要なため、専門家への相談が有効
遺留分に関する問題は、感情的な対立を伴いやすく、解決まで長期化するケースもあります。遺言書の作成段階から遺留分への配慮を意識しておくことが、円満な相続につながるでしょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
金子賢司へのライティング・監修依頼はこちらから。ポートフォリオもご確認ください。



