資産運用
過熱相場での投資判断|注意すべきリスクと分散投資の考え方
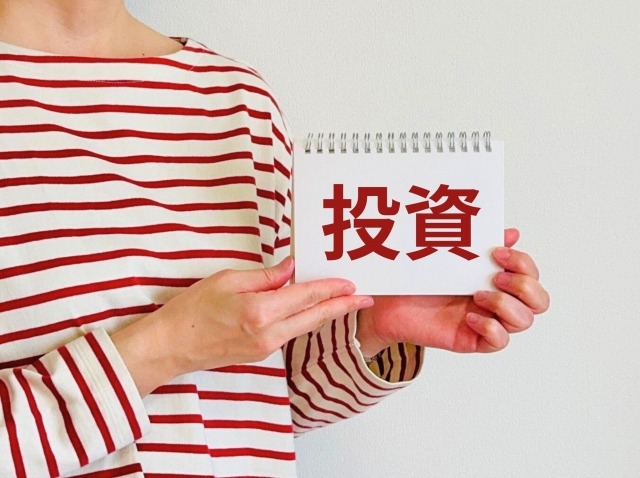
2025年の日本株市場は35年ぶりの高値更新を記録し、相場の過熱感が指摘されています。こうした環境下で資産運用を検討する際、どのような点に注意すべきなのでしょうか。本記事では、過熱相場におけるリスクの考え方、分散投資の基本、各投資商品の特性と留意点について解説します。
2025年の株式市場と過熱感の現状

2025年の日本株市場は、日経平均株価が年末に4万5000円を目指す展開が予想されており、基調としては強い相場環境が続いています。2024年末の日経平均株価は3万9894円と、1989年のバブル期を超える35年ぶりの高値更新を記録しました。
企業業績の好調さや自社株買いの増加、ROE向上施策の本格化など、相場を支える要因は複数存在しているものの、短期間での急騰による過熱感も指摘されています。特に8月には日経平均が急騰し、その後の調整局面を経験したことから、投資家の中には慎重な姿勢を取る方も増えてきました。
こうした市場環境では、適切なリスク管理を行いながら、慎重に投資判断を行うことが資産形成において極めて重要となります。
過熱相場におけるリスク管理の重要性

相場が過熱している局面では、以下のようなリスクが高まる傾向にあります。
・急激な調整局面のリスク
短期間で上昇した相場は、何らかのきっかけで急落する可能性があります。2024年8月にも、7月の急上昇後に大きな調整が発生した事例が確認されています。
・外国人投資家の動向に左右されるリスク
個人投資家の買いが限定的な高値圏では、外国人投資家の売りが相場の急落要因となる可能性があるでしょう。
・地政学リスクや政策変更のリスク
トランプ政権の関税政策や国内政治の不安定さなど、不確実性の高い要因が多数存在しています。
こうしたリスクに対処するためには、分散投資によるリスク低減が基本戦略となります。株式のみに集中投資するのではなく、値動きの異なる複数の資産に資金を振り分けることで、ポートフォリオ全体の安定性を高めることが可能です。
過熱相場での投資判断における検討事項

過熱した相場環境において投資判断を行う際は、リスク管理を重視した慎重な姿勢が求められます。ここでは、資産形成を検討する際の主な選択肢とその特性、注意点について解説いたします。
バランス型投資信託による資産分散の考え方
バランス型投資信託は、株式・債券・REITなど複数の資産クラスに分散投資できる投資信託です。相場の過熱局面では、単一の資産クラスに偏らない運用が検討されることがあります。
投資信託は、投資対象を分散することで価格変動を抑え、リスクを軽減する効果が期待できます。また、運用の専門家が資産配分を調整するため、個人投資家が市場環境に応じて細かく売買する手間を省けます。
・資産の分散(株式、債券、REITなどへの配分)
・地域の分散(国内と海外、先進国と新興国の組み合わせ)
・時間の分散(積立投資による購入タイミングの分散)
これら3つの分散を組み合わせることで、リスクをコントロールしながら長期的な資産形成を検討することができます。ただし、バランス型投資信託にも信託報酬などのコストが発生する点や、市場環境によっては期待通りの成果が得られない可能性がある点には留意が必要です。
REIT(不動産投資信託)の特性と留意点
REIT(Real Estate Investment Trust)は、投資家から集めた資金を不動産に投資し、賃貸収入や売却益を分配する投資信託です。日本のREITは「J-REIT」と呼ばれ、証券取引所に上場しているため株式と同様に売買できます。
REITの主な特徴は以下の通りです。
・相対的に高い分配金利回り
REITは配当可能利益の90%超を分配することで法人税が免除される仕組みになっており、相対的に分配金利回りが高くなる傾向があります。不動産賃貸料は定期的に入ってくることが多いため、比較的安定した分配金につながる可能性があります。
・少額からの不動産投資
実物不動産への投資には多額の資金が必要ですが、REITであれば少額から実質的な不動産投資が可能となります。
・分散効果によるリスク低減の可能性
REITは複数の不動産に投資しているため、特定の物件やテナントのリスクを分散できます。株式や債券とは異なるリスク・リターン特性を持つため、ポートフォリオに組み入れることで全体の分散効果が期待できます。
ただし、REITには価格変動リスクや金利変動リスク、不動産市況の影響を受けるリスクがあります。投資する際は、保有物件の稼働率や用途、地域などを確認し、リスクを理解したうえで判断することが重要です。
債券・債券型投資信託の特性とリスク
債券投資は、株式投資と比較して値動きが相対的に小さい傾向があり、安定した運用を検討する際の選択肢となります。過熱した株式相場においては、債券を組み合わせることでポートフォリオ全体のリスクを抑える効果が期待できます。
債券投資の主な特徴は以下の通りです。
・満期時の元本返済
債券は満期時に額面金額が償還されることが約束されています。ただし発行体の信用リスク(倒産等のリスク)は存在するため、発行体の信用力を確認することが重要です。
・定期的な利子収入
保有期間中は定期的に利子を受け取ることができるため、比較的安定したインカムゲインが期待できます。
・換金性の確保
満期を待たずとも、市場で売却することで現金化が可能となります。
債券にも信用リスク(発行体の倒産リスク)、価格変動リスク(金利変動による価格変動)、為替変動リスク(外国債券の場合)などのリスクが存在します。高金利の債券は相応のリスクを伴うことが多いため、金利が高い理由を理解することが必要です。
個人投資家の場合、複数の債券に分散投資できる債券型投資信託を活用することで、少額から債券投資の特性を活かした運用を検討できます。ただし、投資信託には信託報酬などのコストが発生する点には留意が必要です。
インデックス型投資信託の特性
インデックス型投資信託は、日経平均株価やTOPIX、S&P500などの株価指数に連動する運用成果を目指す投資信託です。個別銘柄を選択するリスクを避け、市場全体に投資できることが特徴となります。
過熱相場では個別銘柄の選別が難しくなる傾向がありますが、インデックス型投資信託は市場全体の動きを反映するため、銘柄選択のリスクを軽減できます。また、信託報酬が相対的に低いことも長期投資において考慮すべきポイントです。
・国内株式インデックスファンド(日経平均、TOPIXなど)
・海外株式インデックスファンド(S&P500、全世界株式など)
・債券インデックスファンド
これらは、グローバルな分散投資を実現する選択肢の一つとなります。ただし、市場全体の下落局面ではインデックスファンドも連動して下落するため、この点には注意が必要です。
高配当株式投資信託の特性と注意点
高配当株式に投資する投資信託は、定期的な配当収入を重視した運用を行います。相場が調整局面に入った場合でも、配当収入があることで一定の収益を得られる可能性があります。
日本国内では、メガバンクや海運会社などが継続的な株主還元策を強化しており、配当利回りが相対的に高い水準にある銘柄も存在しています。高配当株式投資信託では、こうした銘柄に分散投資することで、配当収入とキャピタルゲインの両面から収益を狙うことが可能です。
ただし、配当利回りが高い銘柄の中には、業績悪化により株価が下落している場合もあります。単純に利回りの高さだけで判断するのではなく、企業の業績や配当の持続可能性を確認することが重要となります。また、高配当銘柄は景気敏感株が多く含まれる傾向があるため、経済環境の変化による影響を受けやすい点にも留意が必要です。
過熱相場における投資判断で考慮すべきポイント

長期・積立・分散投資の考え方
過熱相場では短期的な値動きに一喜一憂しがちですが、長期的な視点を持つことが重要とされています。市場のタイミングを完璧に予測することは困難なため、積立投資により時間を分散させることで、高値掴みのリスクを軽減できる可能性があります。
金融庁も推奨する「長期・積立・分散投資」は、相場環境に左右されにくい資産形成の基本的な考え方の一つです。つみたてNISAなどの非課税制度を活用しながら、コツコツと資産を積み上げていく方法を検討することも選択肢となります。
リスク許容度に応じた資産配分
投資家それぞれの年齢、収入、資産状況、投資経験によって、適切なリスク許容度は異なります。若年層であれば長期的な運用期間があるため、株式の比率を高めることも選択肢の一つとなります。一方、定年退職が近い世代では、債券やREITの比率を高めて安定運用を重視することが適切な場合もあります。
自身のリスク許容度を正確に把握し、それに応じた資産配分を行うことで、精神的な負担を軽減しながら投資を継続することが可能となります。ただし、リスク許容度は個人の状況により大きく異なるため、一概に「これが正解」という資産配分は存在しない点に留意が必要です。
定期的なポートフォリオ見直しの考え方
市場環境の変化により、当初設定した資産配分が崩れることがあります。特に過熱相場では株式の比率が予想以上に高まる可能性があります。定期的にポートフォリオの見直し(リバランス)を行い、適切な資産配分を維持することが重要とされています。
リバランスにより、値上がりした資産を一部売却し、相対的に値下がりした資産を買い増すことで、「高く売って安く買う」という投資の基本原則を実践できる可能性があります。ただし、リバランスには取引コストや税金が発生する場合があるため、これらのコストと効果を比較検討することが必要です。
まとめ|慎重な投資判断の重要性
2025年の市場は基調として強い展開が予想されるものの、短期的な過熱感や不確実性も存在しています。こうした環境下では、慎重な投資判断とリスク管理が何より重要となります。
投資判断を行う際は、バランス型投資信託、REIT、債券型投資信託、インデックスファンド、高配当株式投資信託など、値動きの異なる複数の資産クラスの特性とリスクを理解したうえで、自身の投資目的や状況に適した選択を行うことが求められます。
特に過熱相場においては、以下の点に留意することが重要です。
・短期的な値動きに惑わされない長期的な視点の維持
・自身のリスク許容度を正確に把握した資産配分
・定期的なポートフォリオの見直し(リバランス)の実施
・過度な集中投資を避ける分散投資の徹底
投資にはリスクが伴い、元本が保証されるものではありません。各商品の特性やリスクを十分に理解し、ご自身の判断と責任において投資判断を行っていただくことが必要です。必要に応じて、ファイナンシャルプランナーなどの専門家への相談も検討されることをお勧めいたします。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。
金子賢司へのライティング・監修依頼はこちらから。ポートフォリオもご確認ください。



