自動車保険
通勤での車利用は保険料が上がる?安くするコツと選び方を解説

自動車保険は車の使用目的によって保険料が変わります。特に通勤・通学使用は利用頻度が高く、統計的に事故の重大化リスクが意識されやすいため、保険料が上がることがあります。本記事では、頻度基準の正しい理解、公的統計に基づくリスクの見方、保険料を安くする具体的なコツ、そして告知義務の注意点を解説します。
自動車保険の「使用目的」とは?なぜ通勤で保険料が上がるのか

【概要】契約時に申告する使用目的で保険料区分が決まります。距離ではなく利用頻度が判断材料となるのが一般的です。
自動車保険では契約時に車の「使用目的」を申告します。主な区分は次の3つです。
・日常・レジャー使用(買い物や休日利用が中心)
・通勤・通学使用(日常的に通勤・通学で使用)
・業務使用(営業・配達など業務で反復使用)
判定は頻度に基づくのが一般的で、多くの保険会社で「年間を通じて平均月15日以上」の利用が通勤・通学使用の目安とされています(具体の基準や名称は保険会社により異なります)。利用頻度が上がるほど、走行機会の増加や混雑時間帯の走行などによって事故発生・重大化のリスクが高まり、保険料に反映される傾向があります。
通勤での事故リスクはどれくらい?公的統計から見る実態

【概要】「朝の通勤時間帯が特に多い」という断定的な統計は確認できません。一方で、薄暮時間帯(17〜19時台)に交通死亡事故が多いことを警察庁は継続的に示しています。
警察庁は白書等で、最近5年間の時間帯別死亡事故件数は17時台〜19時台に多いとしています。日の入り前後で視界が悪化し、歩行者や自転車の発見遅れが生じやすいことなどが背景です。詳しくは以下の公的資料をご参照ください。
・警察庁「交通安全のための情報|薄暮時間帯における交通事故防止」
・警察白書(令和5年版)「時間帯別死亡事故件数:最近5年間は17〜19時台に多い」
したがって、「通勤=朝が特に危険」という単純化は適切ではありません。帰宅ラッシュと薄暮の重なる夕方以降に重大事故リスクが高まる点を念頭に、ヘッドライトの早め点灯や速度抑制などの防衛運転を心がけましょう(前照灯活用の留意点は警察庁の解説も参照)。
通勤での車利用でも保険料を安くする4つのコツ

【概要】通勤・通学使用でも、契約条件と割引活用で保険料の最適化が可能です。
・コツ1:運転者の範囲・年齢条件を見直す
運転する人を実態に合わせて限定(本人限定・配偶者限定など)し、年齢条件を適正化すると保険料の無駄を抑えられます。
・コツ2:年間走行距離に応じた割引を活用する
実際の走行距離区分を確認し、短距離であれば低い区分を選ぶことで保険料が下がる場合があります。
・コツ3:インターネット割引を利用する
申込・継続をオンラインで完結すると割引が適用される保険会社が多く、手続きも効率化できます。
・コツ4:複数契約割引や安全装置割引を活用する
火災保険等とのセットや、自動ブレーキ等の先進安全装置搭載で割引が適用される場合があります。車両の安全装備や家計全体の契約を棚卸ししましょう。
使用目的の変更を怠るリスクと「告知義務」の注意点
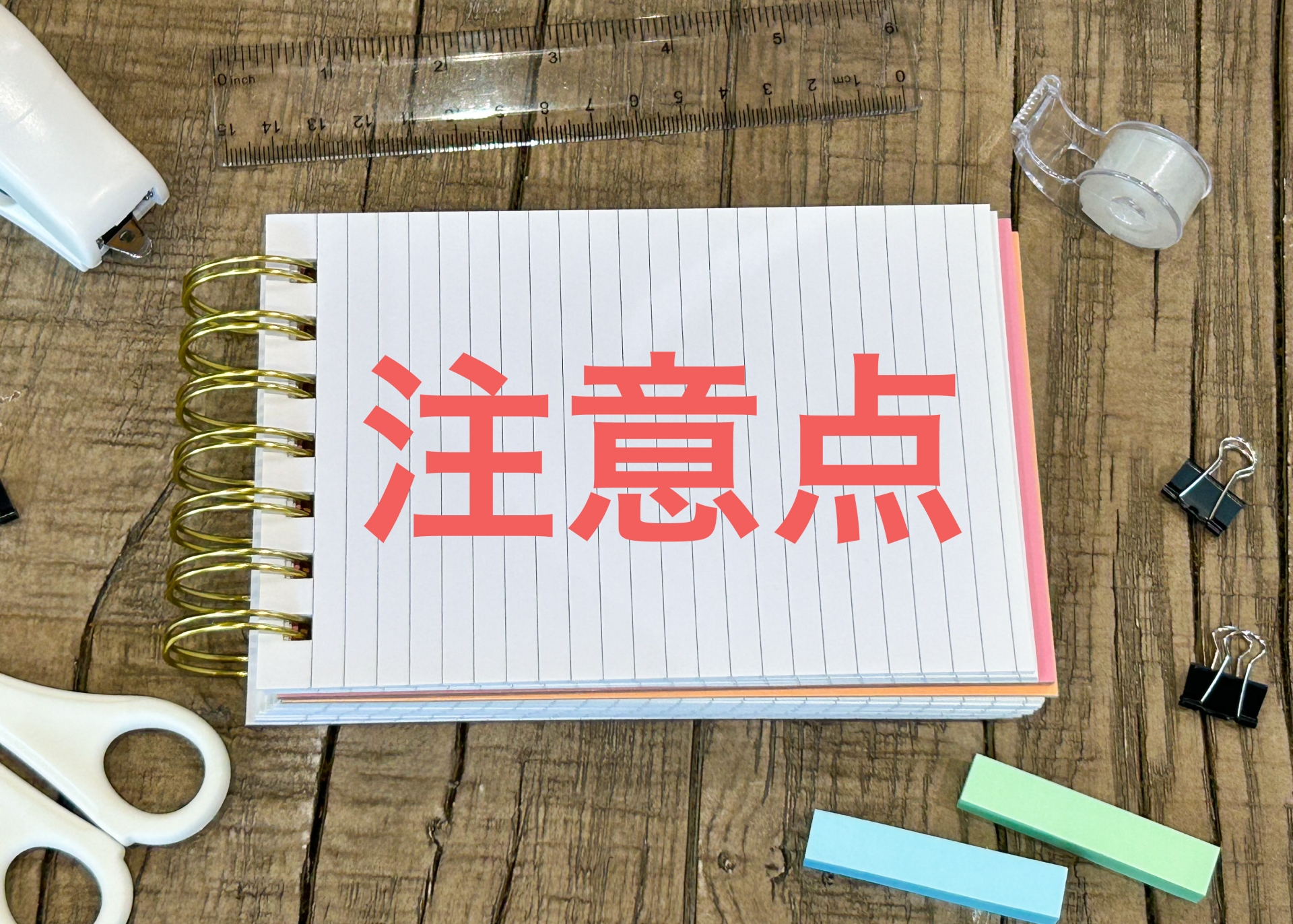
【概要】使用目的が変わったのに連絡しないと、告知義務違反に問われ、保険金が支払われないリスクがあります。
単身赴任や転職などで、当初の日常・レジャー使用から通勤・通学使用に変わった場合は、速やかに保険会社へ連絡しましょう。金融庁は、保険契約における告知義務について、事実と異なる告知を行うと保険金が支払われないことがある旨を周知しています(金融庁|保険商品等に関する利用者からの相談事例)。また、質問応答義務(保険法)への適切な対応が求められる旨は監督指針にも明記されています(金融庁|保険会社向けの総合的な監督指針)。
まとめ|賢い保険選びで通勤コストを最適化
【概要】頻度基準に沿って使用目的を正しく申告し、割引や条件見直しで通勤コストを最適化しましょう。
通勤で車を利用しても、契約条件の適正化と割引活用で保険料は抑えられます。使用目的は頻度で判断されるのが一般的で、実態に合わない契約は告知義務違反のリスクがあります。公的統計で示される薄暮時間帯の重大事故リスクも意識し、前照灯の早め点灯や安全運転と併せて、安心できる保険選びを行いましょう。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



