FPによる貸金業法学習記録
貸金業登録の要件とは?無登録営業の罰則も解説
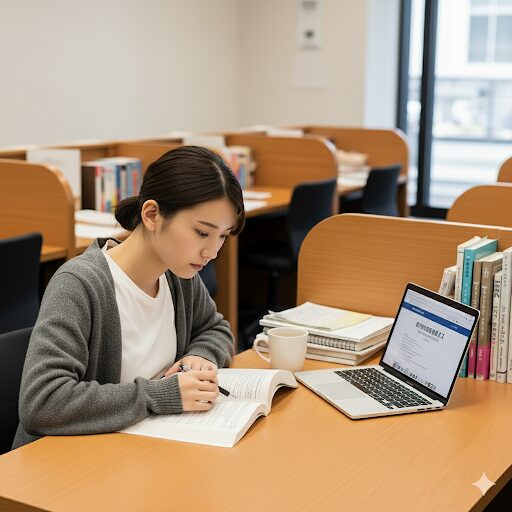
この記事は、CFPが貸金業務取扱主任者を目指すために、自身の勉強記録として残すブログです。
※この記事は個人的な学習記録であり、その内容の正確性を保証するものではありません。実際の業務や判断においては、必ず最新の法令や専門家の助言を確認してください。
貸金業登録の要件とは?無登録営業の罰則も解説
貸金業を適法に営むためには、国や都道府県への「登録」が不可欠。この登録制度は、貸金業の健全な運営を確保し、利用者である借り手を保護するための重要な仕組みとなっている。
貸金業の登録:なぜ必要なのか?
貸金業の登録は、貸金業法第3条に基づき定められている。この登録制度があることで、貸金業者の信頼性が担保され、利用者は安心して取引を行うことができる。また、登録された業者には法律で定められた様々な義務が課せられ、利用者保護が徹底される。
・登録を行う行政庁
貸金業の登録を行う行政庁は、営業所の所在地によって異なる。
・2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合:内閣総理大臣(財務局長)
・1つの都道府県のみに営業所を設置する場合:営業所の所在地を管轄する都道府県知事
・登録の申請先
登録の申請は、内閣総理大臣の登録を受ける場合は財務局に、都道府県知事の登録を受ける場合は各都道府県の貸金業担当課に行う。なお、申請書は日本貸金業協会の支部を通して提出することも可能。
貸金業の登録要件と申請手続き
貸金業の登録を受けるためには、法律で定められた厳格な要件を満たす必要がある。これらの要件は、事業者が適正な業務遂行能力を持つかを行政庁が判断するための重要な基準となる。
・登録申請書に記載すべき内容
登録申請書には、以下のような事項を正確に記載しなければならない。
・商号、名称、氏名
・住所、本店・支店などの営業所の名称と所在地
・資本金、純資産額
・役員や政令で定める使用人の氏名、役職名、職務内容
・貸付け業務を行う者、業務取扱主任者の氏名
・登録申請時に添付する書類
登録申請時には、申請書の記載内容を証明するための書類を添付する。代表的な書類には、役員や政令で定める使用人の経歴書、住民票、貸金業業務取扱主任者登録証明書の写し、定款、会社の登記事項証明書、直近の貸借対照表、損益計算書などがある。
・登録拒否要件
申請者やその役員、政令で定める使用人が、以下のいずれかに該当する場合、登録は拒否される。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えてから5年を経過しない者
・貸金業法等に違反し、罰金刑に処せられてから5年を経過しない者
・暴力団員等
・心身の故障により、貸金業を適正に行うことができない者
・書類の不備があるときも登録を拒否される
登録申請書や添付書類に不備があった場合、行政庁は登録を拒否することがある。これは、申請者が法律で定められた手続きを正確に行う能力がないと判断されるため。
・役員、政令で定める使用人とは
「役員」とは取締役や監査役を指す。「政令で定める使用人」とは、貸金業の業務を行う営業所の代表者や、一定の権限を持つ従業員を指し、これらの人物も登録要件の審査対象となる。
・登録の有効期間と手数料
貸金業の登録には有効期間があり、3年ごとに更新が必要。新規登録および更新登録の申請手数料は、150,000円と定められている。
無登録営業と罰則:登録の重要性
貸金業登録の最大の目的の一つは、無登録で貸金業を営む無登録営業者を排除すること。登録は、行政庁が事業者の適格性を審査した証明であり、この登録を他人に貸す名義貸しも法律で厳しく禁止されている。
・無登録営業とは?
貸金業の登録を受けていないにもかかわらず、反復継続の意思をもって貸付けを行う行為。これは、法律違反であり、利用者保護の観点から最も危険な行為とされている。
・無登録営業をしたときの罰則
無登録で貸金業を営んだ場合、貸金業法に基づき「10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金、またはその両方」が科せられる。この重い罰則は、無登録営業の危険性を社会に周知させるためのもの。



