FPによる貸金業法学習記録
貸金業法における契約内容の変更と書面交付義務
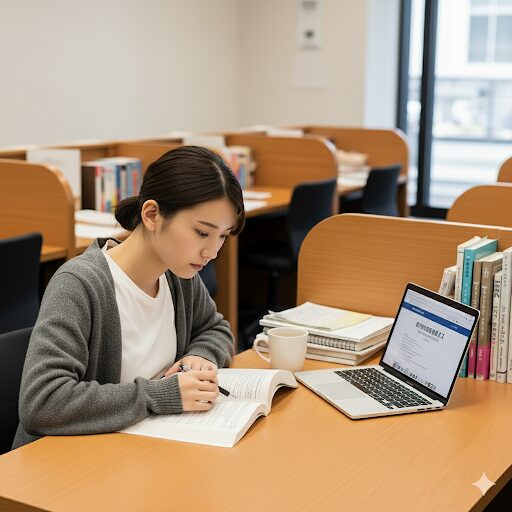
この記事は、CFPが2025年11月16日実施の貸金業務取扱主任者を目指すために、自身の勉強記録として残すブログです。
※本記事は筆者の学習記録であり、その内容の正確性には万全を期しておりますが、法令改正等により変更される可能性があります。実際の業務や判断においては、必ず最新の法令や専門家の助言を確認してください。
貸金業者が金銭の貸付けに係る契約(保証契約を含む)を締結する際、債務者等へ交付する契約締結時の書面は、極めて重要な意味を持つ。この書面には、貸付条件等の重要事項が詳細に記載されており、債務者等はこれを基に契約内容を正確に把握する。
本稿では、この重要事項に変更が生じた場合の、貸金業法上の対応、特に書面の再交付義務について解説する。
契約締結時書面の重要事項に変更があった場合の原則
貸金業者は、契約締結時の書面に記載した事項のうち、重要事項にあたるものに変更が生じた場合、原則として、遅滞なく、その変更内容を記載した書面を当該契約の相手方(債務者等)に再度交付しなければならない。
これは、契約内容が変更された場合であっても、債務者等にその内容を正確に伝え、保護を図るための重要な規定である。具体的に書面の再交付が必要なケースとしては、例えば返済の方式(一括返済から分割返済への変更など)を変更した場合が挙げられる。
書面の再交付が不要となる特例
上記の原則に対し、例外的に書面の再交付が不要となる場合が、貸金業法施行規則に規定されている。これは、契約の相手方の利益となる変更や、相手方の利益の保護に支障を生じない変更に限定される。
再交付が不要となる可能性がある変更事項
重要事項が変更された場合であっても、以下の変更が「契約の相手方の利益となる変更」または「相手方の利益の保護に支障を生じない変更」に該当するときは、書面の再交付が不要となる場合がある。
・貸付利率
・利息の計算方法
・債務者が負担すべき元本・利息以外の金銭(例:事務手数料、保証料など)
・違約金を含む賠償額の予定に関する定めやその内容
・期日前の返済の可否やその内容
ただし、ここで留意すべきは、これらの事項の変更がすべて再交付不要となるわけではなく、あくまで変更の具体的な内容が債務者の利益を害さないと判断される場合に限られるという点である。例えば、貸付利率を引き下げる変更などは、一般に債務者の利益となるため、再交付が不要となる特例に該当し得る。
書面の交付が必要なケースの例(原則として再交付が必要な重要事項)
前述の特例に該当しない、すなわち債務者等の利益の保護のために必ず書面の交付が必要とされる変更の具体例は、以下の通りである。これらの事項は、債務者の返済計画や契約履行に重大な影響を及ぼすため、変更時には原則として遅滞なく書面を再交付しなければならない。
・返済の方式
・返済の方法および返済を受ける場所
・各回の返済期日および返済金額
・契約に基づく債権につき、物的担保を提供させるときは、その担保の内容(担保物件の種類、所在地など)
・保証契約を締結するときは、保証人の商号や名称、氏名、住所
極度方式基本契約における極度額の変更
極度方式基本契約(カードローン契約など)においては、極度額(貸付限度額を含む)を変更するときも、原則として書面の交付が必要である。
しかし、極度額の変更であっても、以下の場合は相手方の利益の保護に支障を生じることがないため、契約変更時の書面の交付は不要となる。
・極度額を引き下げるとき
・極度額を引き下げた後に、もとの額を上回らない額まで引き上げるとき
極度額の引き下げは、債務者が借り過ぎるリスクを低減させるため、利益の保護に支障がないと判断される。また、引き下げ後の再引き上げも、当初の契約の範囲内であれば同様の扱いとなる。
保証契約の変更時における書面交付義務
貸付けに係る契約内容の変更時と同様に、保証契約の変更時にも、原則として書面の再交付が必要となる。
特に、保証契約においては、以下の重要事項に変更が生じた場合も、原則として書面の再交付が必要である。
・保証期間
・保証金額
・保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する(連帯保証人)は、その趣旨やその内容
ただし、これらの保証契約の重要事項に変更を加える場合であっても、その変更が契約の相手方(保証人)の利益となる変更であるときは、貸付契約と同様に書面の交付は不要となる。



