就業不能保険
自営業・フリーランス向け就業不能保険|選び方と保障内容のポイント

就業不能保険とは?自営業・フリーランスが直面するリスク

就業不能保険とは、病気やケガで長期間働けなくなった場合に、一定期間または完治まで毎月の生活費を補償してくれる保険です。会社員であれば健康保険組合や社会保険からの給付がありますが、自営業やフリーランスにはその制度がありません。そのため、突然の入院や療養によって売上が途絶えると、固定費や生活費の支払いが一気に困難になります。
特にフリーランスでは、業務委託契約や個人取引のため「代わりに働く人」がいないケースが多く、休業による収入減が直接家計を圧迫します。就業不能保険は、こうしたリスクに備えるための重要な選択肢です。
雇用保険や傷病手当金が使えない場合の問題点

会社員が病気やケガで働けない場合、健康保険の「傷病手当金」で最長1年6カ月間、給与の約3分の2に相当する支給が得られます(厚生労働省:傷病手当金について(PDF))。また、詳細な受給条件や手続きについては、全国健康保険協会のページをご覧ください(全国健康保険協会:傷病手当金制度)。
さらに、失業時には雇用保険の給付も利用可能です(厚生労働省:雇用保険制度の概要)。しかし、自営業やフリーランスはこれらの制度に加入できません。
結果として、療養期間中の収入源は「貯蓄」「家族からの支援」「民間保険」のいずれかに限られます。十分な貯蓄がない場合、休業が長引けば生活資金が底をつき、事業継続すら困難になる可能性があります。
自営業・フリーランス向けプランの特徴(保障内容・免責期間)

自営業・フリーランス向けの就業不能保険には、以下のような特徴があります。
・保障内容:毎月定額の給付金(生活費や事業固定費に充当可能)
・支給開始までの免責期間:30日・60日・180日など契約時に選択可能
・支給期間:最短2年から、定年相当年齢まで保障するプランもあり
・就業不能の定義:医師の診断に基づく「所定の就業不能状態」
免責期間が短いほど早く給付が開始されますが、保険料は高くなります。逆に免責期間が長いと保険料は下がりますが、短期の休業では給付を受けられません。
保険料と給付額の目安(事例付き)

保険料は年齢・性別・免責期間・給付額・支給期間などによって大きく変わります。同じ条件でも保険会社によって差が出るため、必ず複数社から見積もりを取り、比較検討することが重要です。
事例:IT系フリーランスAさん(40歳)が病気で半年間入院・療養となった場合
免責期間60日 → 61日目から給付開始 → 毎月20万円 × 4カ月=合計80万円の給付
この給付金によって、家賃・光熱費・通信費・最低限の生活費をカバーでき、貯蓄の減少を最小限に抑えられます。
特徴比較:自営業対応プランの違い

商品名は伏せますが、主要な自営業対応プランには次のような違いがあります。
・免責期間が短く、短期の休業にも対応するプラン
・支給期間が長く、慢性疾患や長期療養にも対応するプラン
・保険料が安く、最低限の生活費を確保できるシンプル保障型
・事業固定費(事務所家賃や従業員給与)まで補償対象に含むタイプ
選ぶ際は「どの程度の休業期間に備えたいのか」「事業費用も保障が必要か」を明確にすることが大切です。
加入時の注意点(健康状態・職種制限)
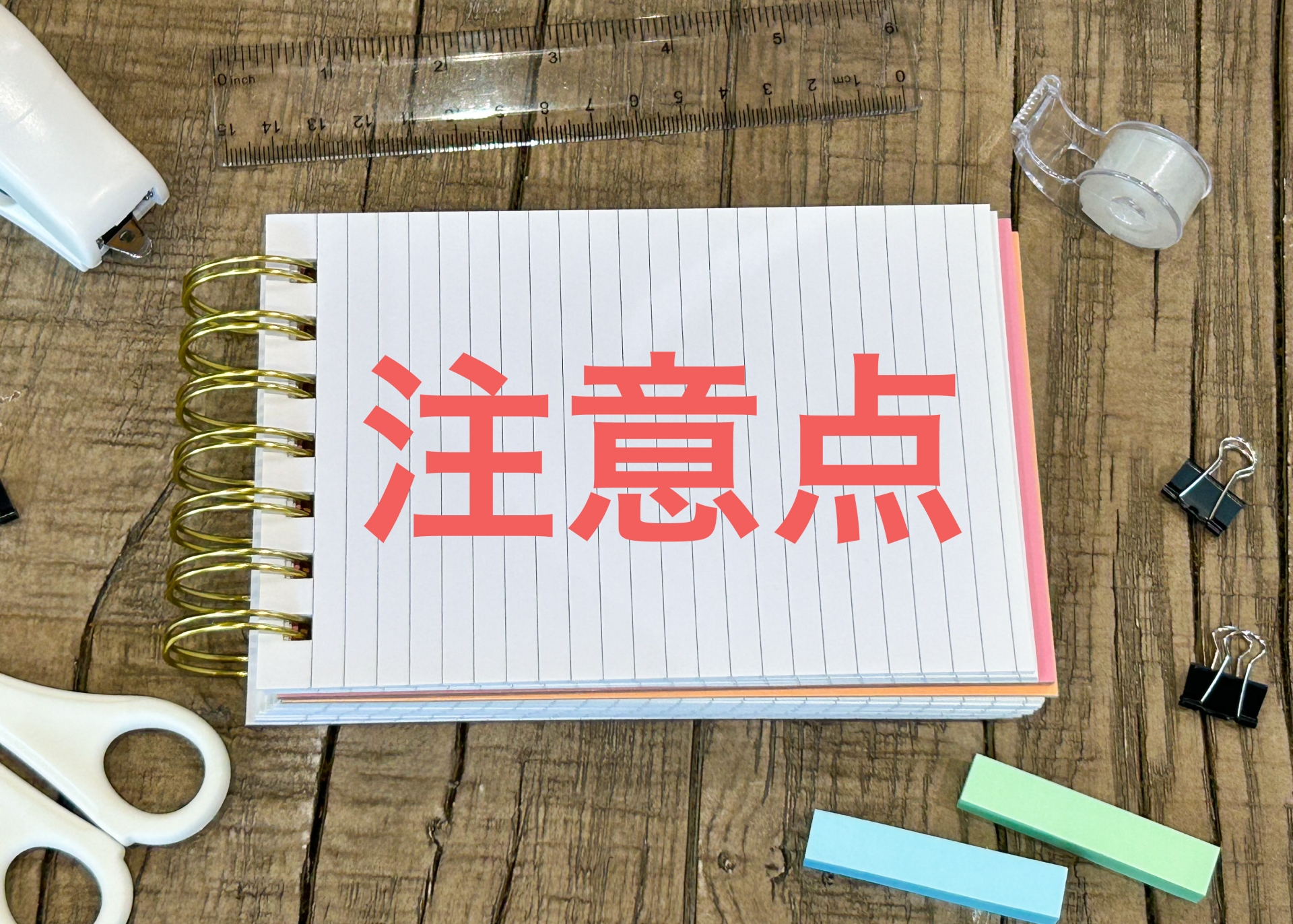
就業不能保険は、加入時に健康状態の告知や診査が必要です。過去の病歴によっては加入を断られることもあります。また、職種によっては保険料が高くなったり、加入できない場合もあります。特に身体的リスクの高い職業や、既往症を持つ方は事前に条件を確認しておきましょう。
さらに、自営業の場合は「就業不能」の定義が契約ごとに異なり、在宅で一部業務ができる場合は給付対象外となることもあります。この点も必ず確認が必要です(金融庁:保険の仕組みと選び方)。
まとめ:選び方の優先順位
自営業・フリーランスが就業不能保険を選ぶ際は、以下の優先順位を意識しましょう。
1.どの期間の休業に備えるか(免責期間・支給期間)
2.生活費だけか、事業固定費も含めるか
3.保険料と給付額のバランス
4.健康状態や職種による加入制限の有無
貯蓄や他の収入源と合わせて、必要な給付額と期間をシミュレーションしながら選べば、いざという時の安心感は大きく高まります。
制度のない自営業やフリーランスだからこそ、就業不能保険は「もしもの生活防衛資金」として有効です。将来の不安を減らすために、早めの検討をおすすめします。
本記事は、CFP資格保有者であり、J-FLEC認定アドバイザーの金子賢司が執筆しています。当記事の執筆者「金子賢司」の情報は、CFP検索システムおよびJ-FLECアドバイザー検索システムにてご確認いただけます。北海道エリアを指定して検索いただくとスムーズです。



